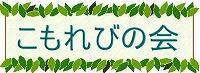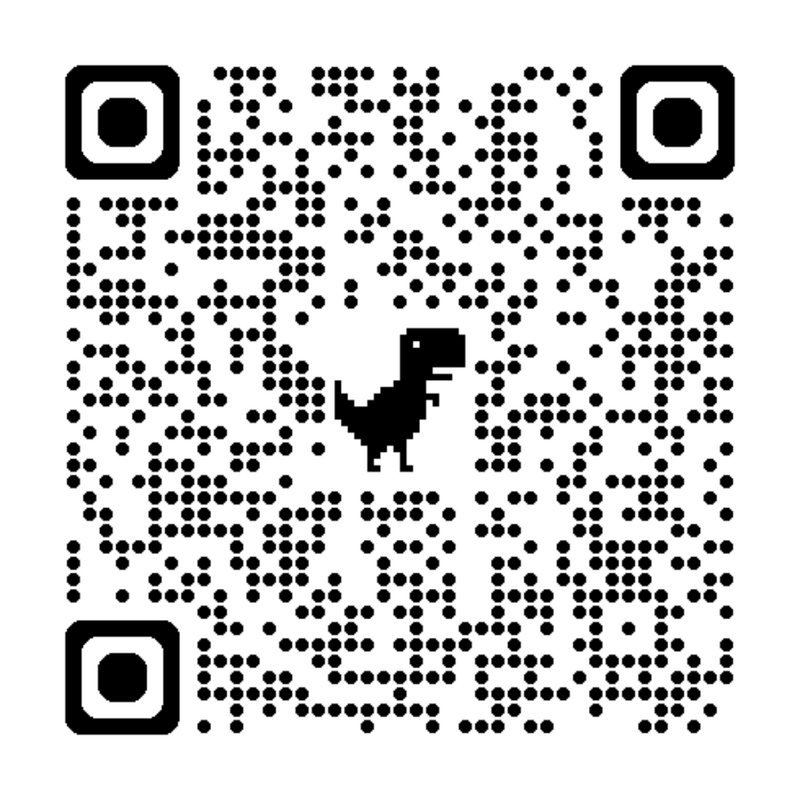今日は教員間の交流授業を行ないました。
1年2組で、特別支援学級ふたばの主任教諭が学級活動の授業を行ないました。

この授業は特別支援学級や特別支援教室では「自立活動」という教科等の学習活動です。
自立活動の学習指導要領には、
3人間関係の形成 (3)自己の理解と行動の調整に関すること (4)集団への参加の基礎に関すること
4環境の把握 (1)保有する感覚の活用に関すること (2)感覚や認知の特性について理解と対応に関すること
などの項目があります。
その解説を要約すると、
〇集団の中で状況に応じた行動ができるようになること。
〇集団の雰囲気に合わせたり、集団に参加するための手順やきまりを理解したりして、遊びや集団活動などに積極的に参加できるようになること。
〇視覚、聴覚など6つの感覚を十分に活用(自己でコントロールすることも含める)すること。
〇イメージを分かりやすい言葉で伝えること。
などが、子どもたちが本授業で達成すべき授業のねらいとして挙げられます。

上の画像は、授業で活用した視覚情報です。昔から「板書」と呼ばれているものです。
授業者は板書により、1単位時間の見通しをもたせます。
①は、はじめますからおわります、までの流れ
②は、具体的な活動の流れ
③の「いまここ」の表示で、何番目の活動が行われているか認識できます
④の時計で、終了時刻を示します。
⑤と⑥で、本時のめあてと学習の約束を提示します。
⑦「めのビーム」は、達成すべきめあてをイメージしやすくします。
⑧のイラストも、⑦の「めのビーム」と同様に、めあてをイメージしやすくします。
これらの情報を授業の導入部に提示することで、
・学習のめあてを理解したうえで、見通しをもって学習できる
・教師による音声言語のみの、長い説明や解説が不要になり、子どもの活動時間が保証できる
・逸脱行為に対する指導で、不要な時間を使わなくて済む
→低学年児童は、言葉だけの長い説明で重要事項を理解するのは難しい発達段階です。
などのメリットがあります。

1年生ですから、夢中になるあまり発言のルールなどを忘れてしまうこともあります。
それでも、授業者や(時には)子どもたちの中からの、「今日の約束は?」という言葉掛けだけで、ほとんどの子どもがめあてや学習のきまりに立ちかえられていました。

子どもたちが挙手している、上の画像は本時の終末に行なった振り返りです。
本時のめあてを達成できたか、と授業者から問われて、ほとんど全員の手が上がり、自分の言葉で説明できました。
もう一つ、特筆すべきは誰もトイレ等で退室しなかったことです。
(ちなみに本校では尿意や便意の我慢を強いてはいません。)
本授業におけるトイレの訴えの有無が問題ではなく、子どもたちが夢中で活動していると、40分程度の時間はすぐに経過してしまうことが分かりました。
終わった後も、またやりたい、の言葉がたくさん上がりました。
最後になりますが、特別支援学級教員と通常の学級教員の交流は、特別支援教育を広く施すためではありません。
この記事の冒頭で触れた「自立活動」の内容は、通常の学級等で扱っている特別活動の内容と共通しています。
よって、この授業は1年生の学級活動で行なっています。
小学校学習指導要領解説 特別活動編には、
2学級活動の内容 (2)(3)学級活動には、
「(2)日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全」と「(3)一人一人のキャリア形成と自己実現」という項目があります。
そこには(要約すると)
〇違いを尊重し合い、仲よくしたり信頼し合ったりして、よりよい人間関係を形成すること。
〇社会の一員として役割を果たすために必要となることについて主体的に考えて、社会参画意識の醸成をすること。
とあるように、学校内で所属している小集団や学級集団等において、人間関係を形成したり集団活動に参加したりする点では、自立活動と特別活動の学級活動の目指している理念は共通しています。
そのことを理解したうえで、両方のエッセンスを上手に混在させながら教育活動を実践することが大切だと考えます。
特別支援教育を呼び名の通り特別なものとして考えることはありません。
今日の授業のように、情報を精査して提示するという手法を用いただけで、学習効率のよい時間を過ごし、学習のねらいに迫っていけることも分かりました。


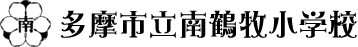











































































 伝え合う活動もやりました。
伝え合う活動もやりました。









































































 二つ目のめあてです。
二つ目のめあてです。

























 言葉の意味や特徴を、子どもたちの言葉でまとめてみました。
言葉の意味や特徴を、子どもたちの言葉でまとめてみました。























































































































































 コミュニケーションアプリやオンラインゲームで素性の分からない相手と繋がることの危険も話していただきました。
コミュニケーションアプリやオンラインゲームで素性の分からない相手と繋がることの危険も話していただきました。



















































 ふたば学級では、体育委員会の一員として、この動画に出演している5年生児童が実演を見せてくれました。
ふたば学級では、体育委員会の一員として、この動画に出演している5年生児童が実演を見せてくれました。