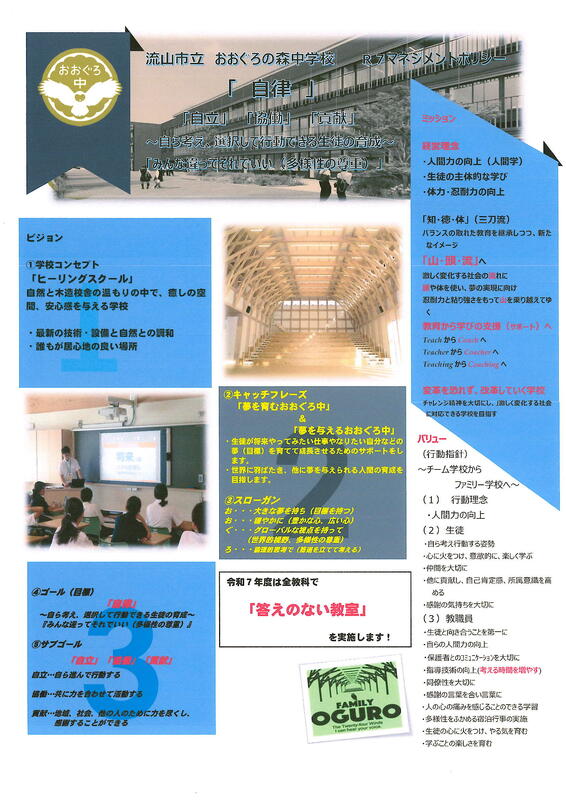学校の様子
新幹線の様子 修学旅行vol.3
予定時刻通り、新幹線は新大阪に向けて出発しています。
早朝の出発ということもあり、
車内では軽食(おやつ?)をとる生徒、友人とおしゃべりをする生徒、カードゲームをする生徒など様々です。
新大阪までの約2時間20分の旅を、それぞれの楽しみ方で楽しんでいます!
東京駅に集合です! 修学旅行vol.2
全班無事に東京駅に集合しました!
これから新幹線乗車ホームに向かいます。
出発しました! 修学旅行vol.1
いよいよ待ちに待った修学旅行当日です!
きれいな青空が広がる中、
3年生はみな元気よくおおたかの森駅に集合し、出発していきました!
天気が良すぎて暑さが心配ですが、
体調に気をつけながら楽しんできてください!
学校長より 修学旅行に寄せて.pdf
荷物が京都へ出発!
いよいよ明日から大阪万博、京都への修学旅行です。3年生の皆様、楽しみですね。そして、在校生・保護者の皆様、修学旅行の様子はリアルタイムでホームページにアップしていきますので楽しさを共有してくださいね。
本日は一足お先に荷物が京都へ出発しました。保護者の皆様、早朝から荷物の運搬等、ご協力いただきましてありがとうございました。
ある生徒がトラックに荷物を積み込む時に発した言葉が印象に残ったので紹介します。「先に京都に行っててね!バイバイ!」この言葉を聞いて、朝から笑いと温かな気持ちになりました。それでは、荷物の積み込みの様子をお届けします
先生方も積み込みの手伝い、ありがとうございました。
荷物、いってらっしゃーい! 京都の宿で待っててね!
何のために、誰のために歌うのか? 2年生、合唱コンクールに向けて、始動!!
今年度の合唱コンクールはいつ開催されるか知っていますか?
正解は、11月15日です。
もう曲決め?と思う人もいるかもしれません。しかし、体育祭と同じくらい合唱コンクールは、学校生活の中でも特別なイベントのひとつです。クラス全員が一つの目標に向かって努力し、協力し合いながら音楽を作り上げる過程は、仲間との絆を深める貴重な経験になります。このコンクールでは、どの曲を歌うかをみんなで決めます。曲選びはとても大事なことですが、それ以上に大切なのは、みんなが楽しみながら練習に取り組み、全力で歌い切ることです。曲が決まった後は、練習を通して一人ひとりの成長を感じながら、みんなで素晴らしいステージを作り上げてくれることを期待しています!

一曲、一曲、合唱委員が熱い思いを伝えながら真剣に聴いています。人によって感じ方は様々。今までの経験した、嬉しいこと、楽しいこと、ちょっぴり苦い思い、つらかったこと、、曲の歌詞を見ながら共感するものもあったのではないでしょうか?
選曲のポイントは
・ みんなが歌いたい曲を選ぶ
・協力して歌いやすい曲を選ぶ
・クラス全員の個性を活かせる曲を選ぶ
曲候補としては、自然や希望、友情をテーマにした感動的な歌から、元気でポジティブな曲まで多彩なジャンルが揃っています。
・青葉の歌
・時の旅人
・予感
・春に
・プレゼント
・I♡×××
・結 ーゆいー
・gift
・君の隣にいたいから
・INTERA PAX 地に平和を
・消えた八月
・未来へ
・天の川
・次の空へ
・心の翼君が広げたら
・奇跡
・僕らはいきものだから
曲名を聞いて、様々な歌手を思い浮かべる方もいるのではないでしょうか?
近年ではNHKコンクールでもJ-POPの曲が課題曲として選ばれています。
J-POPは、特に若い世代にとって身近で馴染みがあり、普段聴いている音楽が合唱曲として取り入れられることで、より感情移入しやすく、歌うことに対して楽しさや意欲を感じやすいです。また、J-POPの曲は、メロディーが覚えやすく、リズム感も良いため、合唱として歌う際にも調整しやすい特徴があるそうです。しかし同じぐらい魅力的なのが、昔からある合唱曲。もしかしたら親子2代で同じ曲を歌う機会があるかもしれませんね。
中には、歌が苦手な人、得意不得意があるかもしれません。悩むことも。もしかしたら仲間と意見がぶつかることもあるかもしれません。そんな時は、歌い終わった後、練習期間を終えた後、どんな人になっていたいのか、どんなクラスになっていたいのか、仲間とどんな関係を作りたいのか思い描けるとよいですね!!
創造・協調・感謝 ~思い出と学びを刻み、仲間とともにStep up!~
1年生の校外学習、2年生のGrowSchoolを終え、残すは3年生の修学旅行となりました。
今週の18(水)・19(木)・20日(金)の3日間で、大阪関西万博と京都市内を巡ります。
今日は5時間目に修学旅行での、行程の細かな点や安全面、緊急時の対応について再確認しました。
時おり、メモを取ったり、仲間と確認したりと、大切な時間となりました。生徒総会・市内大会・定期テストと他の活動も並行してきた3年生ですが、いまは修学旅行が目前に迫っています。学年フロアでは、持っていくお菓子の話題や万博や京都で撮りたい写真、買いたいお土産など、修学旅行に向けて、ドキドキがいっぱいです。
『創造・協調・感謝 ~思い出と学びを刻み、仲間とともにStep up!~』
①修学旅行で大阪関西万博に行って未来のこと、京都では過去や歴史について学び、過去と未来を学んで、これからの自分をどのように創造していくかを考える。
②新しいクラスの仲間と協力し、修学旅行を通して団結力を高め、絆を深められるように成長する。
③修学旅行に携わっているすべての人に感謝の気持ちをもち、自分たちも感謝される人になる。
今回の修学旅行のスローガンです。
修学旅行を体験したあとの学年の姿を想像し、実行委員を中心に、学年全体が自ら考え設定したものです。
また、スローガンと併せて、実行委員長の酒巻さんから学年全体へ向けたメッセージがしおりに掲載されています。いくつか抜粋して紹介します。
・スローガンを達成することで、おおぐろの森中学校の最高学年としての自覚を持てるようになってほしい。
・万博や京都巡りでは、公共の場を班員だけで行動するからこそ、一人ひとりの自律が求められる。
・修学旅行に向けて、修学旅行の先まで見通して、自分の目標をたて、大切にしながら活動してほしい。
・修学旅行を全力で楽しんでほしい!
「自律」をもとに、おおぐろの森中で様々な活動をしてきた3年生。修学旅行全体の意義や目的も自分たちのことばで共有し、実行できるように頑張っています。
最初で最後の修学旅行、3日間で楽しみながら、学年・学級・一人ひとりがレベルアップしていくことを考えると、とても楽しみです。
【しおり表紙絵コンテスト】
しおりの表紙絵を3年生全体へ募集しました!候補作はこちらです!

学年 みんなで投票し、表紙に選ばれた作品はこちらとなりました!
~まめ知識~
・万博とは「万国博覧会」の略称
・1851年に、イギリスのロンドンで「第1回万国博覧会」が開かれた。(日本は第12代将軍・徳川家慶の時代ペリー来航の2年前) 歴史の教科書にも掲載されています。
・1851年の万博の目的は、「世界中のすぐれた「物」を見せ合い、産業を発展させる」こと
・現代の万博の目的は、「世界の課題や未来の社会について考え、協力する」こと
2025年 大阪・関西万博 テーマ:「いのち輝く未来社会のデザイン」
努力の軌跡がここに!~第1回定期テスト~
本日、今年度最初の定期テストが実施されました。
特に1年生にとっては、中学校に入学してから初めての定期テストということで、少し緊張した面持ちで登校してくる姿が印象的でした。初めての中学校のテストはどうでしたか?試験内容だけでなく、服装や姿勢、試験の受け方などたくさん「考えた」1日になったのではないでしょうか。
~1年生テストの様子~

一方、3年生も気合い十分。前日には数学の学習会に多くの生徒が参加し、その熱心さに先生方も驚いていました。試験の合間の休み時間には、教科書やワークを手に、友達同士で問題を出し合いながら学習に励む様子が数多く見られました。


~3年生テストの様子~
また、テスト当日だけでなく、スタディーウィーク中の取り組みも、とても充実していました。
2年生のフロアを覗いてみると……「本気で当てにいく!」と題して、気合いの入った予想問題が掲示されていました!学習委員さん、心強すぎます!!
~2年生テストの様子~

先生に質問をしたり、友達同士で教え合ったりする中で、「わかった!」「できた!」と笑顔を見せる生徒たちの姿がとても印象的でした。
テストはもちろん当日の成果も大切ですが、それ以上に、そこへ向けて努力する過程に大きな意味があるのだと、改めて実感することができました。
さて、テストが終わって少しほっとしたところで、次に待っているのはテスト返却の時間です。
今回のテストで、皆さんの努力の成果はしっかりと発揮できたでしょうか?
点数の高い・低いだけにとらわれず、自分自身のこれまでの学習の歩みを振り返り、「次はどうするか」を考えることが、より大きな成長につながります。
今回の経験を、ぜひ次回へとつなげていきましょう。
仲間とともに創る旅のかたち 〜修学旅行に向けた3年生の姿〜
6月11日(水)5校時、12日(木)6校時の時間を活用して、3年生は来週に迫った修学旅行【6月18日(水)~20日(金)】に向けた点呼・隊形練習、新幹線の乗降練習を体育館で行いました。この集会は、教員が直接指示を出すのではなく、修学旅行実行委員の生徒たちが中心となって、進行・指示・運営を行いました。
練習開始時には、実行委員が体育館前方に立ち、隊形や並び順についての説明を行いました。「今から〇〇班から順に移動隊形に整列してください」「〇組と〇組は右側、〇組は左側に並びます」など、全体を見ながら一つ一つ丁寧に指示を出していきました。
さらに、生徒全体の動きを見ながら「並びの間隔を少し詰めてください」「移動の際は班ごとにまとまって動きましょう」と、集団行動の細かな部分にまで注意を促す場面もありました。
その指示を受けて、各クラスの班長たちがすぐに自分のクラスのメンバーへ指示を伝えていました。自ら前に立ち、仲間の列を確認しながら「後ろの人、もう少し前に来てほしい」「進行方向はこっちだからステージ側を向いて」といった具体的な言葉かけを行いながら、列を整えていく姿が見られました。中には、仲間の不安そうな表情に気づき、手助けをする生徒の姿もあり、相手を思いやる様子に、これまでの学年の絆や信頼を感じとることができました。
また、新幹線の乗降練習では、「乗車口は前と後ろの2か所あります。前側からは〇組と〇組が…後ろ側からは〇組と〇組が乗車します」といった具体的な分担指示も実行委員からなされ、混乱を最小限に抑えたスムーズな動きができていました。時間や安全を意識した指示が適切に出され、それに応えるように生徒たちも落ち着いて行動していた様子からは、集団全体としての高い意識と自律が感じられました。
この2日間の練習を通して、強く印象に残ったのは、「自分の役割を果たそうとする姿勢」と「仲間のために行動する意識」が、学年全体に自然と浸透していたことです。リーダーとしての立場にある実行委員や班長だけでなく、指示を受ける側の生徒たちも、その意図を理解し、必要な行動を考えて動く。その積み重ねが、集団の秩序とまとまりを生み出していたように思います。
修学旅行は、ただの「思い出づくり」の場だけではありません。仲間と協力して動くこと、自分の行動に責任をもつこと、公共の場でマナーを守ること。そうした多くの学びが凝縮された、大切な学校行事です。今回の練習で見せてくれた生徒たちの姿からは、本番に向けての準備が着実に進んでいるだけでなく、一人ひとりが「良い旅行にしよう」という前向きな意志をしっかりと抱いていることが伝わってきました。
出発までの残りわずかな時間も、さらに準備を重ね、気持ちを高めていく3年生の姿が見られることと思います。保護者の皆さま、地域の皆さまにおかれましては、引き続き温かく生徒たちの成長を見守っていただければ幸いです。今後とも、本校の教育活動への御理解と御協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
旬の野菜に触れよう~そら豆さやむきチャレンジ!
梅雨入りとなり、雨の日が続いていますね☔
さて、本日は1年生の様子をお伝えします。「食事の重要性、心身の健康のために、食材への興味・関心を高めていくことを目的とし、旬の食材を「生きた教材」となるように給食に提供していく」、「生産者や調理してくださる方々に感謝する気持ちを育てる。」といった『食育』を目的として1年生がそら豆のさやむき体験をしました。
多くの生徒が初めての体験だったと思います。「そらまめってこんなにフワフワしてるの!?」と感動や驚きの声が続出!”そらまめ”の手触りや香りなどに親しむ姿が見られました。うまくできている級友に対して「コツは??どうやってやるといいの??」と聞きながら、協力して取り組みました。
本日1年生が頑張ってむいたそらまめは、明日の給食メニューに「ゆでそらまめ」として提供されます。生産者の方や調理師さんへの感謝の気持ちを持ち、美味しくいただきましょう。
ご家庭でも調理のお手伝いや、旬の食材を調べるなど食に親しんでほしいと思います。
また、毎日「今日の献立紹介」で給食のメニューの紹介や調理師さんの姿など更新しています。ぜひご覧ください!
「学校運営協議会」が開催されました
本日10時から、おおぐろの森中学校区第1回目の学校運営協議会が、おおぐろの森小学校を会場として、開催されました。
コミュニティスクール(学校運営協議会)は、学校の基本方針を踏まえつつ、保護者や地域の意見を学校運営に反映し、学校運営を充実させていくための仕組みです。
学校運営協議会の3つの機能として、①校長の作成する学校運営の基本方針を承認すること。②学校運営について、教育委員会又は校長に意見を述べることができること。③教職員の任用に関して、教育委員会に意見を述べることができること。という役割が挙げられています。
これらを踏まえ、第1回の大きな目的は、各校の学校運営の基本方針を理解していただき、承認をしていただくことです。
おおぐろの森中・おおぐろの森小・小山小の校長先生から、パワーポイントを使って各校の学校運営についての説明が、それぞれありました。そして、各校より説明があった学校運営の基本方針について、委員の方々から、ご意見や感想、質問等をいただき、それに対して校長先生が回答や詳しい説明を行いました。

ご意見や感想、質問などのやり取りの後、3校全ての学校運営の基本方針について、参加された委員の方々によって、承認されました。
続いて、グループ協議を行いました。グループは2つに分かれ、1つは「マーケティングおよび学校評価に関するプロジェクトチーム」と、「学習支援およびボランティアに関するプロジェクトチーム」です。
最後に、それぞれのグループで話し合った内容について、代表者が発表して共有しました。
今回の学校運営協議会において、様々な立場や視点からの貴重なご意見、ご提案を委員の方々からたくさんいただき、とても有意義な協議会となりました。この場をお借りして御礼申し上げます。ありがとうございました。
初めてのスタディウィーク…!!
突然ですが、問題です!!
(1)182を素因数分解しなさい。
(2)素因数分解の結果をもとに、182の約数をすべて求めなさい。
答え:
(1)182 = 2 × 7 × 13
(2)1,2,7,13,14,26,91,182
これは、実際に1年生が学習した数学の内容です。
皆さん、覚えているでしょうか?
中学1年生でこのような内容を学んでいると考えると、改めて驚かされますね。
校外学習や市内大会も終わり、校内は学習モードの雰囲気になってきました。
そして、いよいよ今週末には「第1回定期テスト」が実施されます。
2・3年生は、きっと準備万端だと思います。
一方で、1年生にとっては中学校生活初めての定期テスト。不安や緊張を感じている様子が見られます。
それでも、授業中に積極的に先生や友達に質問する姿が多く見られ、「おおぐろプライド」が着実に育っていると感じます。
どの学年にとっても、「前学年の内容を復習すること」はとても大切です。
たとえば数学であれば、「正負の数」を学ぶためには、小学校で習った四則演算(足し算・引き算・かけ算・わり算)
がきちんと理解できていることが前提となります。
復習ができていれば、あとは新しい学びにどんどん挑戦するだけです!
授業や小テストなどを「やりっぱなし」にせず、間違えた問題はきちんと解き直し、
理解を深めていくことで、学びに意味が生まれます。
復習の習慣を身につけることが、これからの力になります!
第1回定期テストが、生徒の皆さんにとって実りあるものになるように。
結果だけに目を向けるのではなく、しっかりと振り返りを行い、日々の学習を深めていきましょう。
市内大会を終えて… 修学旅行に向けて…
1か月に渡る市内大会が終わりました。
それぞれがこれまでの練習の成果を発揮し、一生懸命頑張る姿がとても印象的でした。各部活の部長に、市内大会を終えて、また夏の総体やコンクールに向けての抱負を聞きました。
吹奏楽部 宇佐美さん
7月のコンクールに向けて、昨年の銀賞という悔しい結果をばねにし、限られた練習時間をしっかりと活用しながら2曲仕上げていきます。きれいな音色を届けられるように頑張ります。
野球部 佐野さん
市内大会は初戦敗退という悔しい結果に終わりましたが、自分たちの目標である県大会初戦突破に向けて、残り少ない時間ですが、日々練習を頑張っていきます。
陸上競技部 宮本さん
市内大会では女子が総合3位という結果を残すことができました。今後はそれぞれの課題を解決し、総体ではよりよい結果を残せるように頑張ります。
サッカー部 春日さん
市内大会では初戦敗退という悔しい結果でしたが、夏の総体では公式戦2勝という目標を達成できるように、日々練習を重ねていきます。
男子卓球部 鈴木さん
一人ひとりが頑張り、個人団体共に優勝することができました。その結果に満足せず、もっと強くなるということを意識し、総体では県大ベスト8を目標に練習に励んでいきます。
男子バドミントン部 江口さん
市内大会では自分たちの良さや弱点が明確になりました。葛北総体に向けて、日々自分の課題点を意識し、もっと努力してベストを尽くせるように頑張ります。
女子ソフトテニス部 豊田さん
市内大会では、よい結果が出せなかったので、葛北総体では全力で勝ちにいけるように、残り少ない練習や練習試合を一つ一つ大切に活動していきたいです。
男子ソフトテニス部 戸塚さん
市内大会では個人、団体共に3位という悔しい結果に終わってしまったので、総体に向けて限られた時間を有効に活用し、葛北大会では優勝して県大会ベスト16に入れるように頑張ります。
女子卓球部 三浦さん
市内大会では準優勝という悔しい結果になりました。夏の総体では、一人ひとりが全力を出し切れるように日々の練習一秒一秒を大切にし、よい結果で終えられるように頑張ります。
総合文化部 岡田さん
残り短い活動時間ですが、仲間と協力して作品制作をしていきます。また一人ひとりが作品をつくりあげ、創作する力を高めて行きます。そして体育祭の横断幕や合唱コンクールの看板作製に生かせるように取り組んでいきます。
女子バスケットボール部 橋本さん
市内大会では自分たちの思うようにいかないこともありましたが、総体では全員が納得いくプレーをするために、日々の練習に全力で取り組みたいと思います。
バレーボール部 坂本さん
市内大会では4位という結果でした。今までの大会では悔しい思いをしてきたので、総体では県大会出場という目標を達成できるように、残り少ない練習を頑張っていきます。
女子バドミントン部 武藤さん
総体に向けて、全員が自分のベストを出せるような大会にしたいです。そのために練習への取り組みや試合への臨み方を、3年生中心に意識を上げていきます。後輩にも3年生の思いを伝えていこうと思います。
男子バスケットボール部 福永さん
市内大会では自分達の思うような試合運びができなかったので、課題であるパス回しやリバウンドを改善し、総体ではベスト4を目標に頑張っていきます。
どの部活動も、しっかりと前を見据えていました。夏の葛北総体やコンクールが楽しみですね。
さて、今日の6時間目に3年生の教室を覗いてみました。
なにやら班で何かを決めているようです…いったい何をしているのでしょうか…
スマートフォン??班で活動しているのに、スマホを片手に…
いよいよ来週の18日(水)から行われる修学旅行の1日目、大阪万博班別行動の計画をたてていました!
代表者のスマートフォンやタブレットを使って、7日前抽選予約をしていました。
(3年生保護者の皆様ご協力ありがとうございました。)
まだまだ混雑が予想される大阪万博ですが、一つでも多くのパビリオンが見学できるといいですね!
ドキドキしながら抽選結果を待ちましょう!
市内大会 結果報告
令和7年度 市内大会での本校の結果は以下のとおりです。
どの部活も、一生懸命頑張りました。この経験をもとに、3年生にとっては最後の大会である葛北総体に向け、取り組んでいってほしいと思います。
【卓球部】
男子団体戦 優勝
女子団体戦 準優勝
男子個人戦 男子シングルス 2年吉藤さん 優勝
女子シングルス 3年三浦さん 優勝
女子シングルス 2年富田さん 第3位
男子ダブルス
3年佐藤さん・2年武田さんペア
第3位
【ソフトテニス大会】
男子団体戦 おおぐろの森中 3-0 常盤松中 勝利
おおぐろの森中 0-2 八木中 惜敗
第3位
女子団体戦 おおぐろの森中 0-2 北部中 惜敗
男子個人戦 3年戸塚さん・山﨑さんペア
第3位 県大会出場
女子個人戦 3年豊田さん・新飯田さんペア
ベスト32
【バレーボール部】
予選リーグ おおぐろの森中 2-1 東部中 勝利
おおぐろの森中 2-0 西初石中 勝利
※予選リーグ1位で突破し決勝トーナメントへ進出
決勝トーナメント おおぐろの森中 0-2 南流山中
惜敗 第4位
【バドミントン部】
男子団体 おおぐろの森中 2-0 おおたかの森中
勝利
おおぐろの森中 0-2 南部中 惜敗
準優勝
女子団体 おおぐろの森中 0-2 北部中 惜敗
おおぐろの森中 0-2 南部中 惜敗
第3位
【野球部】
1回戦 おおぐろの森中 1-7 八木中 惜敗
【サッカー部】
1回戦 おおぐろの森中 1-1(PK3-4) 常盤松中
惜敗
【陸上競技部】
女子総合 第3位
女子共通1500m 3年小森さん 優勝
女子共通800m 3年小森さん 準優勝
女子共通走り高跳び 3年髙橋さん 準優勝
女子共通走り幅跳び 3年櫻田さん 第3位
【バスケットボール】
男子 vs おおたかの森中 惜敗 vs 東部中 惜敗
vs 常盤松中 惜敗 vs 西初石中 勝利
女子 vs 東深井中 惜敗 vs 南部中 惜敗
vs 八木中 惜敗 vs 北部中 惜敗
【特設水泳部】
400m自由形 2年森さん 優勝
「答えのない教室パート2」いよいよ発売!紀伊国屋書店流山おおたかの森店でパネル展開催!
いよいよ発売!「答えのない教室パート2」
「考える力」をはぐくみ、子ども達をワクワクドキドキさせる授業の全貌を大公開!
教室が笑顔で満たされる授業。3人ひと組になり、時間を忘れて課題に取り組む生徒たち。教師はそれをそっと見守り、必要な時に必要な手助けをする。「答えのない教室パート2」は、おおぐろの森中学校 池田教諭における実践の記録です。
失敗例も含めて「15の題材」(理科での実践例も掲載)を挙げ、授業の内容や進め方を決めた背景、教室の様子、そして授業を受けての生徒たちの感想なども紹介しています。数学に苦手意識のあった生徒がその面白さや奥深さに開眼するさまに触れれば、教師も生徒も保護者も必ずや「こんな授業がいい!」と思うはずです。日々の教授法に悩んでいる教師の方々だけでなく、数学や数学教育に関心のある多くの方に読んでいただければと願っています。
紀伊国屋書店流山おおたかの森店店長様のご厚意で、先行販売そして、おおぐろの森中学校のパネル展を開催していただいています。
井崎市長、吉田教育長へ池田教諭と新評論 武市社長と共に刊行の報告に行きました。
市内大会2日目!団体戦&決勝トーナメント!!!……その裏で、最後の大会に向けて。
市内大会2日目が開催されました。
卓球部やソフトテニス部は団体戦へ。
バレーボール部は、リーグ戦を1位通過しているので決勝トーナメント戦へ。
バスケットボール部は、1日目の頑張りを、活躍を、糧として2日目に臨みます。
3年生中心に大会に出場しています。
「最後の市内大会」ということで、気合の入り方が違いました。
最後の一球まであきらめないプレー、絶対に勝ってやる!!!!!という気迫。
3年間、頑張ってきた証がそこに見えた気がしました。
「勝利」は、優勝した1チームしか得ることができません。
それ以外のチームは必ずどこかで「敗け」を経験します。
その時に「やり切った!」「このチームでよかった!」「ペアで頑張れた!」
……と思えたら素敵ですね。
もちろんやるかには「勝ち」を目指しますが、それだけでない「価値」を見いだせることが部活動のいいところだな~と思っています。
がんばれ!!!!!おおぐろ中!!!!!
その裏で……。
惜しくも敗退したり、日程の関係で市内大会が終了したりして、夏の最後の総体に向けて練習に励んでいる部活動も多くあります。
また、夏休みに行われるコンクールに向けて練習する部活。
己のスキルを磨く部活。
頑張り方はそれぞれです。熱い熱い夏になること間違いないですね!
チームおおぐろ……いや!ファミリーおおぐろで闘いましょう!!!!!
市内大会2日目ダイジェスト版
熱き一日! 本日開催の市内大会2日目の様子をダイジェスト版でお届けします。
ちば夢チャレンジ(千葉ジェッツ)
6月5日(木)、おおぐろの森中学校体育館にて、1年生を対象にプロバスケットボールチーム「千葉ジェッツ」より渡邊様を講師にお迎えし、特別授業を実施しました。この授業では、バスケットボールの魅力や楽しさに触れながら、自身のキャリアや人生に生かしていくことを目的とした内容が展開されました。
授業では、千葉ジェッツの選手の活躍に関するお話に加え、実際に体を動かす体験も行われました。
「移籍ゲーム」と呼ばれる活動では、周囲をよく見て動くことや、広い視野を持つことの大切さについて学びました。
また、「3人組のパス練習」では、ただパスを回すだけではなく、タイミングを意識し、正確にパスを出すことの難しさと面白さを体感しました。
「シュートゲーム」では男女に分かれて競い合い、真剣に取り組む生徒たちの姿が見られました。
そのほか、ドリブル練習も行われ、生徒たちは生き生きと活動しながら、バスケットボールの楽しさを実感していました。
授業後の振り返りでは、次のような感想が寄せられました。
「シュートゲームでは、これまで知らなかったフォームを学ぶことができました。バスケットボール部の練習でも生かしていきたいです。」
「3人組のパス練習では、タイミングを考えたり、まっすぐにパスを出すことが難しかったけれど、とても楽しく活動できました。チームプレーの大切さを改めて感じました。」
「バスケットボールを楽しく学ぶことができ、自分の部活動でも楽しむ気持ちを大切にしていきたいと思いました。」
「富樫選手が167cmの身長で活躍していることに驚きました。千葉ジェッツがとても強いチームだということも知ることができました。」
生徒たちにとって、プロの現場に触れながらスポーツの奥深さを学ぶ、貴重な機会となりました。
1・4・5組
2・3・6組
生徒総会 ~理想のおおぐろの森中学校のつくり方~
本日、令和7年度生徒総会が行われました。
生徒会執行部では、昨年度のうちから全校討議について検討を重ねてきました。どんなテーマを設定すると、全校生徒一人ひとりが自分のこととして考えられるかなど、意見を出し合い、準備を進めてきました。各委員会や部活動でも1年間の活動計画や予算案を考えてもらいました。
今年度の全校討議のテーマは「理想のおおぐろの森中学校のつくり方」でした。事前にアンケートや2回の学級討議で「理想のおおぐろの森中学校とは?」「おおぐろの森中学校の現状」について意見を集めて議論を重ね、
「明るく盛り上がれて、行事でやりがいを感じられる学校」
「いじめのない、助け合いのできる、あたたかい学校」
「全員が個性豊かでのびやかな学校」
の3つを理想の姿として設定し、迎えた生徒総会当日。
この3つの姿に近づくためにできることは何か?全校討議が始まると、各学級から活発に意見があがりました。「〇〇委員会のこの活動が理想の姿につながるのでは?」「このような活動を行うと、理想の姿に近づけると思う」「違う学年との交流が増えれば、互いの個性に気づく機会が増えると思う」「各行事のことをもっと宣伝すると良い」「活躍できる人を増やせるような工夫がほしい」など、一人ひとりが真剣にテーマに向き合い、全校生徒の前で堂々と発言する姿がたくさん見られました。聞く側も耳をしっかり傾け、発言者に拍手を送るなど、明るく前向きな話し合いが行われていました。
今回の討議で出た意見をもとに、「理想のおおぐろの森中学校」に近づく取り組みが、活発になっていくことを期待しています!
また、生徒総会の終了後、流山市役所 子ども家庭課の方から、「流山市こども会議」の案内がありました。
学校のことを真剣に考え、発言できるおおぐろの森中生。ぜひ、その力を流山市のためにも発揮してほしいなと思います。
想像と協働~これからの学びへ~ 1年生校外学習総集編 vol.10
本日、1年生は中学校に入学してはじめての校外学習に行きました。
各クラスごとにバスを乗り、、午前は埼玉県東松山市にある丸木美術館を見学しました。
バスの車内では、レク係が考えたバスレクを行いました。ビンゴや自分たちで作成したクイズを通して、楽しむ様子が見られました。
丸木美術館に到着後、職員さんが生徒たちに丸木美術館について説明してくれました。その中で、「今の時代でもウクライナ問題など、通じるものがある。形を変えていつの時代にも暴力はある。それを知ってほしい。絵を通し、想像力を広げ、人の痛みを感じていってほしい。」といったお話が印象に残っています。
その後、生徒たちは、原爆の悲惨な現実を描いた「原爆の図」を静かに、そして真剣な表情で見つめていました。戦争によって奪われた命や、そこに生きた人々の思いに心を寄せ、「人の心の痛みがわかる学習」として、命の重みについて深く考える貴重な時間となりました。
午後は国営武蔵丘陵森林公園に移動し、班ごとにオリエンテーリングを行いました。生徒たちは地図を片手に、班の仲間と声を掛け合いながらポイントを探し、自然の中で協力して課題に挑戦していました。時には苦戦しながらも、最後まであきらめずに取り組む姿が印象的で、活動を終えた後には達成感と仲間との絆が一層深まったようでした。
今回の校外学習を通して、生徒たちは「命の尊さ」と「仲間との協力の大切さ」という、大切な学びを得ることができました。この経験をいかして、今後の生活も頑張ってほしいと思います。
無事到着しました☆★想像と協働 1年生校外学習 vol.9
行きの事故渋滞の影響で、丸木美術館への到着が1時間遅れましたが、全ての行程を終え、無事流山へ帰ってきました~~
想像と協働~人を想い、自律心と共感する力を養う校外学習~
というスローガンのもと活動し、
午前は丸木美術館で人の心の痛みを想像し、
午後はオリエンテーリングで班で協働して活動しました。
学校では経験できない経験をした1年生
ぜひ今日の体験をこれからの成長の糧にしてほしいと思います。
1年生のみなさんお疲れ様でした!!
集合写真 1年生校外学習 vol.8
予定では昼食の前に撮る予定だった集合写真ですが、
オリエンテーリング後に変更になりました。
たくさん歩いた充実感が、顔に表れているのかな??
皆良い笑顔です!
オリエンテーリング 1年生校外学習 vol.7
お昼ご飯も食べ、マップを受け取ったらオリエンテーリングのスタートです!
広い公園をマップを頼りに班で協力し歩き回りました!!
見事パーフェクトだった班と、総得点が一番高かったクラスは後日学校で表彰されます!!
昼食タイム! 1年生校外学習 vol.6
天候にも恵まれたので、運動広場でレジャーシートを広げ、みんなで昼食を食べました
外で仲間と食べるご飯はまた格別です☆☆
国営武蔵丘陵森林公園到着 1年生校外学習 vol.5
国営武蔵丘陵森林公園に到着しました!!
みんな元気いっぱいです!!
昼食を食べて、午後からはオリエンテーリングです☆☆
丸木美術館見学 1年生校外学習 vol.4
学芸員からの講話が終わり、見学がスタートしました。
見て感じたこと、学んだことを必死にメモをしていました。
丸木美術館で学芸員からの講話 1年生校外学習 vol.3
丸木美術館の講堂で学芸員の関町様から、丸木美術館について説明をしてくださいました。
原爆の図丸木美術館は、画家の丸木位里・丸木俊夫妻が、共同制作《原爆の図》を、誰でもいつでもここにさえ来れば見ることができるようにという思いを込めて建てられた美術館です。
丸木夫妻は、原子爆弾が投下された直後の広島にいち早くかけつけ、戦後の米軍占領下、原爆被害の報道が厳しい検閲を受けていた時期に《原爆の図》連作を描きはじめました。
そして日本全国を巡回し、公民館や寺院、学校の体育館などで展覧会を開催し、被爆の実情を広く伝えました。その後も、戦争や公害(水俣病)、アウシュビッツ、南京大虐殺など、人間が人間を傷つけ破壊することの愚かさを生涯かけて描かれています。
今の時代(ウクライナ)等通じるものがあります。絵を見ることで、人の痛みを感じとってほしいです。
丸木位里・丸木俊夫妻(丸木美術館HPより)
丸木美術館に到着! 1年生校外学習 vol.2
バスは、事故渋滞に巻き込まれ、1時間ほど行程より遅れていますが、
生徒たちは元気にバスレクを楽しみ、丸木美術館に到着しました!
これから美術館を巡ります。
最高の校外学習日和! 1年生校外学習 vol.1
昨日まで雨が降り……ずっと雨が続くような予報も出ていましたが……
本日は最高の校外学習日和になりました!
1年生も朝一から元気に集合場所へ向かっていました。
今日は晴れて本当によかったと思いますが、気温が上がっています。
皆さん水分補給を確実に行って、楽しい校外学習にしてくださいね。
バスの中でも準備万全!
しゅっぱーつ!
この後も1年生の校外学習の様子をお伝えします。
1年生の皆さん、楽しんできてくださいね!
校長より「1年校外学習によせて」
Let's think about UD!!
6月1日は「ルビ振りの日」です。皆さんは「ルビ」という言葉をしっていますか?
ルビとは、漢字の上や横に小さく書かれた「ふりがな」のことを指します。読むことに困難さのある子どもたちにとって、このルビは文章の理解を助け、自分の力で学習を進めるための大切なサポートになります。
本校の特別支援学級でも、日々の学習や生活の中で、ユニバーサルデザインを意識した教材づくりを行っています。例えば、ワークシートや掲示物を作成する際には、見やすいUDフォント(ユニバーサルデザイン書体)を使用したり、授業の流れや活動予定を黒板に書いて可視化したりしています。こうした工夫は、読むことに困難さのある子どもだけでなく、すべての子どもにとっても「わかりやすさ」につながっています。
さらに、おおぐろの森中学校は校内の環境整備にも配慮をしています。多機能トイレやウォシュレットには点字表記があり、洗面台の高さにも車いすの使用を想定した設計が施されています。階段には手すりが設けられたり、昇降口には段差がなくスムーズに学校に入れたりできる設計になっています。
また、2階・3階には誰でも使える冷水器も設置。エレベーターも設置され、必要な支援がどの子にも届くよう工夫されています。
「ルビ振りの日」という機会は、特別支援教育やユニバーサルデザインの大切さを見つめ直す良いきっかけになります。特別支援教育の基本は、一人ひとりの困りごとや得意なことに応じて、学び方そのものを工夫することにあります。ルビはその中でもすぐに取り入れやすく、効果的な支援の一つです。
国においても、「共生社会」の実現に向けて特別支援教育の推進が図られています。文部科学省では、障害のある子もない子も互いに認め合い、学び合う教育の実現を目指しており、ICTの活用や合理的配慮とともに、「読みやすくする工夫」も大切な支援とされています。
これからも本校では、すべての子どもたちが安心して学べる環境づくりを進めていきます。そして、一人ひとりの「わかりたい」「できるようになりたい」という気持ちに応える教育を実践してまいります。
本校の図書室にも、たくさんのユニバーサルデザインや特別支援教育に関する本があるので読んでみてください。
2年生の家庭科 きゅうりの切り方テスト
今、2年生は食生活について、自分の食習慣を振り返り、5大栄養素や6つの基礎食品群を学び、これから少しずつ調理の技能を身につけていこうと、学習を進めています。
そこで、まずは切り方を学ぶということで、きゅうり半分を使っていろいろな切り方に挑戦しました。
まずはキュウリを水洗いします。へたの部分を切って、あく抜きをします。切り取った部分をもとのきゅうりと合わせ、丸々とこすりわせると白い泡が出てきます。きゅうりのあくです。これは洗い流して。さあ、切り方に挑戦。
ホワイトボードにも書いてありますが、まずは教師の切り方を参考に。輪切りは小学校での復習です。できるだけ薄く切ります。
次は、一人分はきゅうり半分。その3分の1くらいを縦に切って、丸太のように上を断面に置きます。縦に薄く短冊に
切っていきます。長方形になったきゅうりを縦長に薄く千切りしていきます。薄く長い2本だけ残します。(提出)
千切りが細く長くできたら、それを横にして細かく切ると、みじん切りです。
みじん切り少々残します。(提出)残っていた3分の2のきゅうりを包丁をはカタカナのハの字にして、斜め切り。
これも、できるだけ薄く長く切ります。(2枚提出)
最後は斜め切りした、切り口を天井に向けて、斜めに切っていきます。これを繰り返すと乱切りができます。
一人ひとり、手洗いした後自分の皿や包丁、まな板など洗浄して始めました。
キュウリを抑える手は、猫さんの手になっているかどうか、確認です。
集中して取り組んでいますね!
皆切るのが上手です!とても丁寧に進めていました。
さあ、平皿にのせて、提出です。出席番号順に5種類2枚ずつ並べてもらいました。
輪切りと斜め切りの差が出ていないと、斜め切りは「もう少し頑張ろう」というところでしょうか。
みじん切りが荒くならないためにも、千切りが薄く細く切れることが大事ですね。
最後は、乾燥ワカメをお湯で戻し、残ったきゅうりを食べやすい大きさに切っておきます。
三杯酢を一人ひとり作ります。
だし小さじ1、砂糖小さじ1(大盛で)、しょうゆ小さじ1、酢小さじ3の1:1:1:3。
砂糖が少し多めが良いので、自分で味見しながら、砂糖をよく溶かしてきゅうりと水切りしたワカメを盛りつけて、
三杯酢をかけて、「いただきま~す!」
味を直すのは各自、自分です。甘いのが好きな人とそうでない人と、好みはそれぞれですね!
最後は片付け。
どの班もみんな、流しの中まできれいに、台ふきで吹き上げることができました‼
7月には、わくわくミルク教室(日本乳業協会様による)も予定しています。
これを機会に、食生活にどんどん興味をもってほしいと思います。
今回、どのクラスも本当に意欲的に取り組んでくれました。また、「「安全第一」に進めることができ、
とてもありがたかったです。(ケガがなくて、ほんとよかったです。)
さらにできたら、できたらでよいのですが、おうちのお手伝いができればさらに嬉しいです。
2年生のおうちでの家庭科の実践を、期待しています。
自分と他者の大切な命を守る
本日の5校時に交通事故遺族者による犯罪被害者等支援の講演会を行い、安藤正恵様からお話をいただきました。
ご自身の経験を基にした、貴重なお話をたくさんお聞きすることができました。
安藤さんは、平成31年4月、木更津市江川の県道交差点で、当時小学3年生の娘さんを交通事故で亡くされました。登校途中、横断歩道を青信号で渡っていたところ、信号無視をしてきた車両にはねられ、心肺停止の状態で病院に搬送され救急処置を受けましたが、数時間後に亡くなられたとのことです。講演では、遺族の痛切な思いや犯罪被害者等支援の重要性などを伝えていただきました。生徒たちは、自分たちにも起こりうる可能性があることを理解し、他人事ではなく、自分事として重く受けとめ、涙を流している生徒もいました。
何かしてあげられることはなかったのかという後悔の念、悲しみ、無力感、怒りなどの感情を、時折声を震わせながらお話する様子から感じられました。
最近でも、大阪市で小学2・3年の男女7人が、車にはねられ重軽傷を負うという事故や、埼玉県三郷市で小学生の列に車が突っ込み、男子児童4人がけがをしたというニュースがありました。
誰もが、被害者にも加害者にもなる可能性があることを頭に入れながら生活しなければならないと感じました。これまで以上に気をつけながら、自転車や自動車の運転をしていかないといけないなと痛感しました。
被害者にも加害者にもならないようにする。そのためには、余裕をもって行動することが大切だと考えます。
みなさんは、朝、余裕を持って登校できていますか?登校中は、スマホを操作したり、イヤフォンをつけながら自転車に乗ったり、歩いたりしていないですか?周りをよく見ることができていますか?
被害者になっても加害者になっても、家族や親族に辛い思いをさせてしまいます。
安心・安全に生活していくために、普段から私たちができること、意識することを考えてみてください。
普段から心がけていれば、自分も守れますし、他者を守ることにも繋がると思います。
講演を聞いて、感じたことや、自分の考え等を作文にして振り返りを行いました。
以下は、生徒の言葉です。
・心の中で一生残り続け、何ともぬぐいきれない気持ちになってしまい、精神的な被害を受けるということがわかりました。
・被害者の話を聞いて、事故はいつ、どこで起きてもおかしくないことを改めて感じた。
・命というのは、物などとは違って、二度と戻ってこない。
・動物たちの命をいただく前に、動物たちへの感謝などを忘れないようにしたいと思った。
・大きな事故は、自分とかけ離れた別世界のものではなく、また、小さな事故に対しても軽視してはいけない。
事故等の犯罪被害について、家族を失った当事者による講演をとおして、被害者のおかれた状況や心情、及び人の心の痛みを感じ、寄り添うことの大切さを学びました。この貴重なお話をこれからの生活に活かしていきたいと思います。
給食試食会 ご参加ありがとうございました!
5月27日(火)、36名の方に来校いただき、給食試食会を実施しました。
本日のメニューは、
ご飯 牛乳 豚肉と蓮根の黒酢炒め 手作り肉団子汁 ヨーグルト
試食会に先立って、宮本栄養教諭よりメニューの説明をさせていただきました。
その後、配膳からお手伝いいただきました。
みんなで「いただきます」をし、試食会スタートです。
参加していただいた保護者の方からの感想を紹介します。
・とても美味しかったです。ボリュームやバランスも中学生にちょうどよいと思いました。
・食材をたくさん使っており、家だけでは足りていないと思うのでありがたいです。
・子どもたちが給食の時間を楽しめる様子が分かってよかったです。
・子どもたちが毎日こんなにおいしい給食を食べてるんだ~、と知ることができてよかったです。給食の雰囲気も懐かしくて、いい体験でした!
・子どもが普段バランスの取れた食事を食べさせていただけていることを実感し、ありがたく思いました。
・とてもボリュームがあり、食べ盛りの子どもにとってありがたく思いました。肉団子がとても美味しかったです。だしやルーなども手が込んでいて驚きました。ありがとうございました。
・子どもとの会話がはずむ機会になりそうです。給食でこういう内容のものを食べるなら、家ではどういうものにしたら良さそうかとか、アイディアが広がりました!
・他の保護やの方と交流する機会にもなり、話がはずみました。学校の様子も分かって助かりました。
・中学生、うらやましい。宮本先生や調理担当の方々の日々のお仕事に感謝いたします。食育学習などの機会もあったりと、子ども達に対しての取り組みもありがたく、家でその話を聞くことも楽しみの一つです。ごちそうさまでした。
その他にも、多くの励ましの言葉や「レシピを知りたい!」といった声をいただきました。
普段お子様が食べている給食を体感していただき、本校の食育が少しでも皆様に伝わればありがたいです。
これからも、安心、安全で美味しい給食を提供できるように努力してまいります。
1年生の車いす体験
みなさん、「インクルーシブ社会」という言葉を知っていますか?インクルーシブ社会とは、性別や人種、民族、国籍、障がいの有無、年齢などの多様性を排除することなく、支え合いながらともに生活できる社会のことをいいます。世界中で、すべての人が公正に暮らすことのできる社会の実現に向け、様々な取り組みが行われています。
おおぐろの森中学校でも、インクルーシブ社会の実現に向け、「車いす体験」を行いました。講師として、江戸川学園おおたかの森専門学校の塩見先生や流山市社会福祉協議会の方々をお招きし、車いすの操作方法について学んだり、車いすに実際に乗ったりしました。
体験では、様々なシチュエーションを想定した車いすの操作方法について学びました。例えば、「右半身が麻痺してしまい、右手と右足が動かせなくなってしまった場合、どのように操作をすればよいのか?」。正解は、左手でタイヤを操作し、左足で地面を蹴り、移動をします。生徒は「どうすれば上手く進めるのか?」「方向転換はどのように行うのか?」を考えながら車いすを操作していました。

日本には、車いす利用者が約200万人いらっしゃいます。車いすを使っての生活には、様々な大変さがあります。特に、車いすの方にとって外出時の段差が悩みの種になっています。例えば、写真のような段差があったとします。
畳の厚さは6cmほどしかありません。しかし、6cmの段差は、車いすに乗っている方が、一人で越えるには難しい高さです。一般的に、車いすで許容できる段差は、「2cm」といわれています。車いすを使っていない人は、多少の段差なら、段差と思わず、無意識に越えていると思います。しかし、車いすの方は、日常生活のいたるところにある段差に苦労しているのです。
この体験を通し、車いすを利用している方々の気持ちを知ることができました。もしも、車いすで困っている人がいたとき、「手伝います!」と自ら声をかけ、行動できる自律した生徒になってほしいと思います。
つながり!流山へ到着!! Grow School vol.34
最初の予定よりも1時間早く無事到着しました!!
「つながり~心と心+伝承の蓄積=∞の力~」
のテーマのもと活動し、心と心のつながりを実感できた3日間
バスから降りてきたときに、たくましい表情のように見えました。
ぜひ、家庭でも3日間のことを話を聞いてみてください。
水曜日はゆっくり休んで、木曜日からまた一緒に活動しましょう!!
三芳PA出発!いよいよフィナーレ! Grow School vol.33
ただいま三芳パーキングエリアの休憩を終え、出発しました。計画より30分早い、5時15分到着予定です。バスの中で帰りの会を行なっています。
甘楽SA 元気いっぱい! Grow School vol.32
甘楽サービスエリアを出発しました。時間もぴったり、予定通りです。元気いっぱい、バスレクを楽しんでいます。全クラスのバス内の様子をどうぞ
東部湯の丸SA &ビンゴ Grow School vol.31
東部湯の丸サービスエリアで休憩をとり、ただいま、バス内ビンゴ実施中です。なんと上位3名には給食おかわり券が贈呈されるとのことです。
お土産追い込み Grow School vol.30
昼食後のお土産コーナーの様子です。1日目のホテルのお土産コーナーに引き継ぎ、店内いっぱい混雑しています。
3日目昼食 Grow School vol.29
善光寺周辺の散策を終え、信州フルーツランドへ到着し、みんなで昼食を食べました。
お土産も買い、12:50に出発しました。
3か所のサービスエリア、パーキングエリアで休憩をはさみながら、流山へ帰ってきます。
名残惜しいですが、終わりまでもう少しです。
善光寺 班別行動開始! Grow School vol.28
善光寺周辺の班別行動がスタートしています。
天気もよく、楽しそうですね!
3日目スタートです! Grow School vol.27
各家庭での民泊を終え、今日は離村式からスタートです。
空気澄み渡る快晴、雪が残る妙高山、黒姫山、民泊させていただいた方々から心をもらった生徒達、
たった一日、されど一日・・・。
温かく迎えてくださった御家庭とのお別れは、つらいものがあります。
「また、会いに来るよ!」「いつでも待ってるよ!」そんな声が、いたるところから聞こえてきます。
名残惜しい、会でした。
お別れをした生徒たちは、これから善光寺へ向かい、班別行動を行います。
民泊先で体験しています!⑦ Grow School vol.26
民泊体験で様々な出会いと体験を行っています!
薪割り上手にできているかな?
なんだかいつもより凜々しい顔が並んでいます!
どの家庭でも温かく迎えてくださっています。
生徒たちは各家庭にて、これから夕食、就寝へ!
民泊先で体験しています!⑥ Grow School vol.25
先生方がいろんな民泊先に行って体験のようすをぞくぞくと撮ってくれています!
〇とうもろこしの作業や、ねぎぼうずをカットするなど、畑でお仕事してました。
〇畑の土の移動など、畑作業をしていました。そのあと、薪割りをやったようです。
〇午前中は障子の張り替えをし、行ったときにはたけのこの皮むきをしていました。
〇山菜採りに行き、その山菜(ヨモギ)で草団子を作っていました。
〇ルバーブを切ってきて、ジャムをつくりにいくところです。
〇ペンションでの体験の様子です。Tシャツを作成するグループ、山菜を収穫してお昼ご飯を作るグループ、ピザを焼いて食べるグループ、木の実を使ってかざりを作るグループ、キッチンカーでハンバーガーを作るグループと様々な体験を楽しんでおります。
〇田植えの体験をしています。苗を田植え機に積み込む作業です。簡単そうな作業に見えますがこれが意外と難しく、丁寧な扱いが求められています。農作業の難しさに触れ、とてもいい学びになっています。
民泊先で体験しています!⑤ Grow School vol.24
各民泊先では、人の心の温かさに触れ、様々な体験をしています。
歴史を感じる建物もあるようですね。
とても貴重な機会です!
みなさん、素敵な笑顔です!
立派なかやぶき屋根ですね。
いろりに触れる機会はなかなかなさそうです。
山でとれる様々なものを使ってリース作りです。
キャンプでピザ窯体験!いいですねぇ
いろりを囲んでいただく食事は、なんとも風情を感じます。
文政6年!?なんと約200年前です!!
家族そろってみんないい笑顔です!
民泊先で体験しています!④ Grow School vol.23
〇キッチンもお風呂も家も遊具も食事も全て手作り。
シュタイナー教育を実践されている幼稚園のご家庭にお世話になっています。
午前中は畑仕事をして、泥だらけに。一生懸命作業に取り組みました。夜は星空の下、自分でお風呂を沸かして五右衛門風呂に入ります。
〇どんな生物がいるのか調査を行っています。この後、専門家の先生にご指導頂きながら解剖を行います。
〇りんご農園
〇畑作業を頑張っています☆
民泊先で体験しています!③ Grow School vol.22
たくさんの野菜やリンゴを育てています。
受け入れ先が海外の方だったので、英会話も上達して帰ってくるかもしれません!!
〇家庭の食事をいただきました
ふきを取ってきて下ごしらえをしていました
民泊先ごとに様々な体験をしていますね!! これからも写真を撮れ次第どんどんUPしていきます!
民泊先で体験しています!② Grow School vol.21
民泊体験の様子②をお届けします!
こちらでは障子を丁寧に張り替えているようです。
民泊先で体験しています!① Grow School vol.20
お世話になる民泊先に到着し、体験がスタートしています!!
〇草取り作業中
〇宿泊先で
〇山散策&山菜採り中
〇花を植えや畑作業中
〇堆肥や肥料を混ぜての畝作り。この後ミニトマトやピーマンの苗を植えます。
山暮らし体験では、冬に向けての薪割りをしています。
民泊対面式 Grow School vol.19
おいしい朝食も食べ終わり、いよいよ2日目の民泊体験のスタートです!
まず、お世話になる民泊の方々との対面式です!!46か所に分かれて体験が始まります!!
対面式には、お世話になっている信濃町の町長 鈴木文雄様にもお越しいただき、生徒の前でお話いただきました。町をあげて、受け入れてくださりありがとうございます!!
学校では体験できない貴重な体験をして、充実した2日目になることを願います☆
2日目スタート Grow School vol.18
さぁ、グロースクール2日目がスタートしました。
朝食の様子です。