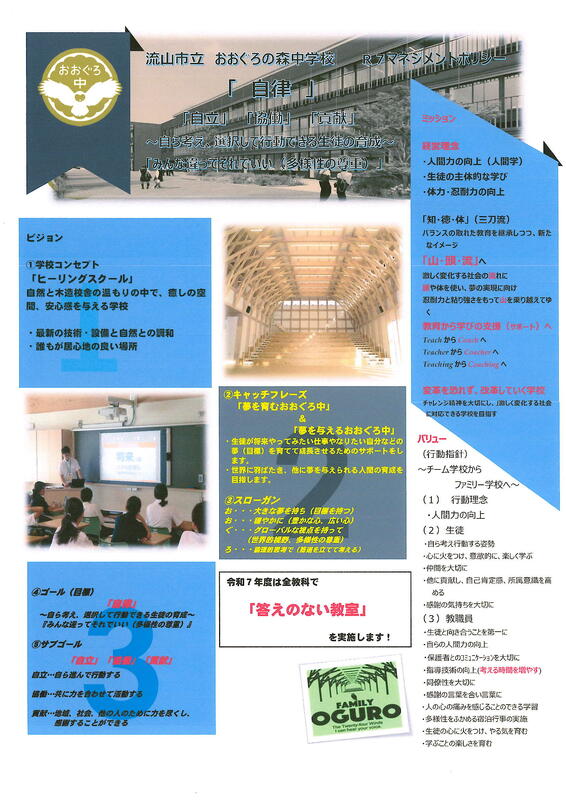学校の様子
2日目夕食 修学旅行vol.19
今日の夕食も部屋食です。
すきやきおいしそうですね!
班別研修の出来事を語らいながら食べるごはんは、
旅の良い思い出になりますね!
宿に到着! 修学旅行vol.18
各班、班別研修を終え、元気に帰ってきました!
体調不良者もおらず、充実した顔が並んでいます
この後は18時から夕食の予定です。
今日のメニューは何でしょう??
京都班別研修Part4 修学旅行vol.17
京都班別研修 金閣寺&京都タワー編です!
男子は着崩れと格闘している生徒が多いようです
この後生徒たちは17時を目指して宿に戻る予定です。
あと少しです!楽しんで!
京都班別研修Part3 修学旅行vol.16
班別研修も後半戦です!
お土産を買う班や、お面をつけて回る班もいます。
京都班別研修Part2 修学旅行vol.15
京都班別研修の様子をお届けします!
みんな楽しそうですね。
そろそろお昼ご飯です!