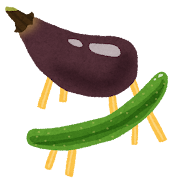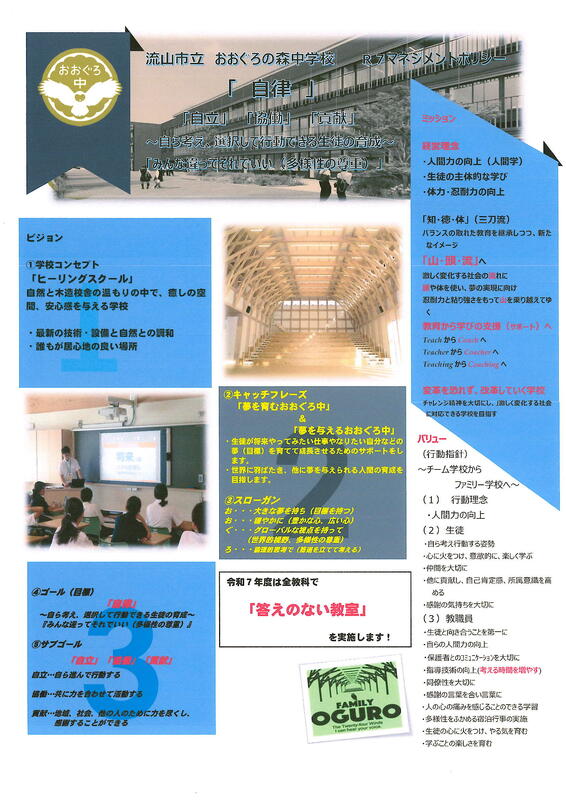学校の様子
次の世代へと
7月20日(土)に野田市総合公園体育館にて、総合体育大会卓球競技の部団体戦が行われました。
結果は、
男子団体戦 準優勝
女子団体戦 第3位
男子
予選リーグ 1位通過
対 野田北部 3-1 勝利
対 関宿 3-0 勝利
対 川間 3-0 勝利
決勝トーナメント
対 野田二 3-2 勝利
対 八木 3-1 勝利
対 おおたかの森 0-3 惜敗
女子
予選リーグ 1位通過
対 岩名 3-0 勝利
対 二川 3-0 勝利
決勝トーナメント
対 流山東部 3-2 勝利
対 野田南部 2-3 惜敗
悔しくも、県大会への切符をつかみとることができませんでした。
1点、1球に思いをのせて、懸命に戦う選手の姿がありました。
ある選手が、こう言いました。
「卓球部の一員で本当によかった。周りのみんながいたからこそ、2年半楽しく活動できた。辛いときも嬉しいときも、共に過ごせた仲間のおかげです。いろいろな指導を受けて、たくさんの経験をして、将来のためになったと思います。県大会へ行くことができなかったけど、最後の最後に、とても熱い戦いができてよかったです。ありがとうございました。」
選手それぞれに、さまざまな思いがあります。これから先、3年生はそれぞれが目指す道に向けて、部活動での経験を糧に、歩んでいって欲しいと思います。
また、保護者の皆様、お力添えいただいた関係者の皆様に、感謝申し上げます。ありがとうございました。
さて、世代交代し、先輩たちの思いを受け継ぎ、新たに目標を定めてスタートした新チーム。
8月1日(木)に、初めての大会(柏オープン大会)に参加しました。
結果は、
男子 下位トーナメント 優勝
女子 決勝トーナメント 進出
予選リーグ 3位通過(下位トーナメントへ)
対 青柳 1-3 惜敗
対 若葉 1-3 惜敗
対 中原 3-0 勝利
下位トーナメント 優勝
対 豊四季 勝利
対 松戸二 勝利
対 松戸一 勝利
対 大津ヶ丘 勝利
女子
予選リーグ 2位通過(決勝トーナメントへ)
対 青柳 1-3 惜敗
対 富勢 3-1 勝利
決勝トーナメント
対 常盤平 惜敗
まだ、始まったばかりのチーム。これから先が楽しみです。先輩たちみたいになりたい!先輩たちを超えたい!それが今の原動力のように感じます。8月末に大会があります。そこに向けて頑張っていきましょう。
オリンピックも盛り上がっています。日本代表として活躍する選手たちの姿を見て、多くのことを感じ取り、自分に生かせるといいですね。
夏休み前半ももう少しで終わりです!
みなさん、
いかがお過ごしでしょうか。
夏休み前半も明日で終わり、
部活動もお盆休みに入ります。
旅行をしたり、
帰省したり、
自分の趣味に時間を使ったり・・・
せっかくの夏休みなので、
自分のために時間を使ってください!
では、そもそもお盆とは何なんでしょうか。
よく、ご先祖様が戻ってくるという話を聞いたことがある人もいると
思いますが、
ご先祖様をご自宅にお迎えしてご供養する行事がお盆です。
地域によって、若干の違いはあるそうですが、
8月13日~8月16日をお盆期間とする地域が多いようです。
では、実際にお盆は何をするのでしょうか?
地域によってやることが違うようですが、
お墓参りをしたり、
親戚一同集まって会食をしたり、
お盆提灯を飾ったり、
キュウリやナスで作った牛馬を飾ったり・・・
色々とあります。
また、京都での大文字焼きをはじめ、
地域行事が行われることもあります。
今では、昔からの行事を行うことも
少なくはなっているかもしれませんが、
親戚が集まることも多いのではないでしょうか。
色々な人と関わることは、
色々な発見にもつながります。
ぜひ、充実した休みにして下さい!
そして、夏休み後半、
また元気にお会いできるのを楽しみにしております。
本日で前半の部活が終わりの部活もあります。
一部ですが、
部活動の様子をお届けし、
終わりにします!
バドミントン部は、
新体制となり2週間!
1年生と2年生で一緒に頑張っています!
女子バスケットボール部では、
3年生の生徒が参加し、
お別れ試合を行っていました。
熱い!アートの卵展 表彰式
今日も暑い!!
夏らしい空ですね。
暑さに負けない「熱い夏」・・・そう!アートの卵展が8月1日~25日まで開催されております。
文化部も熱く盛り上がっております!!
中でも、本日はイベント盛りだくさんの一日でした。
まず、オープニングを飾るのは西初石中学校の和太鼓演奏です。


3学年が揃って演奏するのは今日が最後ということもあり、演奏にも熱が入ります。
沢山のお客様も来てくださり、熱視線が注がれました。
午後には、八木北小学校の渡辺教頭先生をお招きし、作品講評会が行われました。


取材に基づいた描き込みや、実際のモデルを見ながら制作した点等、評価してくださいました。
受賞した作品には、どれも熱があります。
作品のタイトルに込められた思いや、その時の空気感が受賞者から語られ、とても充実した時間となりました。
そして本日のメインイベント!!
いよいよ表彰式です。
78作品の中から本校の井上さんが「奨励賞」を受賞しました!!
おめでとうございます!!!素晴らしい!!熱いぞ!!


今回のアートの卵展開催まで、流山市内の中学生たちが土曜日に集まり、デッサン会を行ってきました。
このように文化部が市内で交流できることは、お互いに良い刺激をもらうことができ、大変有意義なことです。
切磋琢磨しながら技術を高め合い、本日このように花開いたことを大変嬉しく思います。
そして、この開催には森の美術館のご協力あってこそです。
未来ある中学生のために・・・と熱い思いを語ってくださる森館長はじめ、スタッフの皆様、いつも有難うございます。
まだまだ続く熱い夏。今日は沢山元気をもらうことができました。
みんなが行きたくなる学校って、どんな学校?
暑い日が続いていますが、いかがお過ごしですか?
夏のオリンピックも毎日白熱した戦いが繰り広げられていますね。応援で寝不足です…なんて人もいるのではないでしょうか。
さて、そんなオリンピックにも負けない熱い討論会、
「東葛飾地区中学生・高校生との交流会」が昨日、流山北高等学校で行われました。
交流会には、おおぐろの森中学校を代表して
2年2組生徒会の岡村さん 学級委員の酒巻さん 6組学級委員の岩﨑さんが参加しました。
この交流会では、タイトルにもあるように
「みんなが行きたくなる学校ってどんな学校?」
「みんなが幸福で充実した人生を送るために何が必要?」
という2つの討議テーマをもとに、中学生、高校生、大学生がそれぞれの意見を発表しました。
みなさんなら、どう考えますか?
グループ討議では活発な意見交換がおこなわれていました。
「みんなが行きたくなる学校ってどんな学校?」
・みんなの意見が通りやすい学校
・意見に対する第一声が「そうだね!」と肯定してくれる
・長所を生かしてくれる、見つけてくれる学校
・生徒を否定しない
・自分を認めてくれる
・学び喜びを共有できる学校
・いじめがない学校
「みんなが幸福で充実した人生を送るために何が必要?」
・人と人の関わり
・お互いに理解する→良い所をくみとる
・自分を大切にする→敏感になりすぎない
・想像力を増やしていく
・色々なことを好きになる→充実感が得られる
・相手がどんなことを言ってほしいかを考える→人によって違う
・部活(環境)→ 一体感を持つ ポジティブになる
高校生や大学生、千葉県教育委員会の先生方も参加している中でしたが、代表した3名全員が堂々と自分の意見を発表していて大変立派でした。
夏休みも残り一か月ですね。
「みんなが行きたくなる学校ってどんな学校?」
「みんなが幸福で充実した人生を送るために何が必要?」
ぜひみなさんも夏休みの間に、考えてみてください。
2学期元気な姿で会えることを楽しみにしています。
けやきこぶし菜園事件簿
例年にはない猛暑が続く毎日に息切れしてしまいそうですね。
今年の7月の平均気温は、速報値で昨年を上回り過去最高の記録を更新したそうです。
しかし…今日から8月!夏本番です!
今年は梅雨や猛暑、豪雨の影響で夏野菜が、巨大化し今が旬となっています。
ぜひ栄養や水分をいっぱい含んだキュウリやなす、ピーマン、トマトなどを食べて
暑さに負けない体を作ってください!
そして、おおぐろ中でも、けやきこぶし学級で春頃から、夏野菜を育てています。
その夏野菜が今まさに大きく、たくさん実っています。
しかし!!!
実は、7月中旬あたりから大事件が起きているのです!
虫の仕業とはとは思えないくらい大きなかじった跡。
前日に立派に実っていた野菜が次の朝にはこんな姿に…
犯人はいったい何者なのか!?
夜に何者かが忍び込んでいるにちがいありません。
ちなみに私が暗くなってから帰ろうと、体育館脇を通った時、すぐ脇の茂みからガサゴソ、結構大きな生き物の音が聞こえてきました。私は怖くて逃げましたが、おおぐろ中、おおぐろの森にはきっと何かがいます。その何者かが、お腹を空かせてけやきこぶし菜園にやってきたのだと思います。
正体が気になりますが…
今のところ不明です…
森の学校なので、しょうがないなと思っています。
今は、栽培した野菜を守るため、小林先生がネットをかけたり囲いを作ったり、用務員の石井さんが植木の剪定をしてくださっています。
皆さんも体育館脇から校舎に向かう時に、見てみてください。今は、スイカが日に日に立派になっています!
そして、8月も厳しい暑さのようなので体調をくずさなぬよう、日々の体調&栄養管理をしっかりして過ごしてください。