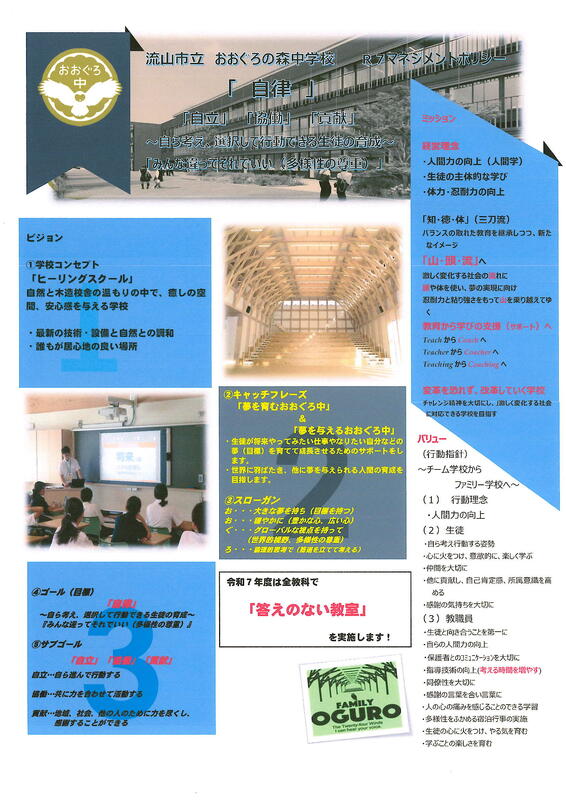学校の様子
夏の訪れ ~まもなく夏休み~
今日は台風の影響で、晴れたり曇ったり雨が降ったりと忙しい空模様でした。
さて、昨日、「カブトムシ」がベランダに訪れ、みんな大騒ぎ!!早速救出し、観察しました。
「ちょっと小さいね。」
「体に毛が生えてる!」
「意外と目が小さくてかわいいね。」
「触ったことないけど触ってみようかな。」
「飛ばないかな?」
カブトムシに詳しい子が、「あまり触りすぎてもよくないよ。ここを持つといいよ!」などアドバイス。
腕にのせてあげると、「くすぐったい~」「チクチクする!」
中には虫が苦手な子も、恐る恐る触ってみると、、「思ったよりも平気かも?」
「教室で飼いましょうよ!」という声が上がり、夏休みまで残り4日間、我が教室で飼育することにしました。
今日、昆虫ゼリーをもってきてくれた生徒がいて、飼育ケースにいれてみると、、、
相当お腹がすいていたんでしょうか、、顔面から突っ込む勢いでがっつり食べていました。
カブトムシは、「佐々木ジョニー」と命名しました。短い間、よろしくお願いします!
天気だけでなく、カブトムシのように、その季節を代表する生き物に出会うと、夏の訪れを感じますね。
食べ物でも季節を感じることができます。夏といえば、夏野菜ですね!
おおぐろの森中では、明日、夏野菜カレーが出ます。
今日は、昨日3年生とけやき学級、こぶし学級の生徒がむいてくれた枝豆が出ました。
枝豆の味がしっかりとしていてとても美味しかったです。中には枝豆が大好きな人もいて、
「毎日食べたい!!」「もっと食べたい!!」
と言って喜んで食べていました。味覚で季節を味わうことも大切ですね。
中村農園さん、いつもありがとうございます。ごちそうさまでした!
夏は暑いので、冷たいものも食べたくなりますね!家庭科の授業を覗いてみると、、かき氷を作っていました。
「冷たくておいしい」
「氷がシャリシャリしてた」
「色がきれい」
「全部混ぜてもおいしい」
「ブルーハワイが一番!」
「青と黄色で緑にした」
など楽しそうな声がたくさん聞こえてきました。
この授業では、色を混ぜ合わせるときれいな色になる
→視覚的にも楽しめるように工夫することが大切であることに気付く目的があるそうです。
ただし、混ぜすぎると、だんだん怪しい色に、、、美術の色塗りと同じですね。
他教科の学習内容もこういうところで繋がっていることを実感できた瞬間でした。


夏休み目前になると、長期休業前の学年集会がつきものです。
6時間目、体育館では2年生が今学期の振り返りを行っていました。
各委員会の学年代表がスライドをつくり、分かりやすくなるように工夫していました。
発表を聞いたあとは、課題に対して学年全体でさらに成長できることはないか、グループごとに話し合いました。
「呼びかけの仕方を工夫しようよ」「合唱曲を練習以外で流すのはどうかな」
など活発に意見を出し合い、真剣に考えている様子が見られました。
来学期、学年内でどのような成長が見られるのか、楽しみにしています!
夏休みまであと4日!!大相撲名古屋場所は残り12日!!どちらも楽しみましょう!!
枝豆収穫体験
毎年、本校では3年生とけやき学級こぶし学級が枝豆収穫体験を行っています。この体験学習は宮本栄養教諭が食育の一環として企画し、中村農園様に御協力いただいて実施しています。
本日は荒天が予想されたため、畑での収穫は早朝、中村様に行なっていただき、多目的ホールでの開催となりました。
中村様から枝豆栽培のノウハウ、難しさや苦労話など、プレゼンテーション後に体験しました。この枝豆は明日、調理され給食で振る舞われます。美味しい枝豆が楽しみですね!
中村農園様、ありがとうございました。
熱い葛北大会が開催されました!
厳しい暑さが続く中、先週に引き続き、12日・13日も葛北大会が開催されました。
7月5・6日に、野球、サッカー、ソフトテニス、卓球、特設水泳が一足先に始まり、続く12日・13日に陸上、バドミントン、バレーも開催されました。
県大会への出場権がかかる大きな大会で、特に3年生にとっては、中学校でこれまで取り組んできた部活動の集大成となる最後の大会です。
多くの保護者の方々が見守る中、試合が行われ、選手たちは気迫のこもった全力プレーを見せてくれました。
そして、3年生はチームの中心として、堂々とした姿を見せてくれました。
〈 バドミントン 〉
〈 ソフトテニス 〉


〈 陸上 〉
〈 バレーボール 〉

思うようなプレーができなかったり、チームが劣勢の状態であったりするなどの苦しい場面でも、3年生が中心となり、声で、姿勢で、気持ちで、最後まで諦めずにやり遂げる姿を示してくれました。
チームのためだけでなく、おおぐろの森中学校の代表として、「おおぐろプライド」も存分に発揮してくれました。その姿はきっと、1・2年生の後輩たちの目にも焼き付いたことでしょう。3年生のほとんどは、この夏の総合体育大会で中学校の部活動に一度区切りをつけます。
1・2年生の後輩たちには、3年生の先輩たちから学んだことを、これからの活動に生かしてほしいと思います。
大会期間中、猛暑が続くにも関わらず、多くの保護者の皆様に足を運んでいただき、ありがとうございました。
バスケットボールなど、これから実施される競技もありますので、引き続き、おおぐろの森中学校への温かい応援・御声援をお願いいたします。
祝!女子バレーボール部 第3位!!
本日、葛北女子バレーボール大会の最終日が西武台千葉高校で開催されました。おおぐろの森中学校女子バレー部はこれまで4試合全て(準々決勝まで)、ストレート勝ち、ベスト4を決め、準決勝、強豪のルミナスと対戦しました。
サービスエースを決めるなど、善戦しましたが、惜しくも敗れてしまいました。しかし、堂々の3位!輝かしい成績です。胸を張ってください。
おめでとうございます!
おおぐろの森中学校女子バレー部は開校から創部4年目、ベスト4は初めてで快挙です。
全ての試合、明るく、コミュニケーションを図り、ミスをしてもチームメイトを助ける声掛けや励まし、そしてチームが盛り上がり、楽しさの中に真剣さがあり、終了後には私自身も涙が止まりませんでした。感動、感動の熱戦でした。
この経験は人生の中でかけがえのない宝物となることでしょう。バレーボール部の皆様、顧問の先生方、お疲れさまでした。そして、感動をありがとうございました。
応援に駆けつけていただきました、たくさんの保護者の皆様、卒業生・在校生の皆様、教職員の皆様に心から御礼申し上げます。
それでは、熱戦の様子をどうぞ!
葛北大会 結果 7月13日(日)
バレーボール
準々決勝 対 野田北部中 2-0 勝利
準決勝 対 ルミナス 0ー2 惜敗
第3位
バドミントン 個人戦
ベスト8
男子シングルス 坂本さん
男子ダブルス 江口さん・染谷さんペア
桑原さん・何さんペア
また、2年 坂本さんが、男子シングルスにおいて、全日本ジュニアバドミントン選手権大会千葉県予選会に出場することが決まりました。おめでとうございます!