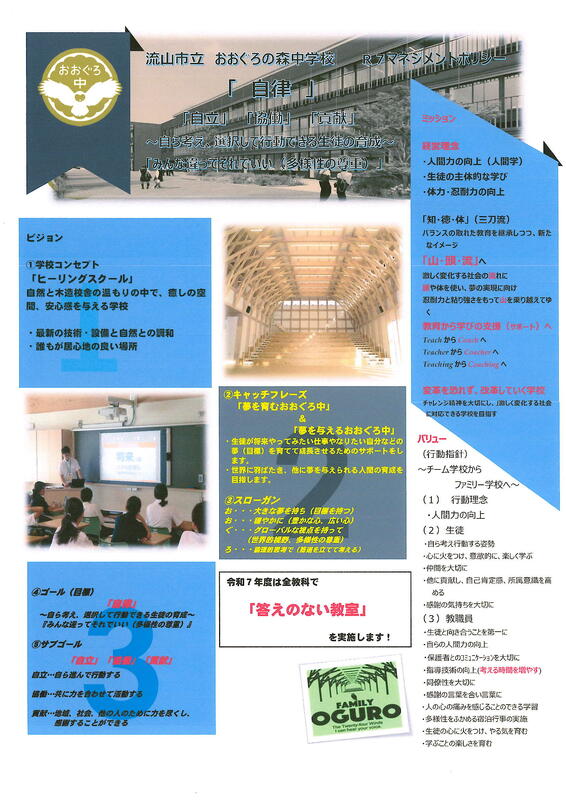学校の様子
民泊先で体験しています!⑤ Grow School vol.24
各民泊先では、人の心の温かさに触れ、様々な体験をしています。
歴史を感じる建物もあるようですね。
とても貴重な機会です!
みなさん、素敵な笑顔です!
立派なかやぶき屋根ですね。
いろりに触れる機会はなかなかなさそうです。
山でとれる様々なものを使ってリース作りです。
キャンプでピザ窯体験!いいですねぇ
いろりを囲んでいただく食事は、なんとも風情を感じます。
文政6年!?なんと約200年前です!!
家族そろってみんないい笑顔です!
民泊先で体験しています!④ Grow School vol.23
〇キッチンもお風呂も家も遊具も食事も全て手作り。
シュタイナー教育を実践されている幼稚園のご家庭にお世話になっています。
午前中は畑仕事をして、泥だらけに。一生懸命作業に取り組みました。夜は星空の下、自分でお風呂を沸かして五右衛門風呂に入ります。
〇どんな生物がいるのか調査を行っています。この後、専門家の先生にご指導頂きながら解剖を行います。
〇りんご農園
〇畑作業を頑張っています☆
民泊先で体験しています!③ Grow School vol.22
たくさんの野菜やリンゴを育てています。
受け入れ先が海外の方だったので、英会話も上達して帰ってくるかもしれません!!
〇家庭の食事をいただきました
ふきを取ってきて下ごしらえをしていました
民泊先ごとに様々な体験をしていますね!! これからも写真を撮れ次第どんどんUPしていきます!
民泊先で体験しています!② Grow School vol.21
民泊体験の様子②をお届けします!
こちらでは障子を丁寧に張り替えているようです。
民泊先で体験しています!① Grow School vol.20
お世話になる民泊先に到着し、体験がスタートしています!!
〇草取り作業中
〇宿泊先で
〇山散策&山菜採り中
〇花を植えや畑作業中
〇堆肥や肥料を混ぜての畝作り。この後ミニトマトやピーマンの苗を植えます。
山暮らし体験では、冬に向けての薪割りをしています。
民泊対面式 Grow School vol.19
おいしい朝食も食べ終わり、いよいよ2日目の民泊体験のスタートです!
まず、お世話になる民泊の方々との対面式です!!46か所に分かれて体験が始まります!!
対面式には、お世話になっている信濃町の町長 鈴木文雄様にもお越しいただき、生徒の前でお話いただきました。町をあげて、受け入れてくださりありがとうございます!!
学校では体験できない貴重な体験をして、充実した2日目になることを願います☆
2日目スタート Grow School vol.18
さぁ、グロースクール2日目がスタートしました。
朝食の様子です。
リーダー会 Grow School vol.17
学級で振り返りを行った後、リーダー会を実施しました。心と心、つながりを大切にした2年生、クラスごとに和気あいあいと今日一日を振り返りました。その後のリーダー会も素晴らしいディスカッションと発表でした。明るさと勢い、そして誠実さと優しさ、感動、感動のgrow school1日目でした。おやすみなさいzzz
学級会後の集合写真 Grow School vol.16
学級振り返りの終了後、クラスごとに集合写真を撮りました。
初日から充実した1日を送ることができました。集合写真の表情から、雰囲気の良さが伝わってきます。
明日も、民泊先での素敵な出会いと、たくさんの体験活動がみんなを待ってます!!
2年1組
2年2組
2年3組
2年4組
2年5組
2年6組
学級振り返り Grow School vol.15
クラスごとに成果と課題を発見・共有して、2・3日目につなげていくため、今日の振り返りを行いました。