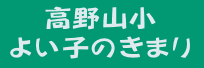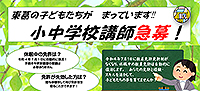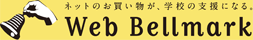校長室から
特別な教科 道徳と外国語科・外国語活動の話
校長 金子 博之
7月になりました。学校は学期末を迎え、先生たちは成績処理の作業に取りかかっているところです。
小学校は、2020年から新しい学習指導要領の内容に完全に切り替わることになっています。そのために今年度と来年度は移行期間と、位置づけられています。このことは、PTA総会の時にも、少しお話しさせていただきました。
保護者のみなさまもご承知の通り、学習指導要領というのは、わたしたち教師が、それぞれの学年で、それぞれの教科で何を教えなければならないのかということが書かれている大変重要はものです。
2020年からは教科書も全面的に変わることになります。
そんな中、今年度からは2020年の完全実施を待たずに、特別な教科 道徳と5、6年生を対象に外国語科、3、4年生を対象に外国語活動が始まりました。
今までの道徳と今年から始まった特別な教科 道徳は何が違うのか・・・子どもたちに人として大切な道徳性を養うというのは変わりません。というか変わりようがありません。今回の改訂では、更に自己の生き方について考えを深める学習を目ざし、道徳的な判断力や実践意欲を育てようという目標が加わり、新たに教科書が使われるようになりました。これまでは保護者のみなさまにお金を出していただいて、読み物資料を購入し使っていました。
通知表の中での扱いも変わります。これまでも学校生活全体の中で、子どもの道徳性が感じられた時などを観て、評価はしてきました。例えば、通知表の総合所見欄に・・・『男女の分け隔てなく進んで声をかけながら誰とでも仲良く遊ぶことができます。』等と書いてきました。
これに対し、特別な教科 道徳の評価は、総合所見欄とは別に枠を作り、45分の授業内での姿を書きます。45分間の授業の中でどのような活動があり、どのような考え方をしていたか等を文章で書きます。道徳性を評価するのに、AだBだCだというような良い、悪いといった評価の仕方は馴染みませんから,文章で書くことになります。
また、3、4年生の外国語活動や5、6年生の外国語科も総合所見欄とは別に、枠を作り、活動内容などを文章表現することになります。英語を一つのツールとして活用しながら、コミュニケーション能力の育成を目指すというのが小学校での目標ですので、英語活動とか英語科という教科名にはならなかったようです。
なお、国は移行期間中の3、4年生の外国語活動は、最低でも15時間程度の実施。5、6年生の外国語科は、最低でも50時間程度の実施としていますが、我孫子市では、体制を整え、2020年の完全実施と同様の3,4年生が35時間の実施。5、6年生が70時間の実施時間で今年度をスタートさせています。
もうすぐ子どもたちが楽しみにしている夏休みがやってきます。保護者のみなさま、地域のみなさまに見守られ、大きなケガや事故もなく無事に夏休みが迎えられそうです。心より感謝申し上げます。本当にありがとうございます。2学期もどうぞ、よろしくお願いいたします。
あいさつや素直な言葉であふれる高野山に
「ちっ、あっちいけよ。消えろよ。来るんじゃねえよ。」
虫の居所が悪いと、教師に対してもそんな言葉を使ってしまう児童がいます。
小学校の中・高学年から中学校時代は、子どもから大人へとのぼる階段のはざまにあります。勉強のこと、友だちのこと等々、悩みや葛藤など思春期の心の揺れは決して小さなものではありません。
したがって、どうしてもかん黙になったり、前述のように斜に構えたりするような態度になりがちです。大なり小なり、私たち大人の誰もが通ってきた道でもあります。
本校では4月、生徒指導部を中心に職員会議の中で、
① 「ひとりひとりの子どもを大切にし、個性の伸長と社会性を育てる。」
② 「基本的な生活習慣を育て、身につけさせる。」
・返事やあいさつがしっかりできる。
・きまりを守ることができる。
という、1年間の具体的なめあてを、高野山小学校の全教職員で共通理解し、取り組んでいるところです。具体的には生徒指導の基本のきである「傾聴と共感」という姿勢で子どもたちに接し、育てていこうとしています。冒頭の子どものように、暫時おへそがどこかにいってしまった子どもを、頭ごなしに怒鳴り散らしても良いことは一つもありません。まずはクールダウンをさせ、原因をじっくり探っていくことが大切となります。
高野山小学校では毎月、生徒指導部から「今月の生徒指導目標」が提示されます。4月の生徒指導の目標は、「進んで元気の良いあいさつをしよう」でした。
校内ではできていても、地域に出るとなかなか実践できない部分があります。理由は様々ですし、永遠の課題かもしれません。
学校では具体的な取り組みも始めています。児童会を中心とした「あいさつ運動」がそうですし、学校外の活動としては、地域の団体との連携も模索しているところです。ここ、高野山の地域で小学生、中学生、そして保護者・地域の皆様のあいさつがあふれたら、こんなに素敵なことはありません。
今月も、どうぞ、よろしくお願いいたします。
保護者・地域のみなさまに支えられています
校長 金子 博之
ここはスクールゾーンなのに、この時間に走っている車は本当に地域の人だろうか。
このこんもりとした林は、暖かくなるこれからの季節、痴漢とか出てきそうだな。
私は、毎朝7時30分から8時過ぎまで子どもたちの見守り活動をしながら学区を歩いています。日によってコースを変えながら、エルム歯科方面や桃山公園方面、我孫子中学校方面に天王台駅方面・・・と、高野山小学校の広い学区内を歩いていますが、そんな時上記のようなことを考えながら、まわりをきょろきょろしながら歩いています。
また、その時間は高野山小学校が保護者の方や地域の方々に支えられていることを強く感じる、そんな時間でもあります。
毎朝、通学路内の信号のない交差点で、見守り活動をされている方がいます。
「こども110番」の看板をつけているお宅の方が、家の前に出て、子どもたちの見守り活動までしてくださっている方がいます。
「子ども見守り隊」の赤い名札をつけ、犬の散歩をしながら子どもたちの登下校時間に見守り活動をしてくださっている方がいます。
入学したばかりの1年生の保護者の方の中には、学校までついてきてくださっている方々がいらっしゃいます。・・・
学区内をほんの少し歩くだけでも、このように実に多くの方々にお会いし、高野山小学校の子どもたちは地域の方々に愛され、そして守られているんだなあと強く感じています。本当にありがとうございます。
4月20日に行われた学習参観・懇談会の際には、授業参観後に保護者全体会(学校経営説明・職員紹介)とPTA総会を実施したのですが、330名を越える保護者のみなさまにお集まりいただきました。このことからも保護者のみなさまの本校の教育活動に対する高い関心度と共に、力強いご支援をいただいていることを改めて感じることができました。本当にうれしい限りです。ありがとうございます。
家庭訪問も始まりました。何か不安な点や疑問に感じる点などありましたら、お気軽に担任にご相談ください。
今月も、どうぞ、よろしくお願いいたします。
平成30年度のスタートです
校長 金子 博之
今年の桜は気が早く、始業式・入学式を待ってくれませんでした。ですが、学校には子どもたちの明るい笑い声が戻り、元気満開と言うところです。
かわいい新1年生85名を、11日の入学式で迎える予定です。希望と期待の中で平成30年度の高野山小学校の教育活動が元気よく始まりました。昨年度同様、変わらぬご理解とご支援をよろしくお願いいたします。
小学校は、2020年から新しい学習指導要領の内容に完全に切り替わることになっています。そのために今年度と来年度は移行期間として、位置づけられています。詳しい内容については、PTA総会の時に、お話しさせていただきますが、今年度も質の高い教育活動が行えるよう教職員一丸となって取り組んで参ります。本校の子どもたちの特徴は、知識・技能は、とてもよく身に付いているのに、それを活用する力に課題があることです。
算数の学習を例にして言うと、算数で学習した知識・技能、考え方などを活用する場面には、次のような場合があります。
・算数の問題を解決するのに活用する。
・新しいことを学ぶことに活用する。
・理科や社会など他の教科の学習に活用する。
・買い物や旅行、筋道立てて考え判断するなど日常生活の中で活用する。
かけ算九九が全部言えても、平行四辺形の面積の公式を覚えても、分数のわり算ができても、それを活用して、上のようなことができるようになっていなければ、本当に算数を学習したことにならないと考えているからです。
本校では、今年度「算数科」を校内研究の教科と位置づけ、研究を進めていきます。
「計算もできるし文章問題も解ける」「漢字の読み書きができ、作文も書け、文章の中身の理解や解釈もできる」・・・こんな子どもを増やすために、教職員一丸となって、丁寧できめ細かい指導を実施していきます。
今年度も昨年同様、保護者のみなさま、地域のみなさまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
便利なスマホですが
校長 金子 博之
高野山小学校のホームページには、毎日400から800のアクセスがあります。本当にありがたいことです。高野山小学校の現在の児童数は、647名で、家庭数は約500世帯ですから、単純に考えると毎日全てのご家庭に見ていただいているということになります。ですが、実際にはそんなことはないでしょうから、お一人で1日に何度もアクセスをしてくださっている方がいらっしゃるのかもしれません。ありがとうございます。パソコンだけでなくスマートフォンでも見ることができますので、まだ見たことがないという方は、一度ご覧になってください。トップページにその日の給食とトピックス等を載せています。(給食の献立は毎日更新、トピックスは不定期更新です)
そんなとても便利なスマートフォンですが、急速に子どもたちにも普及しています。正しい使い方を身につけ便利に利用して欲しいと願っています。
つい先日の新聞にも千葉県内の小学生女子児童が広島県に住む会ったこともない男性に、裸の画像を送ってしまったというニュースが載っていました。便利と背中合わせに危険が潜んでいるということです。
2月8日に5年生児童を対象に実施しました「情報モラル学習」でも、千葉県警察の担当の方から、小学生が携帯電話やスマートフォンとうまくつきあうためには、次の三つが大切という話がありました。
① 正しい知識を持つこと
② ルールやマナーを守ること
③ フィルタリングをかけること
うちの子に限ってではなく、まわりにいる大人の責任としてどうぞよろしくお願いいたします。
*インフルエンザの流行が衰えません。長期化の気配すらあります。学校でも油断することなくうがい・手洗いの励行をすすめています。ご家庭でもお願いいたします。
学力の基礎となるもの
校長 金子 博之
2月4日は「立春」です。暖かくなるのかと期待したいところですが、実際は今が一番冷え込む寒い時期です。学校でも「インフルエンザA,B」が猛威を振るっており、先月末は学年・学級閉鎖が続きました。発熱やインフルエンザでの欠席者は減ってきましたが、まだまだ油断禁物です。うがい・手洗い・換気に引き続き気をつけていきたいと思います。
さて、義務教育での学習が、その後の人生の基礎になると言われます。専門的なことは、高等学校や大学、更には実際に職業に就いてからとなるわけです。
中でも小学校での学習は、何をするにしても基礎・基本となる大切なことばかりですから、できるだけ広く学び、さまざまな知識や技能、考え方を身につけて欲しいと願っています。
更に子どもたちにとっては、社会そのものである学校生活自体が大切な意味を持っています。集団生活の中で学ぶことがたくさんあるからです。
★マナーやルールを守る
学校の決まりを守る、友だちとの約束を守る、自分から先にあいさつをする、思いやりと協力の心をもつ
★学習習慣を身につける
チャイム着席、忘れ物をしない、45分間席に座って学習に集中する
以上のことを身につけて、中学校という次のステップに進めれば、友人関係もうまくいくようになり、学習しやすく効果的に学ぶことができるようになります。
学力の基礎となるもの、それは、「規範意識」と「学習習慣」と言えそうです。
短い2月ですが、今月もどうぞよろしくお願いいたします。
自分を表現する力を身につけよう
金子 博之
新年、あけましておめでとうございます。
本年も昨年同様、どうぞよろしくお願いいたします。
平成もいよいよ今年と来年の途中までと言うことになりそうですが、みなさまにとりまして、本年が良い年となりますように。
本校では、確かな学力、豊かな心、健やかな体の育成を学校経営の柱として取り組んできました。確かな学力の育成のために具体的には基礎的・基本的な学習の時間の徹底であったり、言語活動や共に学び合う活動の推進、朝の読書・昼のドリルタイムの実施など、これらの時間から「自ら学び、思考し、表現できる力」を身につけ、確かな学力の向上につなげていきたいと考え、実践してきました。3学期はそうした学習の総まとめの時期でもあります。
「思考・判断」した力は、「表現」することによって初めて評価することが可能となります。ペーパーテストにその答えを書くという表現によって点数という評価がされるということもそうですし、45分の学習が終わった際に、学習の振り返りカードに感想を記入することによって、学習の理解度を評価するということもそうです。学習中に挙手をし、発表するという活動も自分の考えを表現するということの一つです。つまり、確かな学力の育成は表現力の育成と連動していて、言語活動の充実や言語力の育成を通して、「考え表現する力」を高めていくことが重要となってきます。
始業式では、児童に「自分を表現する力を身につけよう」という話をしました。みんなの前で発表することでもいいですし、ノートに自分の意見を書く、班で話し合う時に自分の考えをしっかり発言する等々、こうしたコミュニケーション力が表現力につながっていくと考えています。児童には、具体的に話しながら自分の考えを表現することの大切さを話しました。
3学期もよろしくお願いいたします。
あたたかい心の貯金
校長 金子 博之
高野山小学校の児童は、優しい子ばかりですが、今月は「ちくちく言葉」と「ふわふわ言葉」のお話をしたいと思います。
「ちくちく言葉」は、傷つく、悲しい、いやな言葉です。逆に「ふわふわ言葉」は、うれしい、優しい言葉です。「ふわふわ言葉」には、子どもたちが互いにつながり、楽しく安心して学校生活が送れるよう、相手のことを思いやる「言葉」を大切にして欲しいという願いが込められています。
人の心の中には生まれながらにして「あたたかい心の貯金」があると言われています。人からほめられたとき、話をしっかり聞いてもらったとき、「ありがとう」「いいよ」「いっしょにやろう」「がんばったね」「あなたのせいじゃないよ」と、思いやりが伝わる「ふわふわ言葉」を言われた時などにあたたかい心の貯金が貯まっていきます。あたたかい心の貯金とは、心の余裕です。心に余裕が生まれると、自然に家族や友だちに優しくなり、周りとのコミュニケーションが上手にとれるようになります。あたたかい心の貯金の残高が多ければ多いほど自分を大切だと思える自己肯定感、やる気、自信が増えてきます。
反対にあたたかい心の貯金が貯まっていない子は、周囲に対して心がささくれ立ち、反抗的な態度をとったり、家族や友だちとうまく接することが難しくなってしまうことがあります。また、自分はだめな子だと自己評価を低くし、自信が持てなくなり、周囲とのコミュニケーションがうまくとれなくなってしまう場合も出てきます。
子ども同士だけでなく、大人と子どもの関係も同じです。ほめれば貯金が増え、けなせば貯金が減っていきます。子ども一人一人の個性を受け止め、温かく見守り、プラスの声かけをしていくことは、私たち子どもの周りにいる大人の大切な役割の一つであり、常日頃から気をつけなければいけないと感じています。
「ふわふわ言葉」があふれる学校・家庭でありたいものです。
今月もどうぞ、よろしくお願いいたします。
いじめはゆるさない
10月27日の新聞で「千葉県内の小中高校・特別支援学校が2016年度に把握したいじめが3万件を超え、3年連続で全国最多となった」と報じていました。
いじめは決して許されるものではありません。本校でも年に数回児童に「いじめアンケート」を実施し、日々の観察と共にその把握につとめています。今年度は1回目のアンケートを6月に実施しました。その結果を見ますと「あなたは今、いじめられていますか」という問いに対し、20人の児童が「はい」と答えています。内訳は低学年が15人、中学年が3人、高学年が2人となっています。直ちに事実確認を行い、重大事案に該当するものはないことを確認しました。いじめにはあたらないものもありましたが、指導が必要な件では該当児童並びに保護者にも事実を伝え、家庭の理解と協力を求めています。
いじめはどこの学級でも起こりうると考えています。1学期の全校朝礼でも「けんかといじめの違い」について、児童に話しました。「けんか」は対等な関係であるのに対し、「いじめ」は上下の関係・強者と弱者の関係があるといった話をしました。児童は、いじめはいけないことだとわかっていますが、具体的にどういう行動がいじめにあたるのか、分かっていない場合があります。
高野山小学校では「いじめ防止基本方針」に則り、いじめや人権侵害などについて次のように取り組んでいきます。
① 児童に「いじめはしない、されたらすぐに先生やお父さんお母さんに相談する、している人を見たら先生やお父さんお母さんにすぐに知らせる。」
② 教師は、友だち同士の接し方についての指導や分かる授業づくりを行う。
③ 学校は、児童・保護者・地域からの情報に即対応する。
学校は、いじめられている児童を学校組織として全教職員で守ります。何かありましたら、少しでも気になることがありましたら、連絡をお願いいたします。
(高野山小学校いじめ防止基本方針は、ホームページで公開しています)
11月の全校朝礼では、「何でもそうだんポスト」が校長室前に設置されているので、どんな些細なことでも相談して欲しいと話しました。
今月も、どうぞよろしくお願いいたします。
いいことをする子がいっぱい
あいさつは、人と人のかかわりを潤いのあるものにします。今月の全校朝礼では、「すてきなあいさつ」ができるように校長先生と三つの約束をして欲しいと話しました。ただ話しても子どもたちはすぐに忘れてしまいますので、記憶に残るようにと、日頃からすてきなあいさつを実践している、6年生の児童3人にも協力してもらいながら話しました。
「6年1組の近藤さん、おはようございます。」「校長先生、おはようございます。」「近藤さんはにこにこ笑顔で校長先生にあいさつをしていました。」
すてきなあいさつの一つ目は・・・・・『にこにこ』です。
「6年3組の木村さん、おはようございます。」「校長先生、おはようございます。」「木村さんはにこにこ笑顔はもちろんですが、校長先生の目を見て、しっかりあいさつしていました。」
すてきなあいさつの二つ目は・・・・・『目を見て』です。
「次は6年2組の久保田さんにやってもらいましょう。」
「校長先生、おはようございます。」「久保田さん、おはようございます。」「久保田さんは、前の二人と違うところがありました。分かりますか?」
「そうです、校長先生よりも先にあいさつしていましたね。」
すてきなあいさつの三つ目は・・・・・『先に』です。
『にこにこ』『目を見て』『先に』そんなすてきなあいさつのあふれる高野山小学校にしましょう。と話しました。
高野山小学校には、あいさつだけではなくとってもすてきな行いをする子どもがいっぱいいます。
落とした鉛筆が手元に戻ってきました。拾って届けてくれた子がいます。そして「ありがとう」とお礼を言った子がいます。
落ちていた靴を、名前を見てその子の靴箱に入れてくれた子がいます。
雨の中、傘を差し、赤ちゃんをだっこして、水筒を届けに学校までいこうとしていたおかあさんに、「ぼくが届けましょうか?」と声をかけ、水筒を預かってくれた子がいます。・・・
子どもたちがこのように育っているのは、保護者のみなさまや地域のみなさまの応援のおかげです。本当にありがとうございます。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
実り多い2学期に
高野山小学校に子どもたちの元気な声と活気が戻ってきました。どの子の顔もやる気満々といった表情でとても頼もしい限りです。
保護者のみなさまには、様々な場面でご支援・ご協力をいただきました。
地区委員のみなさまにはパトロールをしていただきました。
バレーボール部のみなさまには7月と8月の大会に参加をしていただき、大健闘をしていただきました。
更には、ボランティアとして教室のカーテンを洗濯していただいたり、校庭の花壇の水やりにもご協力をいただきました。本当にありがとうございました。
学校ですが1学期末に転出があったり、夏休み中に転入があったりした関係で、9月1日現在児童数649名で2学期をスタートしました。42日間、家庭と自分自身のペースで過ごしてきましたので、学校の生活リズムに乗るまで少し時間がかかりそうです。子どもたち一人一人にきめ細かく関わることを基本に、2学期も教職員一同心と力を合わせてまいります。保護者のみなさま、地域のみなさまよろしくお願いいたします。
さて、学校は先述の通り、保護者のみなさまや地域のみなさまのご協力をいただきながら、どの子も学習などに自信を持ち、友達と協調、協力していけるよう社会性や思いやり・親切といった心情の育成に努めております。子ども時代は、大人になるための単なる準備期間だけではありません。子どもは、今という瞬間を楽しく精一杯生き、生きがいを持ち、明日へよりよいものを求め、将来への夢を抱き、その実現に前向きに進む存在であると思います。子どもに、今日という楽しさや充実があってこそ、何ごとにも意欲的になるのではないでしょうか。家族の愛情と心のこもった食事、公平で温かい教職員の指導、思いやりのある友達の存在、それら全てを見守ってくださる地域の目、その全てが子どもにとっての成長の土台だと思っています。
2学期もご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
すべては子どもたちのために
すべては子どもたちのために
校長 金子 博之
少なくとも私が教師になった30数年前までは、学校は安全で安心できるところだと、教職員はもちろんのこと、保護者の方々も地域の方々も社会全体が信じて疑いませんでした。事実そのように安全でした。
しかし残念なことに、日本社会の急激な規範意識の希薄化、日常生活のルールやモラルの欠如、知恵を絞って人をだましたりごまかしたりなど不正をなりわいとする人々の出現、子どもをターゲットにしてまさに食い物にする大人達の出現は、結果として子どもたちにとって危険な社会を生み出してしまいました。社会の浄化、大人のモラルの回復を叫ぶだけでは、子どもの安全は確保できません。日本人と日本に住む人の規範意識とモラルには、信頼するよりも、不信感を持って対処しなければならない事実が多すぎるように思われます。「知らない人と挨拶はしないようにしよう。」といった指導は、その典型です。
社会がだめになった、日本人がだめになった、地域環境が悪化した、他を責めているだけでは子ども達の安全な生活は保障できません。
学校・家庭・地域社会・警察などが連携し危機管理を徹底していくことが喫緊の課題です。その意味で、今回学校だよりと同時に発行された「地域安全懇談会通信」にある通り、高野山小学校PTAが中心となり、各種団体が一つにまとまっていくことの意義は、大変大きいと考えています。これをお読みになっていらっしゃる全ての人のお力をお貸しくださいますよう、改めてお願いいたします。ご理解とご協力をどうぞ、よろしくお願いいたします。
褒められた子 へこたれない子に
そのことを裏付けるような新聞記事が、つい先日5月4日付けの新聞に載っていましたので、ご紹介します。
子どもの頃に周囲に褒められた経験が多い人ほど、大人になってから困難な状況に直面しても、「へこたれない」傾向にあることが「国立青少年教育振興機構」の調査でわかったというのです。記事では、更に「褒められた」経験が多い人ほど、「へこたれない力」が強く、同時に「厳しく叱られた」経験も多ければ、より、「へこたれない」傾向が見られたと続いています。
記事は、私達、大人は子どもにきちんと向き合い、褒めるべきところは大いに褒め、悪いところはしっかり叱るという姿勢が重要であるとまとめています。
さあ、今からでも遅くありません。さっそく目の前のお子様で実践あるのみですね。
ぶれることなく見守り活動をお願いします
この原稿を書いている4月25日現在、逮捕された男は容疑者という扱いです。しかしながら、新聞記事やテレビのニュースを見ていると、個人的には限りなく犯人なのではないかと思っています。
女子児童と面識があっただけでなく、学校の保護者会の会長だったということで驚きましたが、だからといって私たち大人が見守り活動を、やめようという話にはなりません。
今回の事件の容疑者がただただ卑劣な人物であって、自主的に高野山の地域で見守り活動を行って下さっている、みなさまと同じくくりにしていいわけがないのです。どうぞ、ぶれることなく見守り活動を継続していただきたいと切に願っています。子どもたちを守るのは、学校・保護者・地域のみなさまが一体となった「チーム高野山」の力です。
ちょうど今日4月25日の午前中、1年生を対象とした「誘拐防止教室」が我孫子市少年指導員のみなさんによって実施されました。
担当の方からは、先月の学校便りでも載せた「い・か・の・お・す・し」のお話をしていただきました。
い か の お す し
いか・・・・・・知らない人にはついていかない
の・・・・・・・知らない人の車にのらない
お・・・・・・・危なくなったら大きな声で叫ぶ
す・・・・・・・人のいるところへすぐ逃げる
し・・・・・・・周りの大人にしらせる
改めて、この「い・か・の・お・す・し」の意味の大切さを痛感しました。痛ましい事件が二度と起きませんように。
今月もご支援・ご協力をどうぞ、よろしくお願いいたします。
平成29年度のスタートです
高野山小学校の今年の桜は、とても優しく、始業式と入学式を満開の桜で祝ってくれました。
新1年生113名を迎え、希望と期待の中で平成29年度の教育活動が元気よく始まりました。
今年度も「なかよく(徳育)・進んで(知育)・元気よく(体育)」の合い言葉通りの子どもたちの育成にむかって、質の高い教育活動が行えるよう教職員一丸となって取り組んで参ります。
4月6日の始業式の日の朝、東門の竹やぶ付近で登校指導をしていると、さわやかで元気なあいさつをする子どもたちと出会いました。その時、高野山小学校の素直で明るい子どもたちと、出会えたことを心からうれしく思いました。
始業式の校長の話では、「一生懸命がかっこいい」一生懸命が人の心を感動させる。という話をしました。
今年度も昨年同様、保護者のみなさま、地域のみなさまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。
時には立ち止まって
今年度もいよいよ最後の一月となりました。一月と言っても6年生は後2週間あまりで卒業です。今,その6年生とは,毎日のように校長室で会食を行っています。この会食は,毎年行っていますが,今年は,じっくりと話ができるようにと,1回の人数を減らしました。そのせいか,おしゃべりもはずみ,笑いの絶えない会食となっています。思わぬ「恋バナ」や内緒の話が聞けるのも会食の醍醐味です。
卒業式が近づいてきたので,そろそろ,「校長式辞」も考えなくてはいけません。6年生にとっては,一生に一度の大切な小学校の卒業式です。その中で話す式辞の内容は,毎年,時間をかけてじっくりと考えています。さて,今年はどんな内容にしようかと悩んでいる時,ふと,高野山小学校の「校章」が目に止まりました。校章には,6枚の葉が描かれています。その葉は,高野山小学校のシンボルである「ケヤキ」だということは予想できましたが,今まで,きちんと校章について調べてみたことがなかったので,改めて,調べてみましました。その結果,6枚の葉は確かにケヤキの葉でした。では,「なぜ6枚なのでしょうか」・・・「バランスや縁起がいいから」「1年生から6年生」・・・,6枚の意味もちゃんとあったのです。6枚のケヤキの葉には,「健康・英知・愛情・協力・根気・親和」と言う,6つの願いが込められて,昭和50年に開校と同時に作られたのです。その理由や内容については,卒業式の式辞の中で詳しくお話ししようと思っています。
私達の身の回りには,意外に知られていない秘密がたくさんあります。毎日忙しくしていて,つい見逃してしまいがちです。時には立ち止まって,気になることを詳しく調べてみることも必要ではないでしょうか。その中には,きっと大切なことがあるかもしれませんね。
悔いのないように
先日の「一日学習参観」の時には,急に「マスクの着用と消毒」をお願いしたのにも関わらず,多くの方にご協力をいただきました。お陰様で流行を最小限に抑えることができています。保護者の皆様のご理解とご協力に大変感謝いたします。
1月があっという間に過ぎ去り,今年度も残すところ2ヶ月となりました。「2月は逃げる」「3月は去る」と言われるように,この時期の時間の経過は,他の時期に比べてとても速く感じます。6年生は,卒業まで33日,その他の学年も修了式まで37日です。この1年間,悔いなく過ごせたでしょうか。残りが少ないからと言って,あきらめないで,最後の1日まで,できることに全力で取り組むことを期待しています。1日何かひとつでも達成すれば,
30以上の成果となります。1日10文字の漢字練習をすれば,300文字以上も書けるようになるのです。節分の日には「鬼は外,福は内」と言いながら豆まきをします。今までの「怠け心」を追い出し,「やる気」を体いっぱいにして,頑張って欲しいと思います。
また,今季は,インフルエンザが例年になく流行しています。休養と栄養を十分にとり,手洗いやうがいを念入りに行うことで予防にも努め,子ども達が残りの3学期を悔いなく過ごせるようにご支援ください。
立春とはいえ,まだまだ厳しい寒さが続きそうですが,校庭のウメやカワヅザクラが咲き始め,春はそこまでやってきています。西郷隆盛の漢詩の一節「雪に耐えて梅花麗し(梅の花は寒い冬を耐え忍ぶことで春に一番麗しく咲く)」のように,この時期,悔いのないように,しっかりと締めくくりを行わせ,次年度の更なる飛躍を目指して,梅や桜に負けない素敵な花を咲かせられるように指導していきますので,ご協力をよろしくお願いいたします。
新年を迎えて
今年は,松の内を過ぎての新学期となりました。始業式では元気よく新年の挨拶をして,3学期がスタートしました。
保護者や地域の皆様にも,新年のご挨拶を申し上げると共に,昨年に引き続き,よろしくお願いいたします。
始業式の中で,子どもたちと2つの約束をしました。1つ目は「進んで元気な挨拶をしよう」です。高野山小学校の子どもたちは,本当に元気よく挨拶ができます。その良さをさらに伸ばし,伝統の1つにして欲しいと思います。挨拶は,1日を気持ちよく過ごすおまじないです。大人も子どもも,進んで元気よく挨拶のできる高野山小学校であることを期待しています。
2つ目は「姿勢を良くしよう」です。「立っている時」「座っている時」どんな時であっても,お腹に少し力を入れて,背筋を伸ばして正しい姿勢を保つことを目指して欲しいと思います。特に,学習時,いすに姿勢良く座ることで,文字をきれいに書くことができたり,人の話を集中して聞くことができたりします。成長期の子どもたちにとって,正しい姿勢を保つことは大切なことです。もちろん大人にとっても,腰痛予防や体型保持には有効です。正しい姿勢を維持できない児童は体感が鍛えられておらず,精神的にも落ち着かない場合が多いと言われています。姿勢を正すことで,児童のよりよい発達を促すことを目指しますので,家庭でも気にかけていただけると,学校での指導がより有効に身につくと考えています。
1年生から5年生は53日,6年生は49日。3学期を充実させることは,次年度や中学校での生活にとって重要です。精一杯の指導に勤めますので,ご協力をお願いいたします。
実りの秋にするために
時候の挨拶として「実りの秋」という言葉をよく耳にします。言葉通り,これからの時期は米や果物,野菜など1年のうちで最も作物の収穫が多く,おいしい時を迎えます。また,今年も残すとこと2ヶ月となり,暦の上ではまとめの期間です。しかし,いくら「実りの秋」とはいえ,全てが突然,実を結ぶわけではなく,種を蒔き,大切に育てなければ,収穫は望めません。学校においても10月は,市内陸上大会をはじめとして,市内音楽発表会など,今までの活動の成果を発表する場がたくさんあります。子ども達は,それぞれの大会を目標に頑張ってきました。1学期とは見違えるような成長ぶりです。きっとその努力が実ることを期待しています。
この夏は,リオのオリンピック・パラリンピックで多くの日本人選手が活躍し,メダルを手にしました。また,私が応援する「広島東洋カープ」も25年ぶりの優勝を手にしました。メダルや優勝は,誰もが目標としているはずです。しかし,それを手にすることができるのは,極限られた人達です。多くの人は,メダルや優勝を得ることはできませんが,それまでの努力は決して無駄なことではありません。だからと言って最初からあきらめないでほしいと思います。ゴールの一瞬,ボールを放す一瞬まで,気を抜かないことが大切です。「実る」のではなく「実らせる」と言う強い気持ちが必要なのです。
スポーツや音楽に限らず,一人一人が目標を持って頑張っていることがあると思います。いつか絶対に「実らせる」という信念を持って,取り組んでほしいと思います。
「実る」のは,秋に限ったことではありません。5年後,10年後,いやもっと先のことかもしれません。いつかきっと「実る」ことを信じて,頑張ってほしいと思います。
オリンピックから学ぶこと
長い夏休みが終わり,2学期が始まりました。台風10号の影響で,やむなく林間学校を延期せざるを得なかったことは残念でしたが,子ども達は,夏休み中に取り組んだ課題や作品を手に,元気な笑顔を見せてくれたことを心から嬉しく思いました。しかし,今回の台風接近では直撃を免れたので,関東地方はほとんど影響を受けませんでしたが,東北や北海道では,大きな被害が出て,自然災害の恐ろしさを実感しました。災害への対応や備えは,最悪の事態を考えて,安全を第一に取り組む必要性を改めて考えさせられました。
私は今年の夏,オリンピック中継に釘付けでした。選手の健闘とメダルの多さはもちろんのこと,バドミントンやカヌーなどいろいろな種目で史上初のメダル獲得は,スポーツの多様性や面白さを知るきっかけとなりました。また,シンクロや卓球,体操などの団体競技を見ていると,互いの力を融合して更なる力が発揮できることを教えてくれた気がします。
さらに,陸上男子リレーで見せたバトンワークは,天性の運動能力を超える練習と技の素晴らしさを私たちに伝えてくれたように思いました。子ども達も,この様子を見ていて多くの刺激を受けたのではないでしょうか。
4年後は,東京でオリンピックが開催されます。選手として出場することを目標とするだけでなく,今回のオリンピックから学んだことを今後の目標にして,取り組んでくれることを期待しています。
精力善用(せいりょく ぜんよう)
6年生が「ふるさと学習」で学んだ講道館柔道創始者,嘉納治五郎氏が提唱された言葉です。「何事をするにも,その目的を達するためには,精神の力と身体の力とを最も有効に働かすが大切である」ということです。このことは,柔道をやっている人だけに当てはまることではありません。普通に生活している私たちでも,身体と心の健康が保たれなければ,快適な生活を送ることができないからです。身体の健康は,規則正しい生活や食事,運動などによって維持増進することができます。では,心の健康はでのようにすればいいのでしょうか。一つの方法としては,お互いを思いやり協力することで培うことができます。また,困ったことは相談したり,間違った言動に対しては勇気を持って注意したりすることも必要です。学校教育では,学習活動や集団生活を通してこのことを常に子ども達に指導しています。
しかし,子ども達の生活の基盤はなんと言っても家庭が第一です。特に,夏休みなどの長い休みは,その大半を家庭で過ごします。高学年なるに従って子ども達は大きく成長していきますが,まだまだ不十分です。心と身体のバランスがとれた成長を促すのは,大人の大切な責任だと考えています。夏休みの生活の仕方は学校でも十分指導しますので,その支援と見守りをお願いいたします。
一体感の奇跡
大きな学校行事のひとつである運動会が無事終了しました。今年は,オリンピックイヤー,4年後の2020年には再び東京でオリンピックが開催されます。子ども達にとってスポーツは,心身を鍛えるひとつとして,とても大切です。体育や運動会,部活動などを通して楽しく運動ができるようになり,2020年のオリンピックで活躍する選手が一人でも生まれれば素敵なことだと思います。
今年度の運動会は,奇跡的に両チーム共に777点,高野山小学校に幸運の女神が舞い降りた結果となりました。2人の応援団長が一緒に優勝旗を手にしたときの笑顔は忘れられません。
しかし,この結果は,単に奇跡や幸運だけはありません。暑い中で,一生懸命練習に取り組んだことによりもたらされたものだと思います。特に,応援団は,朝や放課後,各学年や学級を回り,熱心に練習し,当日も絶えず大声で応援を続けた賜と言えます。サッカーや野球でもサポーターの存在が選手のエネルギー源であるように,元気な応援は,児童の気持ちを奮い立たせます。共に力を合わせて競技に取り組むだけでなく,応援する児童との一体感が今回の結果になったと確信しています。
夏休みまでの2ヶ月間,気持ちを新たに充実した学校生活が過ごせるように,児童と教師が一体となって取り組みますので,保護者・地域の方々の熱いサポートをよろしくお願いします。
便利さの陰に
先日,新聞に日本PTA全国協議会が行った「携帯電話やスマートフォンに関する調査」によると,保護者の半数以上が「我が子の携帯電話やスマホを使ったインターネット利用の内容に制限を設けている」と答えたのに対し,子どもの半数以上が「ルールはない」と答え,保護者と子どもの認識の差を指摘する記事が掲載されていました。特にLINEやゲームにおける認識の差が大きく,保護者は注意して子どもに渡していても,実際に子どもが何に使っているかまで把握できていないようだと懸念していました。携帯電話やスマートフォンは,本当に便利ではある反面,その仕組みを十分に理解して使われているかは,私を含めて不安です。今一度,使い方についてのルールを確認し,有効に使いこなせるようにしていきたいものです。中学校では,トラブルも発生しているようです。
高野山小学校では,子ども達の「学校での使用」は認めていませんので,ご了承ください。
新年度のスタート
平成28年度がスタートしました。久々に登校してきた子ども達の笑顔も満開の桜の花に負けないくらい輝いていました。12名の新しい教職員を迎え,高野山小学校は,昨年度以上にパワーアップしています。
本年度も「なかよく 進んで 元気よく」を全校の合い言葉として,児童が将来,社会に役立つ自立した人間形成を目指して,教育活動を行っていきます。詳しくは,後日配布する「学校経営の方針」をご覧いただき,ご理解・ご協力願います。
現在,6月からのエアコン使用に向けて,取り付け工事を行っています。また,校庭に降りる階段脇の花壇をスロープに改修,放射線量の心配がなくなったプール周辺も活用し,1周約400メートルのランニングコースを整備しました。早速,陸上部の練習に活用しています。この他にも,子ども達が快適に過ごすための環境づくりに力を入れていきたいと考えています。これらの設備を有効に使い,学力向上や体力向上に努めます。
4月6日の朝,陸上部・吹奏楽部・合唱部の発足会を行いました。その中で,「高野山小学校の児童としての誇りを持って,演奏や競技に臨んで欲しい」と激励の言葉をかけました。演奏や記録の善し悪しは,不断の練習の結果として表れます。教職員一同一丸となって指導にあたりますので,保護者のご理解とご協力をお願いすると共に,演奏会や競技会での声援をお願いいたします。4月15日(金)は,今年度最初の授業参観と懇談会です。お忙しいとは思いますが,是非,ご参加ください。また,PTA総会にも出席願います。
日々の積み重ねが6年間の成長に
平成27年度も残すところわずかとなりました。3月1日,卒業を祝って
「6年生を送る会」を行い,各学年からの工夫した出し物で最後の楽しい一時を過ごしました。
卒業は,親しい人との別れですが,新たな旅立ちのスタートラインでもあります。1月中旬から6年生と給食の時間を使って,校長室で会食を行いました。5,6人と給食を食べながら,いろいろな話やゲームを楽しみました。一人一芸の発表では,楽器の演奏や縄跳び,剣玉や手品など,得意技を披露し,普段見られない一面を見せてくれました。また,中学校での抱負や将来の夢を語る自信に満ちた姿に,6年間の成長を感じました。高野山小学校を卒業していく子ども達は,自信を持って次のステージへのスタートができると確信できました。
6年間の成長は,一年一年の積み重ねです。6年生を送る会の各学年の出し物を見ていると,どの学年の子ども達にも確かな成長を感じることができました。過ぎてみるとあっという間の1年ですが,日々の学習と経験は,子ども達にとって貴重な財産となっています。
学年の修了を一区切りとして,1年を振り返ってみましょう。頑張ったことを自信にして,次の学年の目標を立てることも大切です。5回の修了を充実させることで,6回目の修了(卒業)がより感動的に迎えられるようにしていきたいものです。短い3月ですが,残り少ない学校生活を充実させ,晴れやかな気持ちで修了と卒業が迎えられるように,取り組んでいきたいと思います。
春はそこまで
2月3日節分を過ぎると,暦の上では春となります。今年は暖冬の予報が出ていましたが,底冷えのする寒さは身にしみますね。流行の遅れていたインフルエンザに感染する児童も増え始め,更なる予防に努めなければと注意を促しているところです。
節分は,本来,「季節を分ける」つまり季節が移り変わる節目を指し,立春・立夏・立秋・立冬それぞれの前日で,1年に4回あったものですが,日本では1年の始まりとして,立春の前の節分の日が尊ばれ,次第に節分といえば春の節分を指すようになったようです。
節分には豆まきをしますが,この習慣は中国から伝わったとされています。豆は「魔滅(まめ)」に通じ,無病息災を祈る意味があります。1年間健康に過ごせるようにとの願いを込めて,家族で豆まきをするのも,古くから伝わる日本の習わしを絶やさない活動になるのではないでしょうか。
とはいえ「習わし」だけでは,病気の予防にはなりません。十分な睡眠と栄養・手洗い・うがいの励行が大切な予防対策です。咳が出るときには,マスクを着用することも,感染を防ぐ重要な手立てです。日本は,マスクの着用率が高い国のひとつです。予防意識が高いだけでなく,人にうつさない配慮ができる優しさの表れだと思います。
追伸
市内在住の山田昭文様より桜の苗木5本を寄贈いただき,プール側滑り台のある小山の中腹に植えました。「染井吉野(そめいよしの)」よりやや遅咲きの「思川(おもいがわ)」という品種です。どんな花を咲かせてくれるか楽しみです。新しい高野山小学校の息の場となることでしょう。
新しい年を迎えて
新年明けましておめでとうございます。
今年は,とても暖かく麗らかな年明けとなりました。私は,実家の広島で新年を迎え,厳島神社に初詣し,1年の健康・安全を祈願してきました。瀬戸内の海は,春のように穏やかで,水面は初日に照らされてキラキラと輝き,今年もきっと良い年になる予感がしました。高野山小学校の子ども達が元気で頑張れるようにお願いしてきました。
始業式では,元気な子ども達と新年の挨拶をしました。とても落ち着いた態度で,楽しい年末年始を迎えたことを実感できる3学期始となりました。
不思議なもので,新しい年を迎えると誰もが「よし,今年こそ頑張ろう。」と気持ちを引き締めます。きっと子ども達もそうした気持ちになっていることでしょう。その思いを大切にして,3学期を過ごさせていきたいと思います。
「1月は行く,2月は逃げる,3月は去る」というように瞬く間に過ぎ去ってしまう3学期ですが,学年のまとめを十分に行い,新しい学年に向けての準備を整えて行きたいと考えています。
また,6年生は卒業までの日々がより充実したものになるように,一日一日を大切に過ごしていって欲しいと願っています。毎年行っている私との会食も楽しみです。給食時間の短い間ですが,将来の夢や印象に残った思い出をたくさん話してくれます。子ども達の意外な一面や特技が発見できる楽しみな時間です。
本年も,保護者や地域の方々のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
安全で安心できる生活を
長い夏休みが終了しました。厳しい暑さから一転,少し肌寒ささえ感じる今日この頃となりました。2学期の始業式では,久しぶりに会う友達と笑顔で思い出を語り合う楽しそうな子ども達の表情に,喜びが込み上げてきました。というのも,大阪で起きた事件は,楽しいはずの夏休みを一瞬でかき消してしまうほどの衝撃的な事件が起きてしまったからです。我孫子でも決して起こり得ない事件ではないので,休み中ではありましたが,本当に悲しく不安な気持ちになりました。幸いにも,本校ではそうした事件や事故の報告はなく,ひと安心しました。この事件を教訓に,2学期以降,子ども達が安全で安心できる,落ち着いた学校生活ができるように,教職員一同,子ども達の指導をより充実させることを確認しました。
特に,交通安全については,危険個所を確認し,登校指導を実施します。
また,防災に関しても,万が一を想定して訓練を行います。安全の確保は,子ども達自身に,危機意識を持たせることが一番の予防策となりますので,学校と家庭が連携して指導ができれば,より効果的だと考えています。
しかし,下校後の子ども達の行動は,学校では十分把握できません。保護者の帰宅まで1人で過ごす場合は,やむを得ないとは言え,不安です。各家庭での約束を十分行い,安全に過ごせるようにご配慮ください。8月からは,「あびっ子」も開設しています。有効にご利用いただければと思います。
家庭での子ども達の生活リズムは,学校生活にも大きく影響します。就寝時刻が遅いと朝が早い学校生活は辛いものです。朝食を食べないで登校すると,活動のエネルギーが低下し,集中力・思考力が低下してしまいます。子ども達の家庭生活は,各家庭で十分ご配慮ください。
19日の「教育ミニ集会」では,子育ての悩みを参加者で共有し,よりよい指導の在り方を話し合いたいと思っています。また,最近は,家庭の躾だけでは解決できない特別な支援を必要とするケースも増えています。体調を崩した時に病院に行くように,専門の機関と連携して対処することの大切さが注目されています。必要な支援を専門機関と連携して行うことは,困り感を持つ家庭や子ども達にとって,とても重要です。いつでもご相談ください。
夏休みを前に
3年生と6年生の代表児童が,1学期を振り返って,頑張ったことを発表しました。3年生は運動会について,6年生は修学旅行についての内容でしたが,2人とも,その取組を通して,学んだことを堂々と発表できました。2人が代表で発表してくれましたが,その他の児童も,1学期が終了し,明日からの夏休みを期待する,嬉しそうな表情で終業式に臨んでいました。
今年度は,休日の関係で,例年より早い夏休み入りとなります。子ども達にとっては,嬉しいことでしょうが,保護者の皆様はどうでしょうか・・・。
長い夏休みに入る前ですが,心配なことがあります。昨日,地域の方から2件ほど,ご注意のお電話を頂きました。
どちらも,道路で遊ぶ子ども達を見てのご意見でした。道路は,車が往来し,多くの方が利用する公共の場です。自転車やキックボード,ボールで遊ぶ子ども達は,遊びに夢中で車や人の往来が目に入らないようです。そうした様子をご覧になった地域の方々は,怒りではなく,子ども達の命の危険を危惧して,お知らせくださっています。
今日の終業式の中でも,具体例を示して注意を呼びかけました。本日,手紙も持たせましたので,各家庭でも安全への配慮をお願いいたします。
また,夏は,水遊びも楽しみのひとつです。子ども達だけの水遊びは大変危険ですので,併せて,ご注意ください。
9月1日始業式に,全員の笑顔が見られることを楽しみにしています。
ジャブジャブ池,今年度も放水開始
今日は,久しぶりの青空で,子ども達も上着を脱いで,元気よく活動していました。
昨年復活した「ジャブジャブ池」。今年も,やっと水を流し始めることができました。
子ども達の大好きなジャブジャブ池です。安全に気をつけて使わせていきたいと思います。

110名の笑顔を迎えて
昨日の霙混じりの冷たい雨で,今日の天気が心配でしたが,1年生の入学を祝うかのような晴天で,子ども達の笑顔がキラキラと輝いて見えました。1人の欠席者もなく,入学式が行えたことを本当に嬉しく思いました。
校長の式辞の中で,お祝いに来て下さった来賓に,一緒に元気よく「ありがとうごさいます」とお礼を言うことができました。「ありがとう」という言葉は,お祝いしてもらった時だけでなく,友達に親切にされたり,助けてもらったりした時に,うれしい気持ちを伝え,仲良くなれる魔法の言葉だという話をしました。友達と楽しく過ごせるように,「ありがとう」が素直に言える1年生になる約束をしました。
また,進んで元気な挨拶をしたり,よく食べ,早寝早起きをして,怪我や病気にならないように気をつけ,学校を休むことがないようにしようとも約束しました。少し長い話になりましたが,ちゃんと話を聞く1年生の態度は,本当に立派でした。
高野山小学校は今年で,創立41年目となります。40年の積み重ねを大切にしながらも,新たな飛躍を目指して,教育活動に取り組んでいきます。
昨年同様,子ども達の「自立」を目指した活動は継続します。更に,安心・安全な学校にするために,保護者や地域の方々との連携,職員の危機意識の強化に努めていきたいと考えています。
また,最近の子ども達の理科離れの実態を踏まえて,身近な事象の観察,体験や実験を通した科学的な思考力や判断力の育成に取り組みます。
昨年1年間のホームページの閲覧が7万件近くあったことを励みに,その更新や内容の充実も図っていきたいと思います。
今後とも引き続き,ご支援のほどよろしくお願いいたします。
1年を振り返って
桜の開花を間近に控え,平成26年度の修了式を終えました。本年度,高野山小学校では,大きな事故や怪我もなく,無事1年の教育活動を終了できたことに,大きな喜びを感じています。これも,保護者や地域の方々のご理解とご協力のお陰だと心より感謝いたしております。
昨年4月,校長として,以前勤務していた懐かしい高野山小学校へ着任しての1年間。毎日が,それまでの10倍のスピードで過ぎ去ったように思います。それは,楽しい時が瞬く間に過ぎ去る感覚だっと思います。
始業式に始まり,入学式,運動会,林間学校に修学旅行,ふれあい祭り・わんぱく祭・合唱祭,あっという間に,卒業式に修了式。
大きな行事だけでも,これほどの行事があります。それに加えて,陸上大会や音楽コンクール等の対外行事。その隙間をうめるように行う学年行事の数々。小学校は,1年間が学習と行事の積み重ねで成り立っていると言っても過言ではありません。子ども達は,これらの活動を通して成長しているのです。
さらに,子ども達にとって大切なことは,こうした活動を通して,友達との関わり方を学ぶことだと考えています。協力することや助け合うこと,我慢することも学びます。どんなに,やりたくても,必ずしも希望が叶うことばかりではないことを経験します。集団で生活することのルールや厳しさを学ばせるのも,学校教育の役割なのです。
しかし,私達は,子ども達一人一人の個性を大切にしながら,その良さを伸ばしてあげなければいけません。一人一人を十分理解するためには,保護者の方との連携が不可欠なのです。
1年間を振り返ってみて,この連携が十分だったとは言えないと思いますが,今年度の反省を生かして,4月から始まる平成27年度の教育活動に取り組んでいきます。引き続き,ご支援とご協力をお願いいたします。
卒業式を終えて
校長式辞では,今年6年生が書き初めで書いた「少年の志」を題材に,「志」には,「目標」と「相手を思いやる気持ち」の二つの意味があり,目標に向けて努力することの大切さや目標達成には,努力はもちろん,「人のため」「社会のため」に頑張ろうとする気持が大切である話をしました。
担任が一人ひとり名前を呼んだ時,大きな声で返事をし,呼びかけや卒業の歌では,今までにない大きな声やきれいな歌声を聞かせてくれました。
多くの来賓の皆様が,本当に立派な卒業式だったと褒めて下さり,誇らしく思いました。
退場の時,担任の前で,一人ひとり丁寧にお辞儀し,「ありがとうございました」と感謝の気持ちを伝えると,担任は,感激のあまり号泣状態でした。
こんな素晴らしい卒業式を実施できたのも,保護者や地域の方々のご理解とご協力の賜物でと感謝いたしております。本当にありがとうございました。
さらに安全・安心な学校にするために
今年度の6年生は14日、その他の学年も18日と、学校で活動できる日が、残り少なくなってきました。子ども達は、6年生を送る会や学年のまとめに、真剣に取り組んでいます。
川崎の中学生が、刃物で傷つけられ、大切な命を失うと言う、大変悲しい事件が発生したことは、他人ごとではなく、学校の安全管理や危機意識を見直す、重要なできごとだと受けとめています。
小学校でも、カッターナイフなど図工で使う機会も多く、子ども達は紙を切ったり、木を削ったりできる便利な道具だという認識で使っています。
今日の集会では、便利な道具も使い方を誤れば、大変危険な道具になってしまうこと、傘や棒きれ、小さな石ころでさえ、人にむかって振り回したり、投げたりすれば、たいへん危険であることを話しました。
また、物だけでなく、悪口や脅すような言葉も、人の心を傷つけ、時間がたっても治らないことなど、友達との関わりの中で、許されない行為があることを話しました。
さらに、もうひとつ、おこずかいの使い方についても話し、むやみに、買ったものを友達にあげたり、もらったりしないようにとの約束をしました。
最近、高野山小学校でも、おこずかいで買った不要なものを友達にあげて、トラブルの原因になっている出来事がありました。各家庭でも、お金の管理同様、子ども達の持ち物にも、十分注意していただき、トラブルの回避に努めていただきたいと思います。
学校においても、子ども達の言動を十分把握し、困っている児童の相談には、親身に対応していくことを、全職員で申し合わせ、本年度のまとめに取り組んでいくことを、確認いたしました。
悔しさと成長
2月7日(土),第11回我孫子市青少年綱引き大会が,市民体育館で開催されました。高野山小学校の5・6年生も大勢参加しました。チームは,学級単位で,6チームが参加しました。
予選リーグの戦績により,「どんぐりトーナメント」か「決勝トーナメント」に進むことができます。たくさんの保護者の方が応援して下さる中,どのチームも全力で戦うことができました。
出場したチームは,どこも全力で戦います。ちょっとしたタイミングで,勝ったり負けたりします。全力を出し切っても負けてしまうと,子ども達は本当に悔しそうです。でも,すぐに気持ちを切り替え,次の試合を全力で戦う姿は,本当に感動的でした。
勝った時は,満面の笑顔でハイタッチをする子ども達。負けた時の悔しさを味わっているだけに,喜びもひとしおです。
「負けるとかわいそう」と思いがちですが,その悔しさを知っているからこそ,「次は,絶対勝ちたい」「勝つと本当に嬉しい」と思えるのです。もちろん,勝ち続けることは大切なことかもしれません。しかし,負けを経験することも,子ども達の成長には必要なことなのです。
「悔しさ」を生かせる子どもになって欲しいと思います。
合同作品展に行ってきました
節分を過ぎると,暦の上では春の到来ですが,まだまだ寒い日が続きます。最近また,インフルエンザによる欠席も増え,油断できない状況です。
しかし,子ども達は元気に縄跳びや授業参観での学習成果の発表の練習に取り組んでいます。残りの期間,充実した毎日が過ごせるように,支援をしていきたいと考えています。
1月30日(金)から2月1日(月)まで,柏ステーションモール8階市民ギャラリーで,特別支援学級の子ども達の作品展が行われています。私も30日の仕事帰りに見に行ってきました。力作がたくさん展示されていていました。どの作品も丁寧で,色鮮やか。子ども達の感性の豊かさに感動しました。細かい作業が施された工作。力強い筆運び。子ども達の個性が生かされ,本当に見ごたえのある作品展でした。
本日15時まで開催しています。お時間のある方は,ぜひご覧ください。


6年生との会食(1)
今,6年生と会食を行っています。5~6人ずつ,校長室のテーブルを囲んで,楽しくおしゃべりしながら,給食を食べています。
今日で1組が終了しました。会食の話題は,その場で,テーマを決めて,1人ずつ話します。「好きな食べ物」「趣味」「行ってみたいところ」「中学での部活」「将来の夢」など,メンバーによって様々です。
その場で決まるテーマですが,みんなちゃんと答えて,その理由もしっかりしているのに驚きます。特に,ほとんどの子ども達が,将来の夢を力強く語ることができていることに,感心しています。また,夢の実現に向けて,今やるべきことをしっかりと理解し,取り組み始めていることにも驚きます。私自身,小学生の時,こんなにしっかりした考えを持っていたかどうかは疑問です。
子ども達は,始めのうちはやや緊張気味ですが,慣れてくると何でも話してくれます。その中にお父さんやお母さんの仕事のことも出てきます。
「お父さんのような仕事がしたい」という子も結構多くて,感心します。
誰ひとり私と同じ仕事に就かなかった娘達,うらやましい限りです。きっと各家庭での会話や励ましが,影響しているのでしょう。高野山小学校児童の家庭環境の良さを実感しました。
明日からは4組との会食。どんは話題になるか,とても楽しみです。
利用の仕方によっては
インターネットの動画サイトに面白半分に,動画を投稿し,逃走の様子や世間に対する自分の思いを伝えていた少年。本当に不愉快な思いで,ニュースを見ていました。
先週,金曜日の教育ミニ集会でも,携帯電話やスマートフォンの使用について話し合いを持ちました。それらは,急速に普及し,今や無くてはならないツールとなっています。私自身もスマートフォンの利用者の1人です。いつも所持していて,忘れると不安を覚えるまでの存在になっています。使い方によっては,本当に便利で,これ一台で何でもできてしまう気さえしてしまいます。
保護された少年も,自分自身が神のごとく,無限の力を与えられたような錯覚をしてしまったようです。今回のような使い方は,社会を混乱させ,多くの人に迷惑をかけると言う誤った使い方と言えます。
今までは,そうしたツールによって,有害なサイトや情報によって,使用するものが被害にあう危険性を心配していました。しかし,今回のような事件では,情報を発信する側のモラルやルールについて,考えなければならないことを示唆しています。小学校における情報教育においても,これらのことを十分に意識して,子ども達の指導に当たらなければならないことを痛感しました。
各家庭においても,これらの購入や使用の際には,十分な話し合いを持ち,節度のある使い方ができるようにお願いしたいと思います。
餅になるまで
今日,5年生が,自分達で育てたもち米で餅つきをして,「新年を祝う会」をしました。
もち米栽培でお世話になった岡田さんや臼を貸して下さった飯田さん,かまどやせいろを貸して下さった調理員の齋藤さん,それに40人以上の5年生のお父さんやお母さんの手伝いで,おいしいきなこ餅や雑煮を食べて,収穫と新年を祝うことができました。
先日紹介した「七草がゆ」同様,餅つきも日本の大切な文化のひとつです。田植え・稲刈りと一連の活動は,5年生にとってとても貴重な体験と思い出になったことでしょう。
それともう一つ忘れてはいけないことがあります。
今日食べた餅は,多くの人の手間と苦労があるからこそ,おいしく頂くことができたのです。種籾から餅になるまでは,長い時間と多くの人の手がかけられています。種を播けば餅になるわけではありません。そのことを,体験を通して学ぶことができました。
餅だけでなく,私達が食べる食物はすべて同じ。だからこそ,粗末にすることなく,感謝して食べる必要があるのです。
ご協力いただいた多くの皆様,本当にありがとうございました。
始業式の話の中で
昨日の始業式で,「七草がゆ」の話をしました。
7日の朝にお粥を食べた児童は,そんなに多くはいませんでした。確かに,朝からお粥を準備するのは大変ですよね。正直なところ,我が家でも「七草がゆ」を食べたのは,昨日の夕飯でした。
しかし,「七草がゆ」のことは,多くの児童が知っていて,春の七草の名前を言える児童もいて,驚きました。
芹(せり):水辺の山菜で香りがよく,食欲が増進。
薺(なずな):別称はペンペン草。江戸時代にはポピュラーな食材でした。
御形(ごぎょう):別称は,母子草で,草餅の元祖。風邪予防や解熱の効果あり。
繁縷(はこべら):目の良いビタミンAが豊富で,腹痛の薬にもなった。
仏の座(ほとけのざ):別称はタビラコ。タンポポに似ていて,食物繊維が豊富。
菘(すずな):蕪(かぶ)のこと。ビタミンが豊富。
蘿蔔(すずしろ):大根(だいこん)のこと。消化を助け,風邪の予防にもなる。
以上,インターネットで検索した情報です。
これらの野草を自然の中で見つけ出すのは大変なことでしょう。我が家もデパートで「七草セット」を購入し,お粥に入れて楽しみました。
こうした日本の古くからの習慣や文化は,これからも大切にしていきたいですね。
新しい年を迎えて
いよいよ明日は,3学期始業式です。平成26年度も残すところ3か月となりました。新しい年を迎えて,気持ちを切り替え,残りの日々を大切にしていきたいと思います。
2学期末は,例年になくインフルエンザで欠席する児童が多くなって,終業式も体育館でできない状況となってしまいました。明日の始業式は,全員が元気な顔を見せてくれることを期待しています。
新年を迎えると,不思議と気持ちが引き締まります。大晦日と一晩違うだけなのに,これほど違った気持ちになるのは,本当に不思議なことですね。良いことも,悪いことも,ひと区切りをつけ,新たなスタートができるのも新年の良さだと思います。
3学期は,とても短い学期ですが,学年のまとめをする大切な期間です。悔いが残らないように,精一杯頑張ってほいいと思っています。私達教職員も,一致団結して,卒業式や修了式が迎えられるように取り組んでいきたいと思います。ご協力よろしくお願いいたします。

2学期を振り返って(その2)
2学期は,学校だよりやホームページで,できるだけ学校の様子を伝えるようにしました。保護者や地域の方の学校への関心が高く,11月のアクセスは6583回,12月は22日現在で,すでに6290回となりました。今後も,できるだけタイムリーな情報を提供できるようにしていきたいと思います。
また,校内の危険な個所をできるだけなくすように,教育委員会に働きかけ,可能な修繕を行ってもらいました。予算の厳しい中,子ども達の安全を第一に,学童への通路や「ジャブジャブ池」の前の段差をなくす工事を行ってもらいました。まだまだ,十分とはいえない状況ですが,できるだけ努力していきたいと考えています。
平成26年度も残すところ3か月。大きな行事は,卒業式だけとなりました。6年生が,立派に卒業できるように,全職員で支援していきたいと思います。また,その他の学年の児童も,充実した1年間だったと思えるように,全力で教育活動を行っていきたいと考えています。
皆様のご理解とご協力に心から感謝しております。新しい年,平成27年もよろしくお願いいたします。
ご多幸と健康をお祈りいたします。よいお年をお迎えください。
校長 小椿 清隆
2学期を振り返って(その1)
とはいえ,例年になく,インフルエンザの流行が早く,早帰りや学級閉鎖の対応をせざる状況になり,ご迷惑をおかけいたしました。今日現在も,欠席者が多く,2学期の終業式は,体育館で行わず,校内放送を利用して行うことにしました。子ども達一人一人の顔を見ながら話ができなく,非常に残念な思いです。3学期の始業式では,全校児童の元気な笑顔が集うことを期待しています。
2学期を振り返って,印象に残ったことのひとつに,給食の残菜が減ったことです。今まで,20%を超える残菜量のメニューがほとんどなくなりました。依然,20%を超えるのは,「野菜のお浸し」です。どんなに,味付けを工夫しても,野菜の多いメニューは子ども達の食べ残しが多いようです。私は,毎日,子ども達が食べる前に,検食(事前の味見)をします。給食で出されるお浸しは,家庭で作るものより(我が家)も,茹で野菜の歯触りや味付けも工夫されていて,とても美味しく(私の主観では)できています。それが,たくさん残り,処分されるのは,本当に残念で仕方ありません。今年度から,学期に1度,各学年の先生と栄養士,調理員の代表で,「給食委員会」を開き,給食の改善を行っています。その成果が,メニューの改善や残菜量の減少につながったと考えています。今後も,検討と改善を重ね,安全で楽しい給食を目指していきたいと思います。
保護者からのお手紙
本日,1人の保護者からお手紙をいただきました。
学校便りを11月からリニューアルしたことや校長からの一言についてのご意見でした。
日々の教育活動は,学年便りや学級だより,ホームページ等で,できるだけお伝えできるようにしています。毎日の出来事はその都度更新するようにしています。お陰さまで,アクセス数が年度当初よりも大きく増え,平日は1日で300回以上,11月の1ヶ月で6583回もの閲覧をいただきました。皆様の関心の高さを知ることができました。
学校便りについては,単なるお知らせだけではなく,高野山小学校の学校経営や教育活動を,一層ご理解いただけるように,メッセージ性のある内容にしたいと考え,新聞形式に改めました。少し内容が多くなり,読みにくさはあるかとは思いますが,校長としての思いをお伝えできるように工夫いたしました。
お手紙は,その内容に共感していただい旨を,美しい手書きの文字で綴ってありました。読ませていただいた瞬間,嬉しさがこみ上げてきました。本当に嬉しくて,何度も何度も読み返しました。私の思いを,受け取って下さった方がいたことの喜びを実感しました。
今は,メールや電話で要件を済ませることが多い中,このようなお手紙でのご意見は,本当に貴重です。学校に対するご意見やご要望がありましたら,頂戴できると嬉しく思います。
実現可能なものと難しいものとはありますが,学校教育改善に役立てていきたいと思います。
iPad 20台の寄贈を受けました
これからが,流行の時期となりますので,全校をあげて予防に取り組んでいきたいと思いますので,ご協力をお願いいたします。
12月3日(水)に,我孫子市教育委員会は,科学雑誌「ニュートン」を発行しているニュートンプレス社から,40台のiPadの寄贈を受けました。そのうちの20台を高野山小学校に頂けることになりました。このタブレット端末には,現在,6年生理科の教材がインストールされています。将来的には,4年生以上の教材がインストールされる予定です。
この端末は,インターネットには接続されていませんが,写真や動画を撮影する機能や各教室の大型テレビに簡単に接続でき,活用が可能です。どのように使えば,楽しく分かりやすい学習ができるのか,研修を行いながら効果的な活用の仕方を工夫したいと考えています。
ご期待下さい。

寄贈された20台のiPad

大型テレビと接続し,
教材(ろうそくの仕組み)を提示

寄贈を受ける倉部教育長
・・・私も贈呈式に参加しました。
師走を迎えて
平成26年も残すところ,1ヶ月となりました。4月に着任以来,子ども達の大きな事故や怪我もなく,安全に過ごすことができたことを本当に嬉しく思います。その背景には,保護者や地域の方のご理解・ご協力があったからこそと,感謝しております。
「師走」という言葉通り,2学期のまとめに慌ただしく過ごしている毎日ですが,子ども達から目を離さず,充実した学校生活ができるように,頑張って参ります。
惑星探査機「はやぶさ」の打ち上げがちょっとした気象条件により,何度も延期されています。その打ち上げ時刻が秒単位まで設定されている理由として,目標とする惑星に到達するには,何億分の1というわずかな打ち上げ角度が,目標達成に左右すると言うことを知りました。子ども達のよりよい成長を見守る我々も,子ども達の将来を見据えて,細心の注意を払い成長の方向性を見極めていかなければいけないという点では,共通しているのではないでしょうか。
しかし,修正の効かないロケットの軌道とは異なり,「修正の積み重ね」が成長につながるとも言えます。失敗を認め,改善を繰り返すことを大切にした教育活動に励んでいきたいと考えます。
卒業式・入学式に向けて
ヒマワリやコスモスが咲いていた正門脇の畑は,菜の花を播くための準備をしています。菜の花は,切り花にして卒業式に飾る予定です。
また,卒業式に飾る「サイネリア」という花を種から播き,苗を育てています。この苗をもっと大きくして,見栄えのする大株に育てるために,さらに大きな植木鉢に植え替えなければいけません。直径が20センチメートルくらいの白いプラスチック鉢がたくさん必要です。もし,家に不要なプラスチック鉢がありましたら,お譲りいただけると大変助かります。

大きく育った「サイネリア」の苗。これを,プラスチック鉢に植え替えます。

たくさん必要な「白いプラスチック鉢」
花壇やプランターには,「サクラソウ」や「パンジー」「ビオラ」などを植えて,卒業式や入学式に彩りを添える予定です。たくさんの苗が順調に育っています。花壇やプランターへの移植は,用務員さんが中心に行っていきますが,とても,時間と手間がかかるので,時間のある時は私も手伝います。もし,興味のある方は,ご一緒に作業をしませんか。

たくさんの「パンジー」「ビオラ」の苗。この苗を,花壇やプランターに移植します。
「白いプラスチック鉢の提供」と「移植作業のボランティア」
お待ちしています。
地区別(天王台地区)合同防犯懇談会に参加して
11月10日の月曜日,「こもれび」で天王台地区の防犯懇談会が開催されました。我孫子市防犯協会や我孫子警察,学校,PTA,自治会,少年指導員等,30名以上の方々が出席されました。
各団体から活動の状況や課題が出され,それぞれの立場から意見を出し合って,有意義な意見交換ができました。話題は,最近多発している振り込め詐欺,街灯のLED化,子ども達の安全についてが中心でした。
高野山小学校の子ども達の安全については,PTAや地域の方々のご協力により,今年度大きな事件や事故もなかったものの,「ひやり・ハッと」した場面がみられたことが意見として出されました。
①自転車の乗り方や飛び出しが危険。
②公道で,「ローラーボード」に乗っている児童を見かける。
③午後4時を過ぎても公園で遊ぶ小学生の姿がある。
④1人で下校する低学年が心配。 等々
地域の方々は,子ども達の事を本当によく見て,心配して下さっていることを痛感しました。
早速,11日朝の教職員の打ち合わせで,このことを話し,もう一度,各学級で指導するように伝えました。日頃から児童の安全については,いろいろな方法で指導を重ねています。
「1年生の防犯教室」「道路歩行や自転車の乗り方などの交通安全教室」「職員による登下校指導」に加え,毎日必ず注意事項を話してから下校をさせています。
しかし,子ども達は,1日が終わった解放感から,おしゃべりに夢中になって,注意がおろそかになってしまうごとが多いようです。下校時や帰宅後,子ども達の危険な行動を見かけましたら,一声かけていただくと,嬉しく思います。注意しずらい時には,学校にご一報いただいても結構です。
学校でも指導を徹底いたしますが,学校と地域が一体となって,子ども達の指導に関わっていくことが,事件・事故の防止につながると考えています。よろしく,ご協力ください。
全校朝礼で
まず最初に,「半年を振り返って,どうですか? ひとつでも頑張ったことのある人は?」の問いかけに,半数の子ども達が手をあげました。「校長先生は,みんなが朝元気よく挨拶をしてくれるのが,とっても嬉しいよ。それに,合唱部や吹奏楽部,陸上部,とってもよく頑張ったね。」と半年の頑張りを褒めると,とてもうれしそうな笑顔を見せてくれました。新しくできた「奉仕活動部」の話もしました。「火曜日から木曜日の朝,落ち葉掃きをしています。今は,10人での活動ですが,みんなのために頑張っています。見かけたら,元気よく挨拶をしてあげて下さいね。」
次に,先日4年2組で行った「人権尊重の授業」について話しました。その中で出た「チクチク言葉」「フワフワ言葉」について話すと,ほとんどの子ども達が,その言葉を聞いたことがあり,1年生でもその意味を知っている様子でした。「自分では気がつかなくても,友達が傷ついてしまう言葉や行動があるから,相手の気持ちになって仲良くしようね。」
次に,「妖怪ウオッチを持っている人は?」と聞くと,驚くことに低学年の多くの子ども達が持っていると答えました。「校長先生は,持っていないからうらやましいな。欲しいな。」と言うと,「あげるよ」と優しく反応してくれる子どももいました。「でも,どんなにうらやましくても,大切なものだから,勝手にさわったり,使ってはダメだよ。鉛筆や消しゴムなども同じだよ。心のブレーキをかけてね。」・・・「心のブレーキ」の話は,1学期もしたので,覚えている子がたくさんいました。
さらに,「困った時には,相談しよう」と呼びかけました。学校には,毎週,火曜日と水曜日に「何でも相談できる先生(心の相談員)」が来ていて,気軽に相談できることを話しました。「でも,一番みんなのことを知っていて,相談にのってくれるのは・・・」と問いかけると,「担任の先生」と何人もの子ども達が答えてくれました。「誰に相談してもいいけど,担任の先生が一番。どうしても話せない時は,校長先生のところに来て話してもいいからね。」
最後に,「高野山小学校には,素敵な合言葉があるね。」と尋ねると,全員が「なかよく 進んで 元気よく」と答えることができました。「この合言葉のように,過ごせるように頑張りましょう。」「はい!」 気持ちのよい元気な返事で,全校朝礼の話を終えました。
友達を思いやり,仲良くしよう
高野山小学校の周りでも,あちらこちらで紅葉し始め,すっかり秋が深まってきました。子ども達は,合唱祭に向けて,きれいな歌声を響かせて,練習に取り組んでいます。本番の発表が,本当に楽しみです。
先日,4年2組で,我孫子市の人権擁護委員会の方が,「友達への思いやり」をテーマに,道徳の授業を行ってくださいました。誕生日のプレゼントをめぐり,いじめられてしまう友達を助け,お互いの気持ちを理解することで,問題を解決していくお話をもとに,「思いやり」の大切さを学習することができました。
高野山小学校の子ども達は,登校する時,元気よく「おはようございます」と挨拶できる子ども達がたくさんいます。休み時間には,誘い合って,外で仲良く遊ぶ子ども達もたくさんいます。本当に,明るく,仲良く,元気に過ごしていることを嬉しく思います。
その一方で,友達の持ち物を勝手に使ったり,相手を傷つけてしまう言葉を使ってしまったりして,お互いいやな思いをしてしまうことも起きています。話をよく聞くと,少し「心のブレーキ」が効かなかったり,相手への「思いやり」が足りなかったりしているようです。
11月の全校朝礼では,もっと仲良よく,楽しい学校生活が送れるように「友達を思いやり,仲良くしよう」をテーマに,話をしたいと思います。また,困った時には,「お家の人や先生に相談し,解決していこう」と呼びかけたいと考えています。
さらに,4年2組で勉強したことを,他の学年や学級でも行い,学校全体で「思いやり」の大切さに気づかせ,もっともっと楽しい学校にしていきたいと思います。

高野山小漢字検定実施します
今学期の目標として、「高野山小漢字検定の実施」をかかげました。落ち着いて学習に取り組めるこの時期に、実施することにしました。
先日、6年生だけに、試作問題をやってみました。間違いやすい読みや四文字熟語など20問。かなり難しかったようで、各学級の平均が40点前後でした。しかし、中には、80点以上の児童も数人いました。6年生の担任に結果を伝えると、高得点の児童には、読書好きが多い傾向が分かりました。また、テスト終了後、友達同士で、答えの確認をするなど、漢字への興味は高まったようです。
試作問題は、以下の20問、ぜひ、挑戦してみて下さい。
①発足 ②数寄屋 ③異口同音 ④潮騒 ⑤秋刀魚 ⑥一日千秋 ⑦乙女 ⑧茶飯事 ⑨一期一会 ⑩砂利
⑪発起人 ⑫十人十色 ⑬若干 ⑭最寄り ⑮前代未聞 ⑯山車 ⑰宮内庁 ⑱老若男女 ⑲喧嘩両成敗
⑳本来無一物
「潮騒」は、NHKのドラマの影響か、正解率が高く、「山車」は、馴染みがないのか、「オフロードカー」なんて、ユニークな読みをする児童もいました。
試作問題は、かなり難しかったようなので、実際の検定は、クイズ的な問題にして、3年生以上で実施します。漢字の読み書きが向上するようにというより、漢字への興味を高めることを目的に実施しますので、ご家庭でも一緒に楽しんでみて下さい。
読書をしよう
今週も台風襲来で、心配な週明けとなりました。幸いにも、高野山小学校では被害もなく、1時間遅れで授業を開始しました。今日いっぱい、まだ強い風が残るようですが、台風一過の晴天で、子ども達は元気に過ごしています。
先週の「皆既月食」、どうでしたか?月が欠け始めた時は、とてもきれいに見えていましたが、肝心の皆既の時には、雲に隠れてしまい、終了間際に、姿を現したそうですが、残念ながら私は見ることができませんでした。3年後に再び見るチャンスがあるそうですので、リベンジしたいと思います。
前々回に「読書」の事を書きましたが、今回は、私が小学校の時に好きだった、2冊の本を紹介します。
1冊目は「十五少年漂流記」です。
この物語は、あることから船で漂流してしまった十五人の少年達が無人島にたどりつき、協力して数々の困難に立ち向かう話です。私は、小学生のころ、あまり物語が好きな子どもではありませんでした。しかし、この本は、時間を忘れ、一気に読んでしまうほど、面白い内容でした。ハラハラ、ドキドキ・・・次は、どうなるのだろうと、途中で、本を閉じることができなくなってしまいました。読み終わった時には、自分も十五人の一人になったような気分で、喜びと勇気が湧いてきました。
もう1冊は「ファーブル昆虫記」です。
私は、小学校の時、理科は好きでしたが、どちらかというと、虫は苦手でした。しかし、この本は、シリーズでいろいろな虫のことを詳しく、知ることのできる興味深い内容でした。特に、自分の糞を丸めて運ぶ「タマコロガシ」の話は、すごく面白くて、大好きでした。理科の観察が好きになったのも、この本の影響かも知れません。
読書は、言葉の理解や巾を広げ、心を豊かにします。1冊の本との出会いが、その後の生き方に影響することもあります。好きなジャンルの本を読むだけではなく、時には、違ったジャンルの本にも挑戦してみてはどうでしょうか。
皆既月食を観察しよう
10月8日(水)の夜は、満月が地球の影にすっぽり入り、赤黒い「赤銅色」となる皆既月食が起こります。気象条件もよさそうなので、家族で、この珍しい天体ショーを見てみませんか。月が欠け始めてから満月に戻るまで3時間あまり、完全に地球の影に覆われるのが午後7~8時台となるので、夕食後、東南の空を見上げてごらんなさい。双眼鏡や天体望遠鏡を使うと、皆既食となった月のそばに、普段は探すのが難しい「天王星」を見ることができるチャンスも重なります。日本で広く観察できる皆既月食は2011年12月以来のことだそうです。【2014.10.4千葉日報より】
皆既月食は、下の図のような仕組みで起こります。【国立天文台 天文情報センター資料より】

もっと詳しく知りたい人は、インターネットで検索してみるといいですね。ちなみに、下のアドレスにアクセスすると、月のことだけではなく、宇宙のことがいろいろと分かります。
宇宙科学研究所キッズサイト「宇宙ワクワク大図鑑」
http://www.kids.isas.jaxa.jp/zukan/index.html
実りの秋・読書の秋・食欲の秋
1日の市内陸上大会では、練習の成果を発揮し、総合5位という立派な成績でした。肌寒い中、緊張した面持ちで出番を待ち、一人一人が、真剣に競技に取り組む姿に感心しました。また、6年生全員で応援に行きましたが、参観の態度もよく、一生懸命応援する様子は、正面の校長席で見ていた私の眼には、市内の学校の中で一番よかったように映りました。9月の修学旅行も含め、高野山小学校の6年生は、とても誇らしい最高学年として成長しています。残り半年を、さらに実り多いものとして過ごし、卒業の日を迎えられることを期待しています。
高野山小学校には、陸上部や吹奏楽部・合唱部の特設クラブがありますが、10月から
「奉仕活動部」を新設しました。この特設クラブの設立については、1学期から児童会を通して子ども達に「母校高野山を少しでもきれいな学校にするために活動する仲間を募ろう」と呼びかけ、活動内容や名称を検討してきました。活動できるのは、他の部活動同様、4年生以上です。しばらくの間は、落ち葉掃きや教頭先生の手伝いをしますが、部員で相談して、主体的な活動ができる、実りあるクラブに成長させていきたいと考えています。保護者や地域の方のご協力も大歓迎です。
毎週、金曜日の8:20から8:40は「読書タイム」を設定しています。「読書タイム」の時間は、学校全体で静かに読書をしています。ボランティアの方に読み聞かせをしてもらうこともあります。子ども達は、本が大好きです。家庭でも時間を決めて、家族みんなで読書なんて、素敵な過ごし方をしてみませんか。
私は、以前、学校を離れて、教育委員会や博物館、科学技術振興機構と言うところで仕事をしていました。その時は、ほとんど外食でした。好きなものを食べられる良さはありますが、毎日となると案外飽きてしまうものです。しかし、給食は、毎日食べても飽きることはありません。いつもご馳走というわけではないのに不思議です。メニューが豊富、手作り、温かいうちに食べられる・・・。しかも、カロリーや栄養のバランスが専門的に考えられています。私は、子ども達が食べる前に、確認をする「検食」を毎日行います。「異臭はないか」「加熱は十分か」・・・等、何項目かのチェックをし、安全性を確かめてから、子ども達に給食を提供しています。よく考えられたメニューに感心することもしばしば、栄養士さんに作り方を教えてもらうこともあります。毎日の給食は、学校のホームページに掲載しています。時々、給食だよりでもレシピをお知らせしています。旬の食材を使ったメニューが多いので、参考にしてはいかがでしょうか。
「教育振興基金」をご存じですか? 我孫子市では、平成25年4月1日に条例を制定し、寄付金を募っています。この基金を積み立て、子ども達が使う楽器や運動用具の購入・教育環境の整備に役立てます。子ども達の教育活動がさらに充実し、実りあるものになるように、ご協力いただければ嬉しく思います。
2学期をむかえて
私の実家のある広島市では、豪雨による土砂崩れで、多くの犠牲者が出てしまいました。そこでは、2学期の始まりを楽しみにしていた小学生も尊い命を失い、その地区にある梅林小学校は、避難所として多くの被災者を収容しています。いつものように始業式を行うことができた高野山小学校の子ども達は、本当に幸せだと痛感しています。
さて、私が始業式で子どもたちに話したことは、
一つに、「進んで挨拶をしよう」ということです。高野山小学校の児童は、とても明るく元気です。挨拶もよくしていますが、誰に対しても進んで元気な挨拶ができることを期待しています。
二つ目に、「新しいことにも挑戦していこう」ということです。これは、私自身もぜひ挑戦してみたいことでもあります。しかし、私一人ではできないので、全校で取り組んで行きたいと思っています。まず最初に、「高野山漢字検定」の実施です。漢字が得意な児童もいれば、そうでない児童もいるとは思いますが、私が作る検定問題に、学年に関係なく挑戦してほしいと考えています。始業式の後で、「校長先生、計算検定はやらないの」と言ってくる児童もいました。いずれは、「計算検定」もしていきたいと思いますが、まずは「漢字検定」を実施して、児童の様子をみたいと考えています。期待通りの「高野山検定」になるようご協力ください。
三つ目は、来年中学校へ進学する6年生に「教科担任制」を行うことを話しました。中学校では、教科ごとに教わる先生が違います。少しでも、そのシステムに馴染むように、6年生の担任が一部の教科を交代して教えることにしました。どの先生に教わっても、一生懸命取り組めることを願っています。そのためには、先生方も教え方を工夫していきますので、ご期待下さい。
最後に話したのは、「あびっ子」設置のことです。「あびっ子」とは、放課後、子ども達が安全にすごせる場所のことで、一小をはじめ、多くの学校に設置されています。高野山小学校でも設置を希望する声が多く、1日でも早い実現が待たれています。やっと設置のめどがついて、来年9月開設を目指して準備が進められていることを、我孫子市長から直接伺いました。先日、子ども支援課や教育委員会の担当者とも打ち合わせを行いました。
このように、高野山小学校は、日々進化しています。「なかよく 進んで 元気よく」の合言葉のように、高野山小学校の良さをさらに伸ばし、魅力のある高野山小学校になるように、努力していきたいと思います。