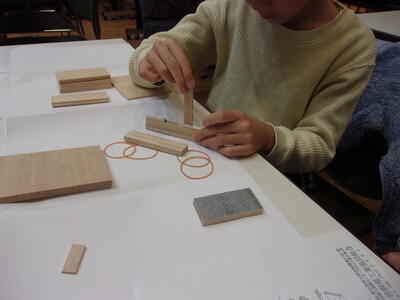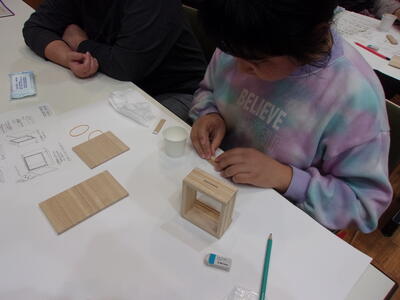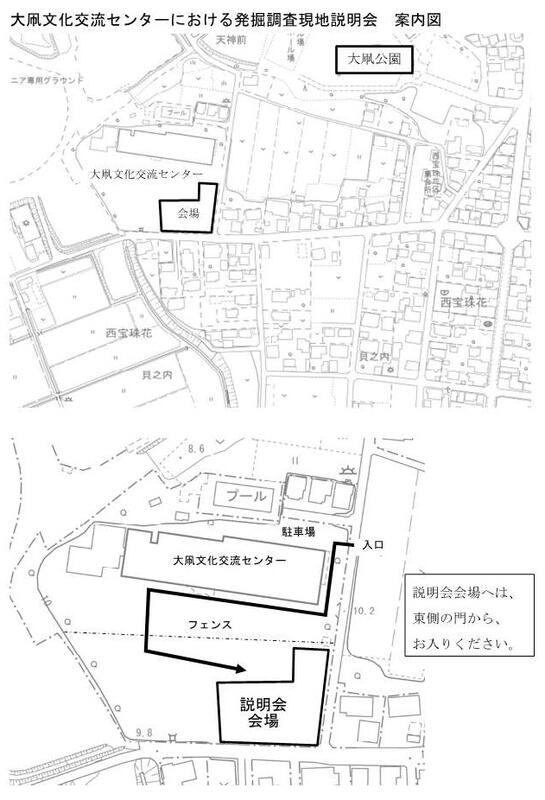文字
背景
行間
- 「文字の大きさ」については、画面右上のボタンから「大・中・小」が選択できますので、お好みのものをご利用ください。「背景色」、「行間」も調整可能です。
- 春日部市郷土資料館利用のご案内
- 春日部市郷土資料館収蔵資料データベース
- 古文書解読勉強会の成果はこちらです
その1 その2 その3 その4 その5 その6 その7 その8 その9 その10 その11 その12 その13 その14 - 日光道中粕壁宿「歩いてみよう道しるべ」ホームページ版解説を掲載しています
- 収蔵資料・館蔵の古写真を紹介しています
【小学校の先生へ】小学校地域学習「昔の道具」(学習リーフレット)をご活用ください
【休館日】(年末年始、毎週月曜日、祝日、月曜日が祝日の場合はその翌日、施設点検日等)
<令和7年~8年ーこのほか施設点検日等が休館になりますのでご注意ください>
- 4月の休館日 7日(月曜日)、14日(月曜日)、21日(月曜日)、28日(月曜日)、29日(火曜日・祝日)
- 5月の休館日 3日(土曜日・祝日)、4日(日曜日・祝)、5日(月曜日・祝日)、6日(火曜日・振替休日)、12日(月曜日)、19日(月曜日)、26日(月曜日)
- 6月の休館日 2日(月曜日)、9日(月曜日)、14日(土曜日・施設点検日)、16日(月曜日)、23日(月曜日)、30日(月曜日)
- 7月の休館日 7日(月曜日)、14日(月曜日)、19日午後(土曜日・選挙)、20日(日曜日・選挙)21日(月曜日・祝日)、22日(火曜日・祝日の翌日)、28日(月曜日)
- 8月の休館日 4日(月曜日)、11日(月曜日・祝日)、12日(火曜日・祝日の翌日)、18日(月曜日)、25日(月曜日)
- 9月の休館日 1日(月曜日)、8日(月曜日)、13日(土曜日)~16日(火曜日・館内燻蒸予定)、22日(月曜日・祝)、23日(火曜日・祝日)、29日(月曜日)
- 10月の休館日 6日(月曜日)、13日(月曜日・祝日)、14日(火曜日・祝日の翌日)、20日(月曜日)、25日午後(土曜日・選挙)、26日(日曜日・選挙)、27日(月曜日)
- 11月の休館日 3日(月曜日・祝日)、4日(月曜日・祝日の翌日)、10日(月曜日)、17日(月曜日)、23日(日曜日・祝日)、24日(月曜日)
- 12月の休館日 1日(月曜日)、8日(月曜日)、13日(土曜日・施設点検日)、15日(月曜日)、22日(月曜日)、29~31日
<令和8年>
- 1月の休館日 1~3日、5日(月曜日)、12日(月曜日・祝日)、13日(火曜日・祝日の翌日)、19日(月曜日)、26日(月曜日)
- 2月の休館日 2日(月曜日)、9日(月曜日)、16日(月曜日)、23日(月曜日・祝日)、24日(火曜日・祝日の翌日)
- 3月の休館日 2日(月曜日)、9日(月曜日)、16日(月曜日)、20日(金曜日・祝日)、23日(月曜日)、30日(月曜日)
ほごログ
【臨時休館のお知らせ】
令和7年12月13日(土)は教育センターの施設点検のため、郷土資料館は休館となります。
ご迷惑をおかけしますが、ご注意ください。
12月14日(日)は通常通り開館します。
11月30日、体験講座「桐の貯金箱づくり」を実施しました
11月30日、春日部桐箱工業協同組合の皆様にご指導いただき、桐の貯金箱づくりを実施しました。
この講座は、令和3年の企画展「語り出したらキリがない 桐のまち春日部」展の関連イベント以来、毎年開催しているものです。今年は、大人の方の参加も多く、皆さん楽しみにしてご参加いただきました。普段は、桐箱製造にお忙しい、市内の業者さんたちは、今日は講師となり、やさしく丁寧に指導されていました。
桐の貯金箱づくりは、オリジナルキットを組み立ててつくります。
アンケートでは、ボンド付けが難しかったと答える方が多かったです。
ボンドがはみ出たり、形が曲がったりしたら、格好が悪い箱になってしまいます。職人さんたちは、はみ出たボンドをきれいに拭き取って、板が曲がらないように輪ゴムで圧着させながら、組み立てるよう、一人一人丁寧に指導されていましたト。春日部の桐箱づくりの「わざ」が垣間見られた瞬間でした。
さらに、ミゾが入っている小さな板を組み合わせ、お金を出し入れできる、スライド式のフタのからくりも作ります。これも桐箱づくりの「わざ」の一つ。素人の手作りではできない細工です。
そして、オリジナルはココ。背板を自由にデザインし、電ノコで型を切り抜きます。
上の方は、見本のコバトンのイラストを重ねて写していました。今年は、ウサギやキツネ、マインクラフト、そして相変わらずポケモンのイラストを描いている方がいました。
型抜きは、職人さんがやります。
毎年恒例ながら、自分の作品が職人さんの手によって切り抜かれるのを、子どもたちは羨望のまなざしでみていました。参加された大人の方は、自分で電ノコを扱えると思っていたらしく、少し残念そうでした。
背板や残りの部品を組み立てて、ヤスリがけしたら一先ず完成。
丁寧にヤスリがけをして、色を塗ったり、紙やシールを貼ったりすれば、本当にオリジナルな貯金箱のできあがりです(時間の関係上、ご自宅で作業いただきます)。
インフルエンザが流行っていたためか、直前にキャンセルされる方も多く残念。大変好評なイベントなので、来年も開催する予定です。参加が叶わなかったかたも、別のデザインの貯金箱を作りたい方も、ぜひご参加ください。
最後に告知。12月23日(火)、24日(水)には、市役所の「まちなかひろば」にて桐箱と押絵羽子板の特産品まつりが開催されます。丁寧につくられた春日部の桐箱を手に取って、リーズナブルに手に入れることができますので、ぜひお立ち寄りください。
11月の考古学関係展示会、イベント情報
近隣博物館・資料館の考古学情報をお届けします。
(毎月28日ごろに掲載します。随時、情報を更新します。)
(春日部市発掘調査現地説明会)
・12月12日(金曜日)13時30分から14時30分 貝の内遺跡発掘調査現地説明会(申込不要)
場所:春日部市西宝珠花593:大凧文化交流センターハルカイト内)
*駐車場あり(施設内満車の場合は大凧公園へ)
春日部駅東口より関宿中央ターミナル行き朝日バス「大凧公園入口」下車徒歩6分
バス時刻 12:46発→13:15着 12:58発→13:30着 13:21発→13:50着 13:32発→14:01着
(東部地区文化財担当者会リレー展示ー都鳥が見た古代)
・12月6日(土曜日)~12月21日(日曜日)
行田市教育文化センターみらい(行田市・パネル展示)
(展示会_閉会日順)
・12月8日(月曜日)まで 羽生市役所
「永明寺古墳県指定10周年記念パネル展」 主催:羽生市教育委員会
*以下巡回します
1月17日(土曜日)~2月16日(月曜日)村君公民館
3月7日(土曜日)~5月6日(水曜日)羽生市立郷土資料館
・11月30日(日曜日)まで 上高津貝塚ふるさと歴史の広場(考古資料館)(茨城県土浦市)
上高津貝塚ふるさと歴史の広場開館30周年記念第28回企画展「文字が語るもの」
・11月30日(日曜日)まで 白岡市立歴史資料館(白岡市)
第8回企画展「感じて!縄文土器のぬくもり~掘り起こされた白岡遺産~」
・12月5日(金曜日)まで 富士見市立中央図書館(富士見市) 主催:富士見市教育委員会
「氷川前遺跡出土の銅鋺展示~古代のムラから姿をあらわした祈りの器~」
・12月7日(日曜日)まで さいたま市立浦和博物館(さいたま市緑区)
企画展「注目!縄文土器~注口土器」
・12月7日(日曜日)まで 武蔵国分寺跡資料館(東京都国分寺市)
令和7年度秋期企画展「発掘された国分寺市2025」
・12月28日(日曜日)まで 船橋市飛ノ台史跡公園博物館(千葉県船橋市)
「ふなばしを掘る 発掘速報展」
・1月12日(月曜日・祝日)まで 難波田城資料館(富士見市)
「日常使いの近代『セトモノ』展~蔵に眠っていた食器~」
・1月25日(日曜日)まで 藤岡歴史館(群馬県藤岡市)
秋季企画展「再発見!時代を創った古代藤岡のモノづくり -発掘された日本列島2018・2024を振り返る-」
・1月25日(日曜日)まで 岩槻郷土資料館(さいたま市岩槻区)
企画展「さいたま市の土偶たち」
・2月15日(日曜日)まで 下野市立しもつけ風土記の丘資料館(栃木県下野市)
企画展「下野市内の遺跡IV 律令国家の転換と『下野国』古代の制度改革~人がいない・予算がない~」
・3月1日(日曜日)まで 千葉市立加曽利博物館(千葉県千葉市若葉区)
令和7年度企画展示「加曽利B式展ー加曽利の名を持つもう一つの土器ー」
・5月17日(日曜日)まで 群馬県埋蔵文化財調査センター(群馬県渋川市)
令和7年度最新情報展第2期「縄文土器がつくられはじめた頃ーみどり市下谷戸B遺跡の発掘調査から」
(講演会)
・1月18日(日曜日)明治大学駿河台キャンパスアカデミーコモン3階アカデミーホール
主催:明治大学日本古代学研究所(インターネットから申込み)
学術講演会「ヤマト王権と佐紀古墳群」
・2月7日(土曜日)埼玉会館小ホール(さいたま市浦和区)
主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月4日からホームページから申込み)
令和7年度東京・神奈川・埼玉埋蔵文化財関係財団普及連携事業公開セミナー
「弥生時代が終わるころ~ムラのカタチとヒト・モノの流れ~」
(現地説明会)
・12月6日(土曜日) 国指定史跡真福寺貝塚 現地見学会(さいたま市岩槻区)
主催:さいたま市教育委員会(申込不要)
午前の部:10時から11時30分、午後の部:13時30分から15時
・12月14日(日曜日)宅地遺跡遺跡見学会(行田市)
主催:埼玉県埋蔵文化財調査事業団(11月25日よりホームページから申込み)
【手作りおもちゃクラブ】BB弾転がしを作ろう!
12月7日(日)に“手作りおもちゃクラブ”を開催します。
今回作るおもちゃは「BB弾転がし」です。
昨年度から作り始めた準新作のおもちゃです!
郷土資料館の昔のおもちゃコーナーにある「ビー玉転がし」をコンパクトにし、短時間で作りやすく設計したものになります。
しかし、小さいから簡単かと言えばそうでもありません。
よかったら以下の動画をご覧ください。
BB弾がよ~く転がるため、僅かな傾きでも勢いよくすすんでしまい、コントロールが実に難しい!集中力と繊細な動作が求められます!
自作のコースを作ったりしても面白いと思いますよ♪まずは、今回参加して作り方を教わってみてください!
手作りおもちゃクラブはお申込不要、おもちゃの材料も資料館で用意しています。
当日の午前10時30分と午後2時からの計2回開催しますので、お時間までに郷土資料館にお越しください!
【手作りおもちゃクラブ】
日時:令和7年12月7日(日)午前10時30分~・午後2時~
場所:春日部市郷土資料館(春日部市粕壁東3-2-15)
内容:蓄音機と紙芝居の上演
おもちゃづくり(BB弾転がし)
費用:無料
申込:不要(開催時間までに郷土資料館にお越しください)
12月12日(金)にハルカイトにて発掘調査現地説明会を開催します
令和7年8月から、大凧文化交流センター(ハルカイト)駐車場造成予定地において、貝の内(かいのうち)遺跡29次地点の発掘調査を実施しています。
つきましては、調査の成果を市民の皆さまへお知らせしたく、下記日程で現地説明会を開催しますので、お気軽にご来場ください。
1 日 時 令和7年12月12日(金)午後1時30分~午後2時30分
※小雨決行 荒天の場合は中止
2 場 所 春日部市西宝珠花593 大凧文化交流センター(ハルカイト) 多目的広場
※下記の地図をご覧ください。
3 問い合わせ 春日部市教育委員会文化財課 048-739-6811
※事前申し込みは不要です
大凧文化交流センター「ハルカイト」公式ホームページ
https://www.city.kasukabe.lg.jp/soshikikarasagasu/kankoshinkoka/gyomuannai/7/1/1/2/25209.html
▲古代の住居跡