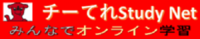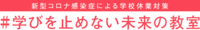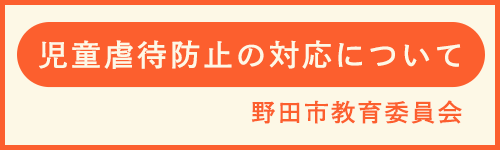学校の様子
5年生 理科 ~ふりこの実験・ラスト
5年生は、理科の学習でふりこの実験その3に取り組んでいました。その1では「ふりこが往復する時間は、ふりこの振れ幅を変えても同じ」ことが、わかりました。その2では、「ふりこが往復する時間は、ふりこの重さ(おもりの重さ)が変わっても同じ」ことがわかりました。今日は、その3(最終)で「ふりこの長さを変えたら・・・どうなるだろうか」でしたが、どのグループも実験は成功し「ふりこの長さが長いと往復する時間は長くなり(動きがゆっくりになり)、短いと往復する時間は短くなる(早く動く)」ことを確かめることができました。
前回も書いた通り、今回は川口市科学館で見て知っていることを確かめる実験だったので、「予想」もみんないっちしていましたが、これからも「自分で予想したことを確かめる」ために行う実験の学習を大切にしてください。
1・2年生 折り紙教室
昨年度に吹き続き、折り紙名人!の菅沼先生を講師に迎えて、1・2年生が折り紙教室を行いました。
ありがとうの会で6年生にプレゼントする分と、自分で持って帰る分で、1年生はチューリップ、2年生はシマオナガの作品作りに挑戦しました。さすが、図工大好き、折り紙大好きの1・2年生です。菅沼先生のご指導を直ぐに理解し、器用に指を動かして作品を完成させることができました。校長先生より上手な人もいたような…すごい!!
菅沼先生からは、学校に(羽根がスライド式になっていて伸びる)「紅白の鶴」をいただきました。全校の児童に見てもらおうと思い、けやきルーム前に展示しました。菅沼先生、ありがとうございました。
4~6年生 箏体験教室
5校時と6校時に分けて、4~6年生が「野田現代邦楽アンサンブル」より3名の講師を迎えて「箏体験」に挑戦しました。日本の伝統楽器である箏をより身近に感じ、興味関心を高められるよう、実技指導を中心にとても熱心な指導をしていきました。箏独特の音色による「さくら さくら」は、聞いたことがない児童が一人もおらず、とても親しみやすかったです。また、大規模校では「6年生だけの体験」がほとんどですが、福二小は4年生から実施しているので、今回が3回目という児童もいて、講師の方も上達ぶりに感心していました。
講師を務めて下さった「野田現代邦楽アンサンブル」の皆様、ありがとうございました。
因みに「箏」と「琴」、どちらも「こと」と呼び,日本の伝統的弦楽器ですが、違う楽器です。「箏」は、可動式の琴柱(ことじ)を立てて音を決め、琴爪をつけて演奏するのが「箏」、左手で弦の長さを区切って音を決め、右手の指で弦を弾くのが「琴」なのだそうです。琴柱を設定してあれば、初心者でも弾きやすいということで、今回は「箏」の体験をしています。
全校なわとび記録会
業間~4校時にかけて、「全校なわとび記録会」を開催しました。短い練習期間だったかもしれませんが、短なわも長なわとびも、最初の頃とは見違えるほど上手になった児童がたくさんいました。
外部の方への対応で、途中から子どもたちががんばる様子を見ることができず、とても残念でしたが、「がんばりました」「目標が達成できました」と何人もの子どもたちから嬉しい報告をもらいました。お疲れ様、よくがんばったね。
4~6年生 防災教室 ~マイ・タイムラインを作ろう
野田市防災安全課の職員の方を講師に迎え、4~6年生が防災教室を行いました。今回は、台風で河川が氾濫し、水害が起きた時の避難行動について学びました。
初めに、防災の知識としてスライドを見せながら、水害とはどういう災害か、水害時の避難情報・防災情報について、情報の受信について、避難のタイミングと非難の仕方について、洪水ハザードマップについて 等を学んだ後に、マイ・タイムライン(いつ・どこに・どのように避難するか一人一人があらかじめ決めておく「農済活動計画」)を作成しました。福田二小が避難所となったばあい、水害での被害は基本的にないのですが学区外から通っている場合、近くにある避難所に指定されている学校は、水害被害が起こる可能性があります。
子どもたちには、少し難しい内容でしたが「自分や自分の家族の命を守る行動」はとても大切なことです。ハザードマップ、マイ・タイムラインの作り方、授業用ワークシートではない「しっかりとしたマイ・タイムライン用紙」を持ち帰っているはずなので、機会を作ってぜひ作成してみてください。
今から5年前、台風の影響で利根川・江戸川に氾濫の恐れが生じたとき、避難所に指定された川間小学校体育館と途中から垂直避難での3階教室に連泊した懐かしい思い出…(当時は教頭でした)