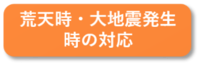校長室から
″体育館耐震工事″順調です!
平成26年1月20日完了予定の体育館の耐震工事ですが、全体の70%程を終え、ほぼ予定通りの進捗状況です。過日星野市長さんや倉部教育長さんが視察に来ていただいたときも説明を受けましたが、細かな所は実際に見てみないとわからないので、泉教頭と2人で確認に行きました。床板はまだ張り替えていませんが、照明を付け替えたり、柵や補強したところを塗っただけでも明るくなったような気がしました。できあがるのが楽しみになります。
市教委総務課のみなさんをはじめ市役所総務部の担当の方や鈴木建築設計事務所のみなさん、立沢建設のみなさん、一條電気工業のみなさん等、本当に多くの方々の手によって、湖北中体育館を安心安全できれいな体育館に再生させていただいております。心より感謝です。本当にありがとうございます。
子ども達の明るい声が響き渡るのも間もなくです。3年生が卒業するまでに一日でも多く使用させてあげたいと思います。
天井照明の寿命は9万時間も!? 床板の張り替えはこれから!
新しいトイレは広い! 工事初期、黄色の外壁も今は…!
ほのぼのバザー!
2日(土)曇り空の中、バザーが盛大に行われました。
卒業生歌手の三令さんのミニキャンペーンや科学部、吹奏楽部の発表等もあり、参加者みんなで盛り上がりました。
体育館の耐震工事の関係で例年のような体育館での発表ができず、その代わり、屋外ステージでの発表となりました。科学部の実験発表は、シャボン玉に熱気球、ペットボトルロケットと屋外でしかできない内容でとても楽しく見ることができました。吹奏楽部の発表も歌あり、踊りありの楽しい演奏会になりました。「あまちゃん」のテーマ曲も地域の皆さんには好評でした。
生徒会とPTAがコラボして行った大抽選会も盛り上がりました。事前準備から本番までPTA役員の皆さんやPTAのOBの皆さん、本当にありがとうございました。とてもほのぼのとした楽しい時間が共有できました。
屋外での生徒会引き継ぎ式 卒業生歌手 三令さん
サイン会 豚汁コーナー
科学部 熱気球 吹奏楽部ミニミニコンサート
星野市長、倉部教育長視察
体育館の耐震工事の進捗状況や授業の様子を視察されました。
星野市長は午前中2,3年生の授業を参観した後、2年3組のみんなと楽しく会食していただきました。
どの教室も真剣に授業に取り組む様子が見られました。
全員が「できた・わかった」と言える授業づくり、それには、わからなかったりできなかったりしたときに、「教えて!」「いいよ!」という聴き合う関係を学級の中に作らなければなりません。学習課題を解決する授業を作らなければなりません。先生から一方的に教わるだけで、静かに黒板を写すだけの学習では本当に身につけたい力がついてこないのです。湖北中の授業をそういう授業に作り替えていきたいのです。
わからないことがわかるようになる、できなかったことができるようになる、勉強は本当に楽しい学びです!
授業中に「先生!俺わかるようになってきた!」と、3年生が、とてもいい表情で伝えてくれました。聞いた私も嬉しくなりました。
そうなんです!「学び」は楽しいのです!


【英語の授業風景】 【理科の実験(イカの解剖)】

【家庭科の授業(小物入れ製作)】
紛争と人間~人間を救うのは、人間だ。~
台風が少しそれて通過したお陰で、雨も小降りになったので、表参道を散策しながら会場に向かいました。
NHKが主催するシンポジュウムで、12月7日(土)14:00からその模様がNHK教育テレビで放送されます。お時間がある人は是非ご覧ください。
解説員の方の上手な進行と三人のパネリストの現場のお話しに時間が経つのも忘れ、2時間半があっという間に終わりました。
最初に3つの質問が会場に投げかけられました。
①「紛争に携わった経験がある人は?」
②「100年後、世界から紛争がなくなっていると思う人は?」
③「将来日本は、何らかの紛争に巻き込まれると思いますか?」
皆さんはYes、Noのどちらですか?

【↓ここをクリック↓】
21「人間を救うのは、人間だ」.pdf
3クラスが「残菜・残乳ゼロ」!
今日の帰りの会で「9月の残菜、残乳ゼロ」の学級を表彰してきました。
2年3組、4組、5組の3クラスは、先月17回の給食を一度も残さず食べました。特に2年3組は4月からずっと残菜ゼロを続けています!スゴイ!
湖北中の「残菜ゼロ運動」は、自校式の学校給食が始まるときに、昔PTAの会長を務めていた真栄寺の馬場和尚さんが、本校で講演会を行ったのがきっかけで始まりました。今では市内の多くの小中学校が、毎月0の付く日(10日、20日、30日)を「残菜ゼロの日」と定めて活動してるようです。湖北中学校は我孫子市内の「残菜ゼロ運動」発祥の学校だと思っています。
また、東日本大震災の際に避難所のニュースが流れた後、それまで残菜のあった学級が、食べられることの幸せを感じ、卒業まで「残菜ゼロ」を続けたということもありました。
「命」を「いただきます!」という気持ちを忘れず、これからも「残菜ゼロ運動」が続くように取り組んでいきたいと思います。