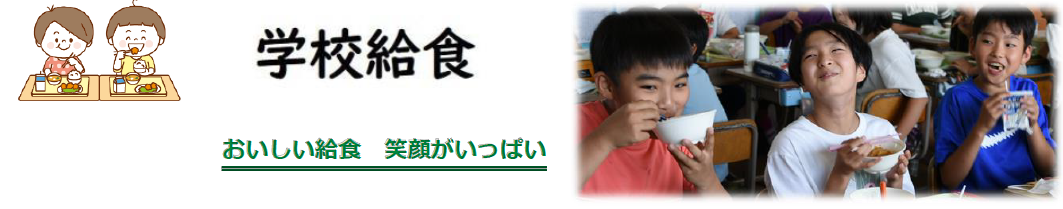学校給食ブログ
12月5日(金)給食センターの献立
・こどもパン
・牛乳
・チーズオムレツ
・キャベツのサラダ
・ポークビーンズ
12月4日(木)給食センターの献立
・ごはん
・牛乳
・あじのみそだれ
・炒めなます
・吉野汁
12月3日(水)給食センターの献立
・チキンハヤシライス(麦ごはん・ルウ)
・牛乳
・ほうれん草のソテー
12月2日(火)給食センターの献立
・みそラーメン(中華めん、スープ)
・牛乳
・揚げぎょうざ(小2個/中3個)
・茎わかめ入りサラダ
12月1日(月)給食センターの献立
・ごはん
・牛乳
・ぶた肉のカルビソース
・もやしのナムル
・トック入りだいこんスープ