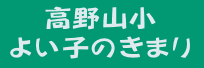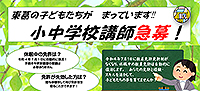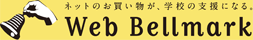校長室から
あたたかい心の貯金
校長 金子 博之
高野山小学校の児童は、優しい子ばかりですが、今月は「ちくちく言葉」と「ふわふわ言葉」のお話をしたいと思います。
「ちくちく言葉」は、傷つく、悲しい、いやな言葉です。逆に「ふわふわ言葉」は、うれしい、優しい言葉です。「ふわふわ言葉」には、子どもたちが互いにつながり、楽しく安心して学校生活が送れるよう、相手のことを思いやる「言葉」を大切にして欲しいという願いが込められています。
人の心の中には生まれながらにして「あたたかい心の貯金」があると言われています。人からほめられたとき、話をしっかり聞いてもらったとき、「ありがとう」「いいよ」「いっしょにやろう」「がんばったね」「あなたのせいじゃないよ」と、思いやりが伝わる「ふわふわ言葉」を言われた時などにあたたかい心の貯金が貯まっていきます。あたたかい心の貯金とは、心の余裕です。心に余裕が生まれると、自然に家族や友だちに優しくなり、周りとのコミュニケーションが上手にとれるようになります。あたたかい心の貯金の残高が多ければ多いほど自分を大切だと思える自己肯定感、やる気、自信が増えてきます。
反対にあたたかい心の貯金が貯まっていない子は、周囲に対して心がささくれ立ち、反抗的な態度をとったり、家族や友だちとうまく接することが難しくなってしまうことがあります。また、自分はだめな子だと自己評価を低くし、自信が持てなくなり、周囲とのコミュニケーションがうまくとれなくなってしまう場合も出てきます。
子ども同士だけでなく、大人と子どもの関係も同じです。ほめれば貯金が増え、けなせば貯金が減っていきます。子ども一人一人の個性を受け止め、温かく見守り、プラスの声かけをしていくことは、私たち子どもの周りにいる大人の大切な役割の一つであり、常日頃から気をつけなければいけないと感じています。
「ふわふわ言葉」があふれる学校・家庭でありたいものです。
今月もどうぞ、よろしくお願いいたします。
いじめはゆるさない
10月27日の新聞で「千葉県内の小中高校・特別支援学校が2016年度に把握したいじめが3万件を超え、3年連続で全国最多となった」と報じていました。
いじめは決して許されるものではありません。本校でも年に数回児童に「いじめアンケート」を実施し、日々の観察と共にその把握につとめています。今年度は1回目のアンケートを6月に実施しました。その結果を見ますと「あなたは今、いじめられていますか」という問いに対し、20人の児童が「はい」と答えています。内訳は低学年が15人、中学年が3人、高学年が2人となっています。直ちに事実確認を行い、重大事案に該当するものはないことを確認しました。いじめにはあたらないものもありましたが、指導が必要な件では該当児童並びに保護者にも事実を伝え、家庭の理解と協力を求めています。
いじめはどこの学級でも起こりうると考えています。1学期の全校朝礼でも「けんかといじめの違い」について、児童に話しました。「けんか」は対等な関係であるのに対し、「いじめ」は上下の関係・強者と弱者の関係があるといった話をしました。児童は、いじめはいけないことだとわかっていますが、具体的にどういう行動がいじめにあたるのか、分かっていない場合があります。
高野山小学校では「いじめ防止基本方針」に則り、いじめや人権侵害などについて次のように取り組んでいきます。
① 児童に「いじめはしない、されたらすぐに先生やお父さんお母さんに相談する、している人を見たら先生やお父さんお母さんにすぐに知らせる。」
② 教師は、友だち同士の接し方についての指導や分かる授業づくりを行う。
③ 学校は、児童・保護者・地域からの情報に即対応する。
学校は、いじめられている児童を学校組織として全教職員で守ります。何かありましたら、少しでも気になることがありましたら、連絡をお願いいたします。
(高野山小学校いじめ防止基本方針は、ホームページで公開しています)
11月の全校朝礼では、「何でもそうだんポスト」が校長室前に設置されているので、どんな些細なことでも相談して欲しいと話しました。
今月も、どうぞよろしくお願いいたします。
いいことをする子がいっぱい
あいさつは、人と人のかかわりを潤いのあるものにします。今月の全校朝礼では、「すてきなあいさつ」ができるように校長先生と三つの約束をして欲しいと話しました。ただ話しても子どもたちはすぐに忘れてしまいますので、記憶に残るようにと、日頃からすてきなあいさつを実践している、6年生の児童3人にも協力してもらいながら話しました。
「6年1組の近藤さん、おはようございます。」「校長先生、おはようございます。」「近藤さんはにこにこ笑顔で校長先生にあいさつをしていました。」
すてきなあいさつの一つ目は・・・・・『にこにこ』です。
「6年3組の木村さん、おはようございます。」「校長先生、おはようございます。」「木村さんはにこにこ笑顔はもちろんですが、校長先生の目を見て、しっかりあいさつしていました。」
すてきなあいさつの二つ目は・・・・・『目を見て』です。
「次は6年2組の久保田さんにやってもらいましょう。」
「校長先生、おはようございます。」「久保田さん、おはようございます。」「久保田さんは、前の二人と違うところがありました。分かりますか?」
「そうです、校長先生よりも先にあいさつしていましたね。」
すてきなあいさつの三つ目は・・・・・『先に』です。
『にこにこ』『目を見て』『先に』そんなすてきなあいさつのあふれる高野山小学校にしましょう。と話しました。
高野山小学校には、あいさつだけではなくとってもすてきな行いをする子どもがいっぱいいます。
落とした鉛筆が手元に戻ってきました。拾って届けてくれた子がいます。そして「ありがとう」とお礼を言った子がいます。
落ちていた靴を、名前を見てその子の靴箱に入れてくれた子がいます。
雨の中、傘を差し、赤ちゃんをだっこして、水筒を届けに学校までいこうとしていたおかあさんに、「ぼくが届けましょうか?」と声をかけ、水筒を預かってくれた子がいます。・・・
子どもたちがこのように育っているのは、保護者のみなさまや地域のみなさまの応援のおかげです。本当にありがとうございます。
今月もどうぞよろしくお願いいたします。
実り多い2学期に
高野山小学校に子どもたちの元気な声と活気が戻ってきました。どの子の顔もやる気満々といった表情でとても頼もしい限りです。
保護者のみなさまには、様々な場面でご支援・ご協力をいただきました。
地区委員のみなさまにはパトロールをしていただきました。
バレーボール部のみなさまには7月と8月の大会に参加をしていただき、大健闘をしていただきました。
更には、ボランティアとして教室のカーテンを洗濯していただいたり、校庭の花壇の水やりにもご協力をいただきました。本当にありがとうございました。
学校ですが1学期末に転出があったり、夏休み中に転入があったりした関係で、9月1日現在児童数649名で2学期をスタートしました。42日間、家庭と自分自身のペースで過ごしてきましたので、学校の生活リズムに乗るまで少し時間がかかりそうです。子どもたち一人一人にきめ細かく関わることを基本に、2学期も教職員一同心と力を合わせてまいります。保護者のみなさま、地域のみなさまよろしくお願いいたします。
さて、学校は先述の通り、保護者のみなさまや地域のみなさまのご協力をいただきながら、どの子も学習などに自信を持ち、友達と協調、協力していけるよう社会性や思いやり・親切といった心情の育成に努めております。子ども時代は、大人になるための単なる準備期間だけではありません。子どもは、今という瞬間を楽しく精一杯生き、生きがいを持ち、明日へよりよいものを求め、将来への夢を抱き、その実現に前向きに進む存在であると思います。子どもに、今日という楽しさや充実があってこそ、何ごとにも意欲的になるのではないでしょうか。家族の愛情と心のこもった食事、公平で温かい教職員の指導、思いやりのある友達の存在、それら全てを見守ってくださる地域の目、その全てが子どもにとっての成長の土台だと思っています。
2学期もご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。
すべては子どもたちのために
すべては子どもたちのために
校長 金子 博之
少なくとも私が教師になった30数年前までは、学校は安全で安心できるところだと、教職員はもちろんのこと、保護者の方々も地域の方々も社会全体が信じて疑いませんでした。事実そのように安全でした。
しかし残念なことに、日本社会の急激な規範意識の希薄化、日常生活のルールやモラルの欠如、知恵を絞って人をだましたりごまかしたりなど不正をなりわいとする人々の出現、子どもをターゲットにしてまさに食い物にする大人達の出現は、結果として子どもたちにとって危険な社会を生み出してしまいました。社会の浄化、大人のモラルの回復を叫ぶだけでは、子どもの安全は確保できません。日本人と日本に住む人の規範意識とモラルには、信頼するよりも、不信感を持って対処しなければならない事実が多すぎるように思われます。「知らない人と挨拶はしないようにしよう。」といった指導は、その典型です。
社会がだめになった、日本人がだめになった、地域環境が悪化した、他を責めているだけでは子ども達の安全な生活は保障できません。
学校・家庭・地域社会・警察などが連携し危機管理を徹底していくことが喫緊の課題です。その意味で、今回学校だよりと同時に発行された「地域安全懇談会通信」にある通り、高野山小学校PTAが中心となり、各種団体が一つにまとまっていくことの意義は、大変大きいと考えています。これをお読みになっていらっしゃる全ての人のお力をお貸しくださいますよう、改めてお願いいたします。ご理解とご協力をどうぞ、よろしくお願いいたします。