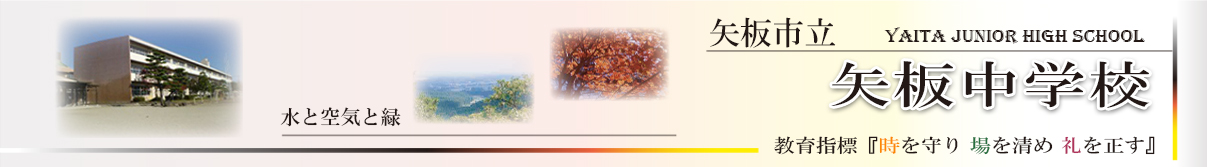給食のページ
12月4日の給食
今日の献立は、「ごはん さばのみそ煮 もやしとのりのあえもの 鶏肉入りけんちん汁 牛乳」でした。
もやしには疲労回復に効果的なアスパラギン酸や、美容や健康に良いとされるビタミンCなどの栄養が含まれています。主に緑豆もやし・ブラックマッペもやし・大豆もやしの3種類が生産されています。それぞれ特徴がありますが、給食では緑豆もやしを多く使います。もやしは価格が安定して味にくせがないので、様々な料理に活用されています。
12月3日の給食
今日の献立は、「ごはん ユーリンチー 中華あえ 春雨肉団子スープ 牛乳」でした。
ハムを使ったあえ物が出ました。ハムは豚のもも肉を塊のまま塩漬けにした加工食品です。ハムには、骨を抜いたボンレスハムや豚のロース肉を使ったロースハム、肩肉を使ったショルダーハムなどがあります。たんぱく質が多く、もともと保存食であるため簡単に食べることができます。ただし、塩分や脂質も多く含まれていますので、食べ過ぎには注意が必要です。
12月2日の給食
今日の献立は、「肉みそソーススパゲティ グリーンサラダ みかんクレープ 牛乳」でした。
今日は、みかんクレープが出ました。みかんには様々な品種がありますが、日本で主に食べられているみかんは温州みかんです。みかんは、ビタミンが豊富で体の調子を整える働きがあります。さらに皮をむいた後の白い筋にはフラボノイドが含まれており、血液をサラサラにする効果があるといわれています。
12月1日の給食
今日の献立は、「いか天丼 磯香あえ どさんこ汁 牛乳」でした。
冬はエネルギーが一番必要な時期になりますので、食事の量や質をよくして、スタミナをつける事が大切です。寒さに負けないためにも、日頃からしっかりと食事をとり元気に過ごしましょう。 またこの時期 は、インフルエンザやノロウイルスの食中毒も流行してきます。手に付着したウイルスは、目や鼻 、口の粘膜を通って、体内に侵入します。石鹸 でしっかり手を洗い食事をするようにしましょう。
11月28日の給食
今日の献立は、「食パン チョコクリーム ミートソースペンネ 野菜のポトフ フルーツゼリーあえ 牛乳」でした。
ポトフは、フランスの家庭料理の一つです。鍋に牛肉やソーセージ、大きく切ったにんじん、たまねぎ、セロリ、キャベツ、かぶなどの野菜類を入れ、塩や香辛料で味付けしたスープでじっくり煮込んだ料理で、具材とスープを別々に盛りけるのが本来の食べ方です。濾した煮汁は他の料理のブイヨンとしても利用されます。世界各国に似 たような料理があり、フランスでは、日本版ポトフとして「おでん」が紹介 されているそうです。
11月27日の給食
今日ん献立は、「麻婆丼 肉シューマイ もやしとわかめのナムル 牛乳」でした。
もやしは、豆を水につけてから作ります。光を当てずに暗い場所で育てることで、白くて長いもやしになります。天気に左右されず、収穫や値段も安定しているため手に入りやすく、くせがなく調理しやすい野菜です。今日はナムルに使われていました。
11月26日の給食
今日の献立は、「カレーうどん かぼちゃコロッケ ビーンズサラダ 牛乳」でした。
カレーうどんの発祥は、東京早稲田の老舗料理店だと言われています。その数年後には別の店から「カレー南蛮そば」が誕生しています。カレーうどんは、インド発祥の「カレー」と中国発祥の「うどん」が日本の和風だしでアレンジされた人気のある料理です。
11月25日の給食
今日の献立は、「ごはん 卵焼き 切干大根のゆずぽん酢あえ すき焼き風煮 牛乳」でした。
豆腐は、大豆の代表的な加工食食品です。豆腐は、大豆に水を加えながらすりつぶし、豆乳とおからに分けて、豆乳ににがりを加えて固めて作ります。今日の給食では、すき焼き風煮にたくさんの豆腐を使用しました。
11月21日の給食
今日の献立は、「コッペパン タンドリーチキン ひじきとツナのサラダ 豆のポタージュ 牛乳」でした。
白いんげん豆は、煮豆や甘納豆、白あんの原材料として和菓子などによく使われています。世界では肉と一緒に煮込んだり、スープに使ったりと、おかずとして食べられることが多いようです。様々な栄養素を含んでおり、コレステロール値や血糖値の上昇を抑える働きがあります。特に他の豆と比べてカルシウムが豊富です。給食でも、白いんげん豆のピューレをカレーやシチューに入れたりと、積極的に使用しています。今日は、白いんげん豆で作ったポタージュが出ました。
11月20日の給食
今日の献立は、「ごはん 納豆 インド煮 鶏団子スープ 牛乳」でした。
納豆は、大豆を蒸して納豆菌をまぜ発酵させてつくります。ネバネバの正体は、うま味成分でおいしさのもとです。独特の風味をもつ消化吸収の良い、優れた発酵食品です。ビタミン類 やマグネシウムなどのミネラル、食物繊維や、腸に良い乳酸菌を多く含んでいます。免疫力を高める健康食品とも言われています。長寿国日本の長生きの秘訣として、各国の健康志向の高まりにともない、国外でも匂いを弱めた納豆の人気が高 まっています。