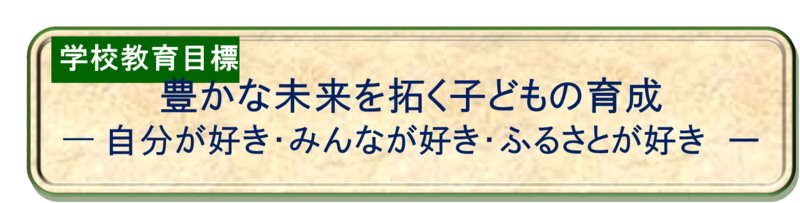今日の給食(令和7年度)
11月25日(火)
「わかめごはん、カレー肉じゃが、ちゃんぽんみそ汁、みかん、牛乳」
今日は「わかめごはん」です。炊いたごはんに、わかめごはんの素、煎ったごまを、塊がないよう丁寧に混ぜ合わせました。子どもたちには大好評で、よく食べていました。
「カレー肉じゃが」には、80㎏のじゃが芋を使用しました。豚肉、玉ねぎ、にんじん、しらたきを炒め、だし汁、調味料を入れてから、じゃが芋を入れて煮ました。じゃが芋は、煮崩れしないように、少し固めのタイミングで一度火を止めて約10分置いて味を染み込ませ、再度火を付けて、青みのいんげんを入れて仕上げました。いつもと違うカレー風味の肉じゃがは、子どもたちにも好評でした。
「ちゃんぽんみそ汁」は、鶏肉、いか、かまぼこ、野菜が入ったみそ汁です。いかは硬くならないように、酒をふって軽く蒸してから入れました。最後に、流山産の小松菜を入れて仕上げました。
11月21日(金)
「ごはん、鮭の南部焼き、磯香あえ、具だくさんみそ汁、牛乳」
11月24日は「和食の日」です。24日は振替休日なので、今日は和食の献立にしました。和食は、多様で新鮮な食材を使用し、栄養バランスのとれた食事として「ユネスコ無形文化遺産」に登録され、世界にも認められました。
「鮭の南部焼き」は、鮭にしょう油、酒、みりんで下味を付け、白ごまをふりかけてオーブンで焼きました。鮭の切身は冷凍の状態で納品されて下味がつきにくいので、鮭を鉄板に並べる時にバットに残った調味料もふりかけて焼きました。白ごはんによく合い、子どもたちも食べやすかったようです。
「磯香あえ」は、にんじん、もやし、流山産の小松菜をゆでて冷却し、調味料の一部をかけて、野菜から出てくる水分をよく切ってから、蒸して冷却した糸かまぼこ、オーブンで焼いたきざみのり、残りの調味料を混ぜ合わせました。のりの香りが良く、子どもたちにも好評でした。
「具だくさんみそ汁」は、豚肉、じゃが芋、野菜、干ししいたけなどが入った具だくさんのみそ汁です。干ししいたけの戻し汁も使用し、いろいろな具材からうま味が出ていました。
11月20日(木)
「ほうとう、じゃが芋とひじきの煮物、安倍川もち、牛乳」
今日は、「山梨県民の日」ということで、山梨県の郷土料理を取り入れました。山梨県出身の先生から教えていただきました。
「ほうとう」は、山梨県を代表する郷土料理で、かぼちゃや里芋などが入ったみそ味の煮込みうどんです。かぼちゃは煮崩れないように、他の具材が煮えてから最後の方で入れました。幅広で太めのうどんは、おいしい汁を吸って食べごたえがありました。ある教室では、「体が温まるね~」と言いながら、うれしそうに食べていました。
「じゃが芋とひじきの煮物」は、富士山の山開きの時に食べるそうです。じゃが芋やひじき、油揚げに味がよく染みていました。ひじきは、食べ慣れていない子も多いですが、山盛りのおかわりをしている1年生もいました。
「安倍川もち」は、きな粉がかかったおもちです。きな粉と砂糖をザルでこして、塊がないように混ぜ合わせ、白玉もちにかけました。子どもたちには大人気で、おかわりの行列ができていました。
11月19日(水)
「チキンカレーライス、ツナとわかめのサラダ、牛乳」
今日は「チキンカレーライス」です。米は、6㎏ずつ14釜炊きます。米と水に加え釜の重さもあるので、炊飯器の一番上の段に入れるのも2人掛かりです。カレールウは、バターと小麦粉各8㎏を色づくまで炒め、カレー粉を入れて更に炒めました。玉ねぎの半量は、茶色くなるまで30分以上炒め、甘味とうま味を引き出しました。釜いっぱいにあった玉ねぎの嵩は、1/4位に減ります。また、カレールウとは別に、ガラムマサラとカレー粉を油で軽く炒めたものを最後に入れ、香りを引き立たせました。いつも通り子どもたちにも大好評で、よく食べていました。
「ツナとわかめのサラダ」は、野菜と茎わかめはゆでて冷却し、蒸して冷却したツナ、ごま、調味料と混ぜ合わせました。野菜や茎わかめのシャキシャキとした歯ごたえとツナのうま味で、子どもたちも食べやすく、食べ残しの少ないサラダです。
11月18日(火)
「カミカミ丼、大根サラダ、厚揚げのみそ汁、りんご、牛乳」
今日は「カミカミメニュー」です。茎わかめ、ごぼう、こんにゃく、えのき茸、りんごなど、かみごたえのある食材を使用しました。
「カミカミ丼」は、豚肉、玉ねぎ、にんじん、ごぼう、糸こんにゃく、茎わかめを炒めて味付けし、サッと下ゆでしたピーマン、ごま油を入れて仕上げました。味付けには、トウバンジャンやみそ、砂糖、しょうゆなどを使用しました。
「大根サラダ」は、大根、きゅうり、キャベツ、にんじん、糸かまぼこをゆでて冷却し、調味料、ごまと和えました。糸かまぼこは、丁寧にほぐしました。野菜は、ゆでてから手早く冷却し、歯ごたえを残しました。
「厚揚げのみそ汁」は、切った厚揚げを湯通しして、油抜きをしてから入れました。最後に、流山産の小松菜を入れて仕上げました。みそは、赤みそと白みそを合わせて使用したので、味に深みが出ました。
1年生の教室で、「よくかんで食べましょう」と声をかけると、「歯がグラグラしてるから、うまくかめないんだぁ」と歯をよく見せてくれました。