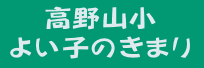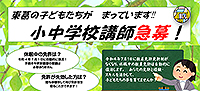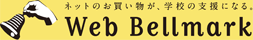校長室から
校長室から~5月を振り返って
運動会を振り返って考える
校長 安田 憲司
5月25日の運動会は、たくさんの地域・保護者のみなさまにお越しいただき誠にありがとうございました。残念ながら酷暑のためプログラム23番の2年生「大玉ころころ」から、6月8日の1日参観日午前中へ延期となってしまいました。過日ご案内文書を発送してありますのでご覧いただき、お時間がございましたら学校まで足を運んでくださると、児童の励みになります。
今回は、暑さ対策として全児童を冷房のきいた教室へ戻す15分休憩や、お昼休憩時のエアコン完備の全教室開放など、さまざまな対応をいたしましたが、それだけでは十分ではないと考えています。そこで、現在、次年度以降の運営について、気候の変動に伴う対応も考慮に入れ、どうしていくのか職員と相談し、いろいろな対策を検討しているところです。今後PTA役員の方々にもお図りし、年度内には一つの結論に導く所存でありますので、今後ともご理解ご協力をお願いいたします。
さて、5月15日のお昼の放送で放送委員会の児童からインタビューを受けました。テーマは、「校長先生の休日の過ごし方」です。
私の休日は、よくドラマや映画を見ています。子どもたちに紹介した曲は、「ボヘミアン・ラプソディ」という映画に出てきた「ウィ・ウィル・ロック・ユー」(英語: We Will Rock You)」という曲でした。放送室の中で高学年の児童がよく知っていると口ずさんでいたのが印象的です。音楽は、心を豊かにしますし、音楽をとおして心が通じ合うこともあります。実際、映画を見ながら同年代の方々と大変盛り上がりました。
最近は、「アベンジャーズ・エンドゲーム」を見て感動しました。
また、私は、音楽を聴くことや作詞・作曲もよくしています。休日は、自分の部屋でギターを弾きながらよく歌っています!これまでにたくさんの曲を作ってきましたので、機会があれば集会等で紹介したいと思っています。
では、雨の季節6月になります。運動会後は、「わかる授業づくり」に向け、校内研究会も予定されておりますので、その様子は、ホームページ等でお知らせしていきます。
今月も、どうぞ、よろしくお願いいたします。
5月だからこそ必要なこと!
5月だからこそ必要なこと!
~帽子・交通安全・一緒に行動~
校長 安田 憲司
5月に入り、令和と元号が代わりました。世間は、新元号の登場と10連休にわきましたが、よい思い出がたくさんできましたか?
さて、5月というと次の「3つの増える」を思い出します。
1つ目は「紫外線」です。気象庁の観測データによる月別紫外線量から、5月あたりから紫外線量が増えていき、7~8月頃がやはり1番多くなっています。
5月は過ごしやすい気候でも、紫外線は多く、外で活動する時には注意が必要です。運動会練習もあり、学校では十分に気をつけていきますが、天気によっては帽子をかぶることもおすすめします。ただし、風で飛ばされて、交通事故になることもあるので、帽子にゴム紐を付けるなど工夫も大切です。
2つ目は、小学生の交通事故です。警察庁の集計で2014年からの5年間に歩行中の交通事故で死亡したり重傷を負ったりした小学生は全国で合計3276人、月別では5月の349人が最も多かったことが分かりました。特に小学校1年生の増加が目立っているそうです。また、内容別では「下校中」が多く、6割以上が「飛び出し」や「横断違反」などが報告されています。
また、県内では、小学生が、停車中や走行中のバスや乗用車を触る事案が起きています。交差点等で速度を落とした際に触るようです。大変危険なので学校は十分に指導していきますが、ご家庭でもお願いします。
3つ目は、「忘れ物」です。年度初めは緊張していることや、保護者の目が行き届いているので少ないのですが、5月に入り、慣れてきたところで増加してきます。「忘れ物はない?」という声かけも大事ですし、前日の夜に親子で一緒にそろえる習慣も大切です。親が全てやってあげるのではなく、お子さんと一緒にすることで身に付いていきます。鉛筆を削ることや、必要な物をランドセルに入れることを繰り返し一緒にお願いします。(学習に関係ないものは持たせないでください。)
最後に、4月19日に行われた学習参観・懇談会の際には、授業参観後に保護者全体会(学校経営説明・職員紹介)とPTA総会を実施したのですが、体育館に用意した椅子に座りきれない保護者のみなさまにお集まりいただきました。保護者のみなさまの本校の教育活動に対する高い関心度と共に、力強いご支援をいただいていることを感じました。ありがとうございます。今月は運動会もありますので、どうぞよろしくお願いいたします。
なかよく・すすんで・げんきよく!
自立した児童の育成を目指して
「なかよく すすんで げんきよく」
~ 平成31年度のスタート ~
校長 安田 憲司
今年度より高野山小学校でお世話になることになりました、安田憲司と申します。香取市立山倉小学校から異動して参りました。子どもたちのためにがんばりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
4月1日の校内辞令交付式では、新しく仲間入りする16名の教職員が高野山小学校の先生方にあたたかく迎えていただきました。初めて聞いた校歌。そして全職員で唱和した「なかよく・進んで・元気よく」の高小スローガン!さわやかな笑顔とキラキラした目の先生方と出会った感動は、きっとこの後も忘れません。
さて、今年度もこれまで同様「なかよく(徳育)・進んでなかよく(知育)・元気よく(体育)」の合い言葉のもと、自立した子どもたちの育成に向かって、質の高い教育活動が行えるよう教職員一丸となって取り組んでまいります。
また、4月5日始業式の校長の話では、子どもたちに、高小スローガンに加え、
「明るいあいさつ・だまってそうじ・一生懸命にべんきょう」
の3つに力を入れてほしいこと。この3つの頭文字「あそべ」も大事だという話をしました。学校生活ではいろいろなことが起こると思いますが、最後は「笑顔」で下校できるよう精一杯支援してまいりますのでよろしくお願いします。
最後に新1年生95名を11日の入学式で迎え、平成31年度の教育活動が始まりました。今年度も昨年同様、保護者のみなさま、地域のみなさまのご理解とご協力をどうぞよろしくお願いいたします。「学校職員の働き方改革」へのご理解とご協力を
校長 金子 博之
男性教員5名(管理職を含む)、女性教員2名、この人数は、ある日の朝の部活動実施日、7時に出勤している職員の数です。更に給食調理員、安全管理員も7時前に出勤し、仕事を始めているというのが、高野山小学校の早朝の様子です。
2月14日に我孫子市教育委員会教育総務部長名で出された「学校職員の働き方改革について」という文書には、新年度の4月1日から実施される予定の「我孫子市学校職員の働き方改革推進プラン(案)」の概要が載っていました。保護者のみなさま方にはご理解とご協力をお願いする次第です。どうぞ、よろしくお願いいたします。
文書にもありました通り、
・業務の改善として
① 週1日、18時00分退勤の「ノー残業デー」を設定します。(曜日未定)
② 夏季・冬季休業中の学校閉庁期間の拡大をします。
③ 夜間・早朝の電話対応の時間を設定します。7時00分~18時00分
※委員会の文書では、7時15分からとなっていますが、高野山小学校では朝は7時00分から電話対応をさせていただきます。
④通知票の記載内容を見直します。
学期ごとの通知票の内容を精選していきます。
⑤ 家庭訪問を見直します。
1年生のみ実施し2年生以上は行いません。(ただし面談を希望されるご家庭や担任の方からお声をかけさせていただく場合は、学校での個人面談を実施します。)
・人員体制の整備として
⑥2024年度導入に向けて部活動指導員による支援体制の構築を図ります。
・部活動の在り方に関するガイドラインより
⑦週1日の「ノー部活デー」を設定します。(曜日未定)
※今年度は木曜日でした。
今年度の「学校評価アンケート」で、『ノー部活デーの日も昇降口は、いつもと同じ7時05分に開けて欲しい。』というご意見をいただきました。最初にも書きましたが、部活のある日には、職員は、7時前には出勤し朝の部活動に備えています。ノー部活デーの日には、職員にも遅めの出勤を奨励しています。従いまして、朝の校内体制が手薄となっており、児童の対応ができないという点を考慮し、ノー部活デーの日は、7時40分に昇降口を開けさせていただいております。何とぞご理解とご協力をお願いいたします。
最後に、私事で恐縮ですが、今月31日をもちまして定年退職となります。高野山小学校では、2年間お世話になりました。
保護者のみなさま、地域のみなさまには、日頃よりご支援、ご協力を賜り、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。
今後とも、高野山小学校の児童・教職員へのご支援、ご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。
先生、うちのクラス、あと何人休んだら学級閉鎖
校長 金子 博之
現在、高野山小学校ではインフルエンザが猛威を振るっています。保護者のみなさまも、我が子がかからなければ良いが・・・とご心配なのではないでしょうか。担任の先生方には、各学級で教室の換気と子どもたちへのうがい・手洗いの励行をお願いしているところですが、すでに先月中旬に1年生の一クラスで、3日間の学級閉鎖を実施しました。また、子どもたちが楽しみにしている「わんぱくタイム」も、感染拡大の恐れがあることから、やむなく中止とさせていただきました。高野山小学校でのインフルエンザのピークはこれからかもしれません。何かとやきもきする季節となりました。
「学級閉鎖を実施するか、しないかというのは、どうやって決まるのですか?」
先日、保護者の方とお話ししている時にそんな、素朴な疑問の声をいただきました。
「先生、うちのクラス、あと何人休んだら学級閉鎖?」と担任の先生に聞いてくる児童もいます。
学級閉鎖は校長の判断で決まり、一定の数的基準とかがあるわけではありません。(学級の児童数の2割が休んだら・・・違います。)風邪による発熱ではなく、インフルエンザとお医者さんから診断された児童が増えてきたクラスがあったとして、その子達以外の他の児童の健康状態が重要なポイントとなってきます。発熱で欠席している児童が、インフルエンザと診断されるなどして、今後右肩上がりに罹患者が増えていきそうな勢いなのか、あるいはクラス内は終息に向かっているのか、インフルエンザだった児童がいつから登校できるか等々を確認し、学校医とも相談しながら、総合的に判断して決めています。
間近に大きな校内行事などが控えている場合には、早めに学級閉鎖を実施し、蔓延を防ぐ対策を講じて、行事を実施するといった場合もあります。
様々な状況を判断材料として、学級閉鎖を行うわけですが、保護者のみなさま方には、ご迷惑にならないよう、お手紙やメールにて事前にお知らせしていきますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
あわせてお願いです。インフルエンザや発熱等での欠席のご連絡ですが、早朝は職員が手薄なために電話に出られないことがございます。連絡帳での連絡をお願いいたします。また、お電話の場合は、7時過ぎにお願いいたします。
(その際、すぐに電話に出られないこともあります。ご了承ください。)
今月もどうぞ、よろしくお願いいたします。