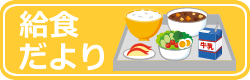学校の様子
令和7年度 進路PTA
10月2日(木)、3年生の生徒、保護者を対象にした進路PTAを開催しました。前半は私立高校、後半は県立高校の受験(検)の際の手続き方法について、進路指導主事から説明がありました。秋の訪れとともに、受験シーズン突入です。3年生の皆さん、頑張ってください。
令和7年度 思春期教室
9月26日(金)、講師の方をお招きして全クラス(1年生のみ男女別)で思春期教室を開催しました。生徒たちは皆真剣に聞き入り、心身の発育・発達や性に関する内容について理解を深めることができました。
令和7年度 地区新人大会
9月19日(金)~20日(土)にかけて、栃木県中学校新人体育大会塩谷地区予選会が各会場で開催され、本校から陸上競技部、卓球部、ソフトテニス部、サッカー部、バレーボール部が参加しました。今大会では陸上競技部から5名、卓球部から1名の選手が来月開催される県大会への出場を果たしました。
*会場移動の関係で、参加したすべての生徒の写真を掲載できないことをお許しください。
令和7年度 WEBQUの分析と活用研修会(現職教育)
9月10日(水)の放課後、栃木県総合教育センターから講師の先生をお招きして職員研修を実施しました。今回の研修テーマは「WEBQUの分析と活用」でした。WEBQUの結果を基に、それぞれの学年に分かれて適切な指導・支援にための事例研究を行いました。
令和7年度 第2回学校運営協議会
9月2日(火)、今年度2回目の学校運営協議会を開催しました。今回は始めに授業参観をしていただき、子どもたちの学ぶ様子を見ていただきました。その後の協議では10月9日(木)に予定されている生徒集会「防災脱出ゲーム」で、委員の皆さんに協力をお願いしました。ゲームの説明は生徒会長が行いました。