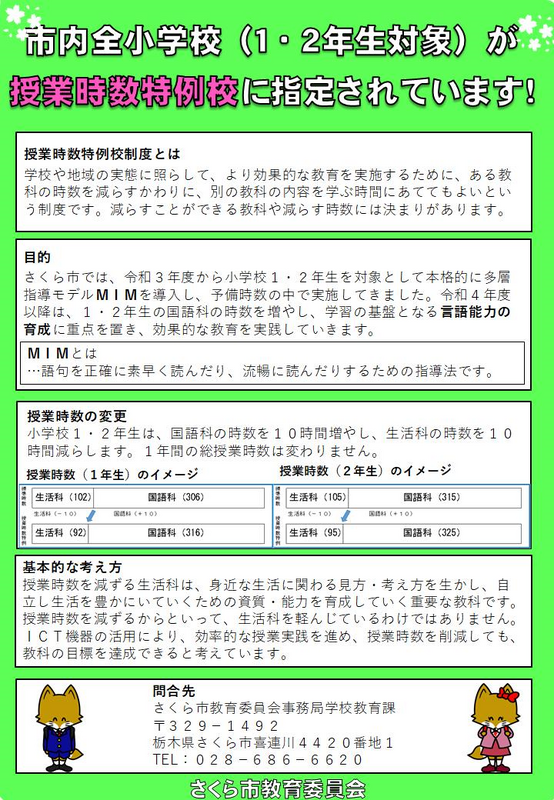文字
背景
行間
2021年9月の記事一覧
今日の給食 9月29日

今日は、にら についてのお話です。
栃木県は、にらを全国で2番目に多く生産していてます。さくら市でも多くにらが作られています。
にらは、1年に数回収穫できるくらい成長が早く、とても強い野菜です。これから寒くなってくると、肉厚で甘味も増しとてもおいしくなります。
からだを温めたり、粘膜を守ったりする働きがあるので、かぜを予防する効果があると言われています。
ぎょうざ、いためもの、あえもの、みそ汁などいろいろな料理に使われるおいしい野菜です。今日はかきたま汁にしました。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ いわしのごまみそに
・ きりぼしだいこんのちゅうかサラダ
・ にらいりかきたまじる
今日の給食 9月28日

今日は、きゅうり についてのお話です。
日本にやってきたのは奈良時代と言われています。熟すと実が黄色くなり、「黄色い瓜」なので、「きうり」と呼ばれたのが名前の由来です。一年中見かけますが、夏が旬の野菜です。
水分が多い野菜で、ビタミンCが含まれています。シャキシャキした歯切れの良さや、みずみすしさがサラダにぴったりの野菜です。
今日は、パンプキンサラダに入っています。
今日のメニュー
・ ミルクパン ・ 牛乳
・ しろみざかなフライ
・ パンプキンサラダ
・ キャベツとベーコンのスープ

今日の給食 9月27日

今日は、カレー についてのお話です。
カレーは、いろいろな香辛料を使った料理で、熱帯地方の人々が肉の臭みを消すことと、食欲増進のために考えられたと言われています。
サラッとしたカレーが18世紀後半、イギリスに伝わりました。日本には明治時代に伝わり、簡単でおいしくできるようにカレールウが開発されて、今のような「カレー」が食べられるようになりました。
今日はチキンカレーです。玉ねぎ、にんじん、じゃがいもなどが入り、よりおいしくするために、2種類のルーやりんご、トマトなどを加えて作っています。
今ご飯ご飯・ ごはん ・ 牛乳
・ チキンカレー
・ かいそうサラダ
・ はちみつレモンゼリー
今日の給食 9月24日

今日は、とり肉 についてのお話です。
とり肉は、牛肉や豚肉に比べて脂肪がやや少なく、あっさりとしていて消化の良い肉です。とり肉を部位で、大きく分けると、もも、胸、手羽、ささみ、になります。また残った骨は「とりがら」といっておいしいスープがとれます。
今日の給食は、とり胸肉に塩、こしょうをし、でんぷんをまぶして、油で揚げたところに、さとう、しょうゆ、レモン汁で作ったレモンソースをかけました。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ とりにくのレモンソースがけ
・ ひじきとツナのいろどりナムル
・ にくいりワンタンスープ
今日の給食 9月22日

今日は、さば についてのお話です。
さばは、日本で古くから食べられている代表的な魚です。
たんぱく質をたくさん含んでいて、からだの血や筋肉をつくる働きをしてくれます。また、さばのような背中の青い魚のあぶらは、血液をさらさらにしたり、脳の働きを活発にしてくれたりします。
これからの秋から冬が旬であぶらがのっておいしい魚です。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ さばのてりやき
・ ほうれんそうのごまあえ
・ だいこんとあぶらあげのみそしる
今日の給食 9月21日

今日は、ポークビーンズ についてのお話です。
ポークビーンズは、白いんげん豆と豚肉のトマト味の煮込み料理で、アメリカの代表的な家庭料理の1つです。豚肉の代わりにベーコンを使うこともあります。
給食では、白いんげんの代わりに大豆を使います。
大豆には、体をつくる「たんぱく質」が肉や魚のようにたくさん含まれていて、「畑の肉」とも言われています。
今日のメニュー
・ セルフコロッケサンド(スライスまるパン
カレーコロッケ ソース) ・ 牛乳
・ キャベツサラダ
・ ポークビーンズ

今日の給食 9月17日

今日は、肉じゃが についてのお話です。
肉じゃがは、じゃがいもを、肉や野菜と一緒に煮込んだ煮物料理で、各家庭でもよく作られています。
関西では牛肉、関東では豚肉が使われることが多いようです。
肉じゃがの歴史は古く、すでに明治時代には海軍の料理の教科書で肉じゃがに近い料理のレシピがあったそうです。ビタミンをたくさん含み、栄養豊富な料理として広まりました。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ にくじゃが
・ ツナとわかめのあえもの
・ なっとう
今日の給食 9月16日

今日は、キャベツ についてのお話です。
キャベツは、オランダ人によって長崎に伝えられたので、オランダ菜と呼ばれていました。キャベツが日本で本格的に食べられるようになったのは、明治時代になってからです。今では、キャベツは日本で2番目に多く作られる野菜になりました。
キャベツには、病気から体を守ってくれるビタミンCが多く含まれています。
キャベツは炒めたり、蒸したり、煮たり、生のままでも食べることができるのでとても使いやすい野菜です。
今日のメニュー
・ 食パン いちごジャム ・ 牛乳
・ メンチカツ
・ ポテトサラダ
・ キャベツとウインナーのスープ

今日の給食 9月15日

今日は、ひじき についてのお話です。
ひじきは海藻の仲間です。ひじきというと、黒い色を思い浮かべますが、海の中では濃い茶色をしています。
とれたひじきを干した後、水を加えて沸騰させます。それを、太陽の下で乾燥させてできあがります。使うときは、水に戻して使います。
ひじきは、貧血を防ぐ鉄や、骨や歯を丈夫にするカルシウムが多く含まれています。体がどんどん成長しているみなさんには、ぜひ食べてもらいたい食品です。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ あつやきたまご
・ ひじきとゆばのにもの
・ とんじる
今日の給食 9月14日

今日は、にんじん についてのお話です。
にんじんは、緑黄色野菜の代表で、ほとんど毎日、給食にでています。オレンジ色が料理をおいしそうにみせてくれるためと、カロテンという栄養素を多く含んでいるためです。にんじんのオレンジ色は、このカロテンの色なのです。
カロテンは体の中に入るとビタミンAに変わり、鼻やのどの粘膜を強くして、病気にかかりにくくしてくれます。また、食物せんいも多く含み、おなかの調子をよくしてくれます。
今日のメニュー
・ ミルクパン ・ 牛乳
・ コーンコロッケ
・ ブラウンシチュー
・ フルーツのゼリーあえ
今日の給食 9月13日

今日は、キムチ についてのお話です。
キムチは日本でもなじみの深い韓国の漬物です。韓国では白菜だけでなく、きゅうりや大根などのいろいろな野菜のキムチや魚介類を加えて作るキムチもあるそうです。
キムチは辛いだけでなく、酸味もありますが、これは乳酸菌を使った発酵食品であるためです。食べ過ぎはよくありませんが、乳酸菌の働きで腸内の環境を整えるのにも役立ちます。また、適度な辛さは、食欲を増し、体を温めてくれます。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ ショウロンポウ
・ こまつなとキャベツのおひたし
・ キムチスープ おかかふりかけ
今日の給食 9月10日

今日は、豆腐 についてのお話です。
豆腐は、大豆を水に漬けてすりつぶし、煮たものをこして、にがりを入れて固めて作ります。畑の肉といわれる大豆の栄養がたっぷり入っています。
豆腐は、今から1200年ほど前に中国のお坊さんが作ったと言われています。日本には奈良時代に伝わり、現在まで食べ続けられています。
今日は、小さなパックに入った豆腐にタレをかけていただきましょう。
今日のメニュー
・ ごはん ・ ごもくごはんのぐ
・ 牛乳
・ ひややっこ たれ
・ じゃがいもとわかめのみそしる

今日の給食 9月9日

今日は、パン についてのお話です。
パンは、今から6千年くらい前にエジプトで作られたのが最初と言われています。そのころのパンは、うすいせんべいのようなものだったそうです。日本には、今から400年ほど前にやってきたポルトガル人によって伝えられました。多くの人がパンを食べるようになったのは、明治時代より後のようです。
パンは、ごはんや麺と同じように熱や力のもとになる大切な食べ物です。食べやすい大きさにちぎって食べてくださいね。
今日のメニュー
・ バターロールパン ・ 牛乳
・ スパゲティナポリタン
・ アンサンブルエッグ
・ はなやさいサラダ
今日の給食 9月8日

今日は、ゆば についてのお話です。
ゆばは、栃木県の日光と京都のゆばが有名です。奈良時代、修験僧が食べたのが始まりといわれています。
京都では、漢字で「お湯の葉っぱ」と書きますが、日光では「お湯の波」と書きます。
ゆばは、大豆から作られる食べ物です。豆乳を加熱した時に表面にできる薄皮がゆばになります。
おさしみ、うま煮、吸物、酢の物などいろいろな料理に使われます。今日はすまし汁にゆばを入れました。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ みそカツ
・ コールスローサラダ
・ ゆばいりすましじる
今日の給食 9月7日

今日は、かぼちゃについてのお話です。
カボチャの原産地は、アメリカです。日本に伝えられたのは、17世紀のことで、カンボジアから伝えられたので、かぼちゃと呼ばれるようになりました。
現在、日本で栽培されているかぼちゃは、日本かぼちゃ、西洋かぼちゃ、ペポかぼちゃの3種類です。その中でも、調理法が多く、ほくほくした西洋かぼちゃが多く出回っています。
かぼちゃはハロウィンや冬至に使うイメージがありますが、かぼちゃの旬は夏です。夏に収穫して冬までおいしく食べることができる野菜です。
今日のメニュー
・ アップルパン ・ 牛乳
・ やさいにくだんご
・ コーンサラダ
・ かぼちゃシチュー
今日の給食 9月6日

今日は、マーボー豆腐のお話です。
マーボー豆腐は、給食でも家庭でもよく食べられている料理だと思いますが、もともとは中国の料理です。
マーボー豆腐のピリッとした辛味は豆板醤という調味料が入っているからです。豆板醤は、日本のみそのようなもので、中国の料理、特に四川地方の料理には欠かせないものです。日本のみそは大豆から作りますが、豆板醤は、「そら豆」から作ります。
級のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ マーボーどうふ
・ ぎょうざロール
・ いそべあえ
今日の給食 9月3日

今日は、牛乳 についてのお話です。
給食には毎日牛乳がつきますね。牛乳には、骨や歯をじょうぶにしてくれるカルシウムが多く含まれています。
体を作るたんぱく質も多いので、成長期のみなさんにはとても大切な食品です。また、にんじんなどの色の濃い野菜に多いビタミンAも含まれています。
牛乳は、1番最初にストローをさして、少しずつ飲むようにしましょう。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ ハンバーグおろしソースがけ
・ ブロッコリーとじゃこのサラダ
・ とうがんとあぶらあげのみそしる
今日の給食 9月2日

今日は、ミネストローネ についてのお話です。
ミネストローネは、イタリアの代表的なスープです。イタリア語で「具だくさん」「ごちゃ混ぜ」などの意味の言葉で、新鮮な野菜をたっぷり入れた、トマト味のスープです。
イタリアでは日本のみそ汁のように、毎日食卓に出てくることが多い料理です。ベーコンやにんじん、じゃがいも、玉ねぎ、マカロニなどたくさんの材料が入っている栄養たっぷりのスープです。
今日のメニュー
・ 黒食パン ・ マーガリン
・ 牛乳 ・ カレーロールフライ
・ フレンチサラダ
・ ミネストローネ

今日の給食 9月1日

今日は、アジ についてのお話です。
アジは、味がいいから「アジ」と名前がついたと言われています。
カルシウムやカリウムが多く、骨や歯を丈夫にしてくれます。ビタミンBも多く、体の疲れをとる働きがあります。また、魚の油には、血液をサラサラにしたり、脳を活性化する働きがあります。
アジは、煮付けや焼き魚、あじフライなどいろいろな調理法で食べられます。今日は焼き魚にしました。
今日のメニュー
・ ごはん ・ 牛乳
・ あじのしおやき
・ ごまずあえ
・ どさんこじる