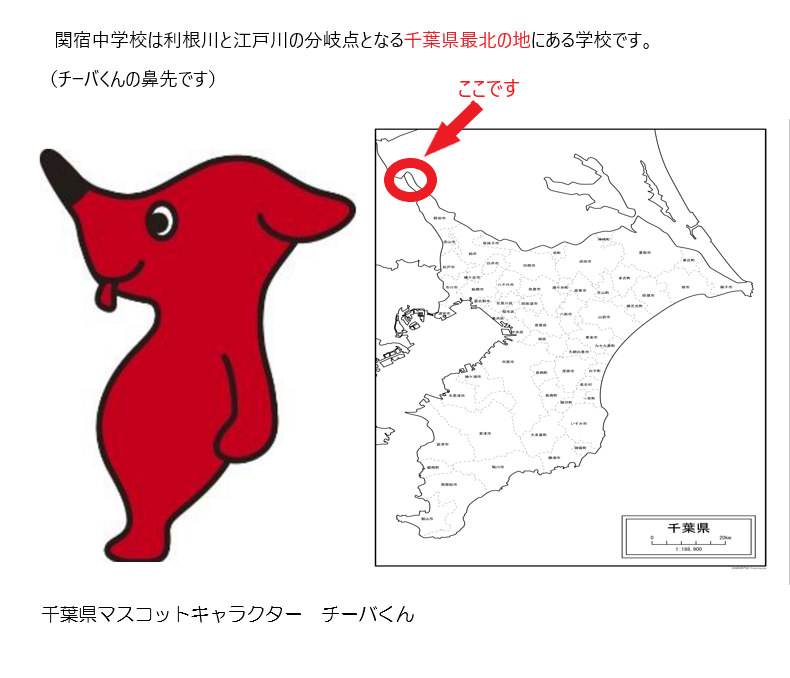校長室から
よいお年を
2017年も学校は、部活動や学習で登校する生徒は多くいるものの一応の終了です。
集会・学級活動を経て今、部活動を行い、下校していきました。
冬休みは、家庭・親を大切にすること。自分や命を大切にすること。ある意味いやだったことを忘れ、リセットしてよい年を迎えましょう。という話をしました。
日本の伝統文化に触れさせ、新しい気持ちを持たせることにその意義があると思います。
充実した年末年始になることをお祈りいたします。
みなさま2018年良いお年をお迎え下さい。
全校学習(保護者参観)

昨日は、私の全校授業を参観頂きましてありがとうございました。
「勉強」ということについて改めて考える機会となりました。
参観頂き、授業の様子、生徒の様子、職員の様子はいかがだったでしょうか。
もうすぐ、2017年も終わります。学習について振り返り、少しでも「根」の部分の説明をしました意欲につながってもらえればと思います。
保護者の皆様には、その後の懇談会も多数参加頂きまして誠にありがとうございました。
12/20保護者会について
12月20日、冬休み前の保護者会を開催いたします。5時間目に全校学活として私めが「なぜ勉強をするのか」という授業をさせて頂きます。全校一斉授業は初めてですのでどうなるかわかりませんが、よろしかったら参観下さい。格技場で行います。
その後、全体会で2回目の学校評価の公表と冬休みの生活について、
学年会で1年生はスキー林間学校について 2年生は校外学習の報告も含めた生活の様子について、 3年生は今回が最後の懇談会になります。よろしくお願いいたします。
2年生校外学習
昨日校外学習にいってきました。
東武動物公園の集合の後、各班で計画に従った行動をしました。
あとの感想で聞くと、道を丁寧に教えてくれた人、わざわざ混雑の中でスペースを空けてくれた人
友達の協力、道の判断、楽しい声かけ、感性の高い本校の生徒ならではの感想があちこちに聞かれました。
午後は全員で本所防災館で研修です。災害を元にした映像だけでなく、消火・煙・地震・風水害の体験をすることが出来、貴重な半日でした。
いざという時に役に立つのは(特に昼間は)中学生だと思います。本校の生徒は、いざという時にきっと活躍してくれると確信した一日でした。

東武動物公園の集合の後、各班で計画に従った行動をしました。
あとの感想で聞くと、道を丁寧に教えてくれた人、わざわざ混雑の中でスペースを空けてくれた人
友達の協力、道の判断、楽しい声かけ、感性の高い本校の生徒ならではの感想があちこちに聞かれました。
午後は全員で本所防災館で研修です。災害を元にした映像だけでなく、消火・煙・地震・風水害の体験をすることが出来、貴重な半日でした。
いざという時に役に立つのは(特に昼間は)中学生だと思います。本校の生徒は、いざという時にきっと活躍してくれると確信した一日でした。
2年生校外学習
2年生は、かなり成長してきました。
班別行動での学習は、不安もありますが、それよりも更に成長してくれることを期待できる学年になってきました。
東武動物公園を班別に出て、人混みの電車に揺られ皆で試行錯誤しながら、テーマ別研修をすることでこの上ない社会勉強をすることでしょう。
安全に気をつけて、良い勉強になることを祈ります。
保護者の皆様、駅までの送りありがとうございます。明日、今までの準備を無駄にしない行動になることを願うばかりです。
班別行動での学習は、不安もありますが、それよりも更に成長してくれることを期待できる学年になってきました。
東武動物公園を班別に出て、人混みの電車に揺られ皆で試行錯誤しながら、テーマ別研修をすることでこの上ない社会勉強をすることでしょう。
安全に気をつけて、良い勉強になることを祈ります。
保護者の皆様、駅までの送りありがとうございます。明日、今までの準備を無駄にしない行動になることを願うばかりです。