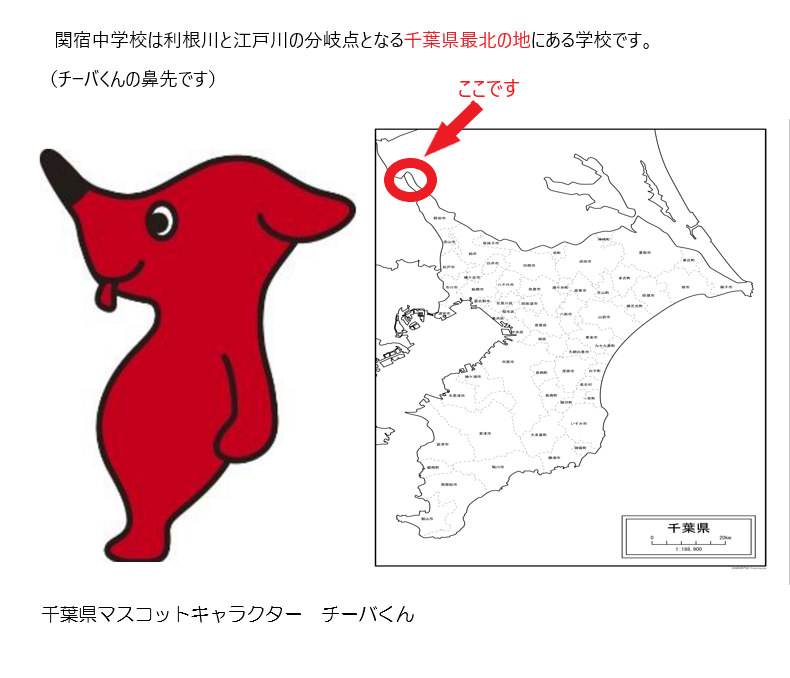校長室から
和太鼓部フェスタ
 9月30日和太鼓部によるフェスタが行われました。
9月30日和太鼓部によるフェスタが行われました。和太鼓部は千葉県でも関宿中独特の取り組みで、地域の行事、文化祭等で発表します。
それぞれが、部活動を2つも持っていて、更にこの和太鼓部を運営・活動しているわけですから、練習時間の確保も難しいところです。
今日の発表では、創作和太鼓のみでなく、踊り、ゲーム、和太鼓体験コーナー等もあり、楽しい企画となりました。
お茶のコーナーがあり、お客様には生徒手作りのお手紙付きコースターセットが全員に渡され、至れり尽くせりでした。部員の表情からにじみ出る充実感を見ていると皆さんが幸せな気持ちになった時間でした。
特に、3年生の和太鼓部の人たち3年間の活動ご苦労様でした。ありがとうございました。
月
「月」が美しいとき。今年の中秋の名月は10月4日です。日本人は、花と並んで月が好きですね。
徒然草(吉田兼好)で
「花は盛りに、月は隈(くま)なきをのみ、見るものかは(花は満開の時だけを、月は曇りがないのだけを見るものであろうか、いやそうではない」
この文に続けて、兼好法師は、「降っている雨を見ながら、見えない月を慕うのも、しみじみと趣深い」と独特の美意識を展開しています。
人それぞれの感じ方ですね。
自分の経験を積み重ねることで感覚がみがかれ、自分の言葉を持つようになります。
獲得した言葉の数だけ感情を細かく分けることが出来、多様な視点を持つことが出来るものです。
様々な教育活動の場を捉えて、自分の思いを言語化する習慣をつけていきたいと考えています。
読書の秋の到来です。古来より、花や月を歌に詠み、文章を表した日本人に思いを馳せながら、あまり読まないジャンルの本を開いてみたらいかがでしょうか。
和太鼓部フェスタ
他の部活動を中心に行っている生徒達、時間を見つけて練習を重ね、関宿中学校独特の伝統を繋いでくれています。
そんな生徒達の演奏を是非、是非ご覧下さい。
時 9月30日(土) 10:30開演
場 関宿中学校体育館
人権講演会
野田市人権・男女共同参画推進課の事業で3年に1度行われます。
講師はNPO法人ジェントルハートプロジェクトの小森 美登里さんです。
小森さんは、いじめが原因で自殺をした娘の事を中心にお話をされます。
人間が人間らしく生きる権利・いじめ・集団生活・人間関係づくりについて考える良い機会となることでしょう。
読書のススメ
読書のススメ
本日、期末テストが終わりました。生徒の皆さんいつもより多い家庭学習ご苦労様でした。試験はどうでしたか?と質問すると今ひとつ結果につながりませんでしたとの返答の人がいます。そこで、試験が終わった今、どのような学習をしたら自分を伸ばせるかを書きます。答えは「読書を勧めたい」です。読書をするとどんないいことがあるのでしょうか。
⑥つの効果について書いてみます。
①読書の習慣を身につけると、集中力が鍛えられていきます。
本を読むことは、自分をその本と対峙(たいじ)させることができ、本を読むと文章を書くスキルもアップすると思います。
本を読むと発想力が豊かになる
②読書することの効果の1つとして、発想力が豊かになるということが挙げられます。多岐にわたる専門書を読めば、それだけ発想の引き出しを増やすことに繋がりますし、物語やフィクションのジャンルの本を読むことによっても、現実とは違った見方を与える効果があると思います。
③本を読むと、今まで知らなかったことや考えたこともなかった知識に触れることが出来ます。そうすると、自分の枠組みから離れたアイデアが浮かんでくることがあります。自分一人で考えていたら一生思い付かなかったようなアイデアでも、読書をするだけで意外と簡単に浮かんでくることがあります。
④本を読むとコミュニケーション能力がアップする
読書をすることで、読み手が登場人物の気持ちを考えることで、他者理解・多様な価値観を享受することができます。
相手の感情を推し量ることができるようになりコミュニケーション力がアップする
読書をすることでコミュニケーション能力が上がると言われると違和感があるかもしれませんが、小説などの物語や著者の体験談などを読むことで人がどのように感情的な反応を示すかがわかり、言って良いこと悪いことや場面に適した言葉を書けることなどができるようになるでしょう。
また、自分ではなかなか考えつかない言葉での表現方法を見つけることができるので上手く感情を伝えられなくて悩んでいる人にも読書を是非おすすめしたいです。
物語性のある本の場合は、主人公や様々な人物も登場します。主人公や登場人物たちの動きを追い、気持ちに触れることで相手の考えや気持ちを察する力が身に付きます。
人の気持ちがわかるようになれば、人間関係の悩みを抱えている場合、自分だけではなく相手の立場になって物事を考えることもできるようになるでしょう。
⑤本を読むとやる気が出る
登場人物が自分の立場を全うしたり仕事や使命に打ち込む姿に共感して自分ももっと頑張ろうと努力することもあるでしょう。
本を読むと失敗を未然に防ぐ事が出来る
本というのは、先人たちの経験が集約されたものです。そこには、彼らの人生で得た教訓や過去に犯した失敗などが綴られているわけです。それを読むことで、私たちは同じ間違いをせずに済むことになります。
成功哲学の本を読めば、成功者がどのような考え方をしていたのかを知ることが出来ます。ビジネス本を読めば、事業を成功させるための秘訣を知ることができます。
⑥本を読むとストレス解消が出来る
ストレスの解消に繋がる
6分間の読書をすることでストレスは3分の1以下になるという研究結果があるそうです。これは、音楽を聞くことや運動をすることよりも高い効果
ストレスを解消したいとき、『音楽』『散歩』やその他の方法がありますが、一番のリラックス効果があるものは『読書』だそうです。