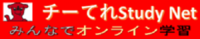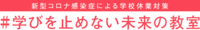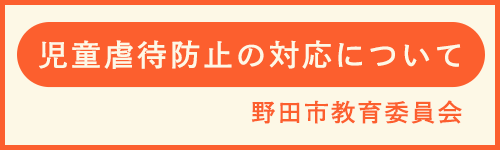今日の給食
10月17日(金)の給食です。
ガパオライス 目玉焼き スープビーフン フルーツカクテル 牛乳 です。
ガパオライスは、タイの名物料理の一つです。タイは年間の平均!気温が約29℃!!と、とても暑いため、食欲を増す唐辛子を使った辛い料理が多いことが特徴です。給食では、赤唐辛子の代わりにパプリカを使っているので安心です。タイの主食も「ごはん」ですが、日本人が普通に食べるお米と違う種類で一般的には「タイ米」と呼ばれる、細長い形のインディカ種というお米です。5年生がお米のことを学習しているので、質問すれば教えてくれるかもしれません。
ガパオライスの「ガパオ」とは、「ホーリーバジル」というハーブのことです。ひき肉や野菜などを、ホーリーバジルや唐辛子、魚を発酵させて作った「ナンプラー」という魚醤を使って味つけをして作ります。目玉焼きを乗せて食べると美味しいです!!
10月16日(木)の給食です。
ごはん いわしフライ 切り干しのナムル 豆腐の団子汁 りんご 牛乳 です。
「1⇒い、わ⇒0、し⇒4」という語呂合わせから、10月4日が「イワシの日」として制定されているそうです。少し遅くなりましたが、今日のめいんは「いわしフライ」でした。いわしは、漢字で書くと「魚へん」に「弱い」で、「鰯」と書きます。これは、他の魚のえさになることが多くて弱い、痛みも早いことから「弱し(よわし)」、等から転じたと言われていて、うろこがはがれやすいという特徴ももっています。DHAやEPAといった良質な脂が豊富で、血液をサラサラにする効果や脳の働きを活性化させる?効果があるらしいです。(いつも「お魚天国」という歌が頭をよごります)カルシウムやその吸収を助けるビタミンDも豊富で、栄養満点の青魚です。
今日のデザートのりんごは「秋映(あきばえ)」という長野県特産の品種です。小さ目で色は赤くありませんが、さわやかな香りと甘みが抜群でした。
10月15日(水)の給食です。
高野豆腐そぼろ丼 いなか汁 いそか和え 鬼まんじゅう 牛乳 です。
後期の給食が始まりました。栄養士の若松先生から、子どもたちへのメッセージを紹介します。「成長期の皆さんは、スポーツと勉強のどちらも大切です。体をよく動かすこと、たくさん学ぶことが、心と体の健康を保つことにつながります。限られた時間の中で、スポーツと勉強を両立させるためには。体力と気力が必要です。食事もトレーニングの一つです。早寝・早起き・朝ごはん!で、元気に朝のスタートを切り、食事で体と脳にエネルギーを補給しましょう」とのことです。
高野豆腐そぼろ丼は、見た目よりもさっぱりしていますが甘辛の味つけがごはんによく合っていました。いなか汁には、地域の方からいただいたバターナッツかぼちゃが使われています。デザートの「鬼まんじゅう」ですが、角切りにしたさつま芋の角がゴツゴツして見え、鬼の角や金棒がイメージされることから名前がついたそうです。「鬼」とついていますが、すっきりした優しい甘さとふわふわの食感で美味しいデザートでした。
10月9日(木)の給食です。
ごはん 高野豆腐のごまみそ和え 野田けんちん汁 シャインマスカット 牛乳 です。
高野豆腐は別名を「凍み(しみ)豆腐・または凍り(こおり)豆腐」と言い、昔の人の知恵で外で干して凍らせ、冬に食材で困らないように作られた保存食です。体を作るたんぱく質やカルシウム、貧血を防ぐ鉄分、お腹をきれいにする食物繊維などの栄養がとても豊富な食べ物です。今日は、揚げた高野豆腐にごま味噌だれをかけました。味がよく染み、また食感も面白く、とてもおいしくいただきました。野田けんちん汁には、野田市でとれた野菜がたっぷり入っています。そして、皮ごと食べられるとても甘いシャインマスカット。今日も、美味しくいただきました。
前期最後の給食です。栄養士さん、調理員さん、ありがとうございました。後期もよろしくお願いします。
10月8日(水)の給食です。
冷やしつけめん わかめのおにぎり 千草焼き オレンジ 牛乳 です。
今日のメインは「冷やしつけめん」です。冷たく締められためんを、スープにつけて食べます。のど越しよく、さっぱり食べることができました。わかめには、骨を丈夫にしてくれるカルシウムとミネラル分がたっぷりです。蒔いた海苔は、千葉県産です。学校の給食では、めん類(ラーメン、うどん、スパゲティ等)の時には、必ずご飯かパンも出されること、気づいていますか?千草焼きは、鶏肉と野菜、卵を使った焼き物のことです。「千草色」は、いろいろな色を混ぜた色なので、そこから名前を取った(いろいろな食材を使っているので)と言われています。デザートのオレンジ、牛乳と合わせて、今日も栄養バランスばっちりの美味しい給食でした。