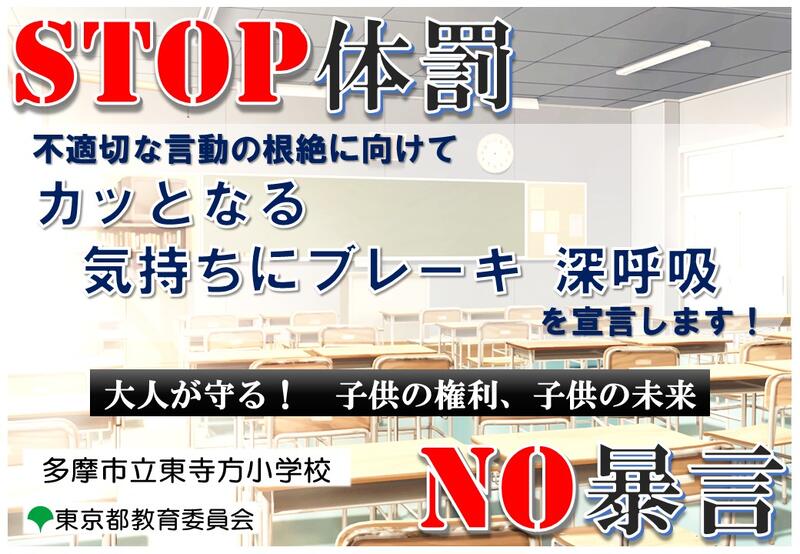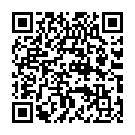今日は朝から雨が降り続き、校庭もぬかるみ、大栗川も水位が上がっています。下校時の注意として、川・水路に近付かない、傘をさして歩道を広がって歩かない、前をよく見て歩く等指導しました。今日で教育実習生の先生が実習終了となりました。一生懸命に子供たちとかかわっていただきました。教員不足が叫ばれる中ですが、こころざし通り子供たちを思いやる教師に育ってほしいと思います。保護者の皆様におかれましてもご理解ご協力ありがとうございました。今日から子ども未来塾「算数チャレンジ教室」が始まりました。該当のお子さんが頑張っています。応援します!