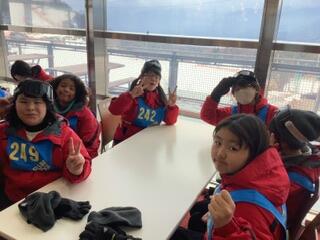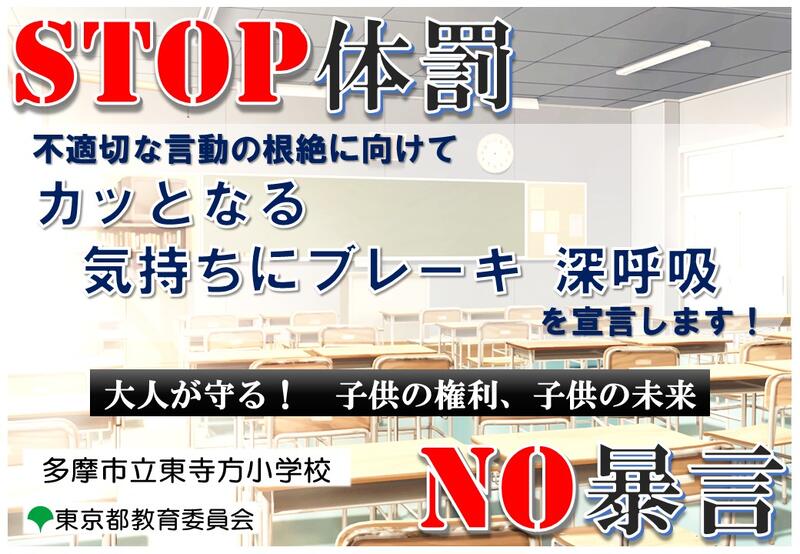6年生が移動教室に出発しました。雨の中ですが入笠山の湿原も散策できました。これから、夕食のカレー作りにとりかかります!
文字
背景
行間
今日の東寺方小
今日の東寺方小
2月16日5年生スキー教室リポート5
2日目が始まりました。
夜中は雷雨で心配しましたが、快晴です。
絶好のスキー日和です。
眠そうでしたが、朝会と朝食もスムーズに終えました。
次は掃除です。感謝の気持ちで「来た時よりも美しく」を目指して一生懸命掃除しました。
閉所式です。短い時間でしたがお世話になりました。
来年度もよろしくお願いします。
さあ2日目のスキー、スタートです。
5年生スキー教室リポート4
少年自然の家に到着。入所式です。
夕食です。協力して準備します。
お腹一杯食べました。
お土産も買えました。
1日の最後、室長会議です。
明日も早いです。おやすみなさい。
本日はこれで終了です。
5年生スキー教室リポート3
上達してきました。
2月15日5年生スキー教室リポート2
昼食です。
お腹が空いていたようで、おかわりする人がたくさんいました。おいしかったです!
2月15日 5年生スキー教室リポート1
富士見高原スキー場に到着しました。
いよいよレッスンが始まります。
代表の挨拶がとても素晴らしかったです。
カウンタ
2
9
8
0
3
5
9
令和4年度 体罰根絶宣言ポスター
東寺方小学校での体罰や不適切な言動の根絶を目指して、教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。
QRコード
携帯電話からもご覧になれます。
携帯のバーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。
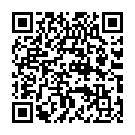
携帯のバーコードリーダー機能で
読み取ってご覧ください。
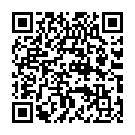
Googleアナリティクス利用について
お知らせ
台風等による臨時休業、登校時刻の変更等の対応に関する指針について.pdf
東京都公立学校教員採用ポータルサイト
https://www.kyoinsaiyopr.metro.tokyo.lg.jp/
「困ったときの相談場所」
厚生労働省 「まもろうよ こころ」
https://www.mhlw.go.jp/mamorouyokokoro/
「あなたのいばしょ」
https://talkme.jp/
ヨシタケシンスケさんの「かくれが」
https://kakurega.lifelink.or.jp/
暑さ指数