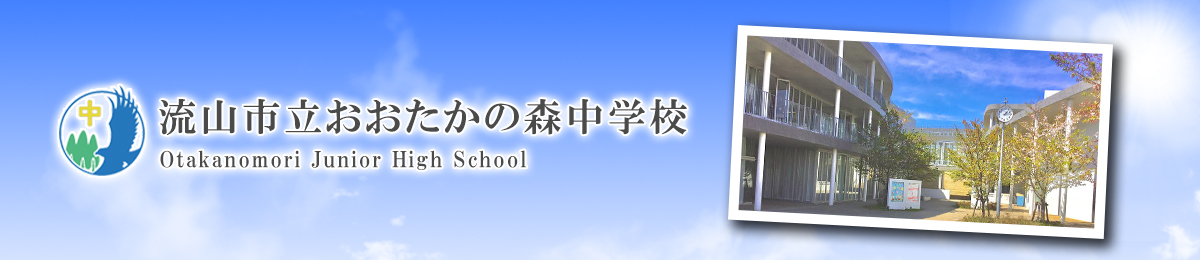令和7年度 給食の献立紹介
12月4日(木)の給食
『みそ豚丼、いも煮汁、フルーツのりんごゼリーあえ、牛乳』
みそ豚丼は、いつものしょうゆ味の豚丼をアレンジして、みそやにんにく、しょうがなどの香りがおいしいみそ味にしました。みそは、千葉県産を使っています。
みそは大豆を発酵したものです。みその発酵には、こうじ菌という菌が、大豆を細かく分解してくれる働きを使っています。
発酵食品には、乳酸菌などの体によい菌がたくさん含まれていて、病気に負けない強い体を作ってくれます。たくさん食べましょう。
12月3日(水)の給食
『コッペパン、ブルーベリージャム、コロッケ、チキンとマカロニのクリーム煮、牛乳』
給食室には、調理員さんが何人いるのか知っていますか?正解は24人です。朝6時から、大量の野菜を洗って、切って、おいしい給食づくりをして
くださっています。今日は、8時から11時すぎまで、3時間以上かけて2150人分のコロッケを揚げてくださっています。
すべてのメニューが、安心安全に、きれいに、おいしく作れるよう、たくさん工夫してくださっています。感謝の気持ちをもって、いただきましょう。
12月2日(火)の給食
『ご飯、のりふりかけ、肉豆腐、豆乳みそしる、牛乳』


給食は、安心・安全に作るために、さまざまな工夫をしています。
食中毒予防の三原則は、「菌をつけない、菌を増やさない、菌をやっつける」です。
つけない工夫は、手洗いや、使い捨て手袋などを使って、食べるものには直接触らないようにしています。
増やさない工夫は、温度管理です。冷蔵品は冷蔵庫、冷凍品は冷凍庫に入れて、菌が増えないようにしています。
やっつける工夫は、加熱です。焼いたり、煮たりして、高い温度で菌をやっつけるようにしています。
感謝の気持ちをもって、いただきましょう。
12月1日(月)の給食
『カレーピラフ、たらのみりんマスタードソースかけ、ABCトマトスープ、牛乳』

たらのみりんマスタードソースには、流山で作られているみりんを使って甘みをつけました。
まろやかな甘みを感じながら、食べてみましょう。
ABCトマトスープは、いつもはコンソメ味のABCスープを、トマト味にしてみました。野菜もたくさん入っているので、栄養満点です。
11月28日の給食
11月27日の給食
11月26日の給食
11月20日の給食
牛乳、ごはん、千葉県産いなだフライ、ひじきの炒り煮、千葉野菜たっぷり豚汁 です
皆さんは、地産地消という言葉を知っていますか?これは、地域で生産されたものをその地域で消費するという意味です。地元でとれた新鮮な食材を食べることで、食の安全や健康増進につながるという考えがあります。
今日の給食はまさに地産地消給食です!いなだという、ブリの子どものフライ、豚汁のぶた肉、にんじん、さつまいも、小松菜や、牛乳、ご飯もすべて千葉県産です。千葉県で生産されている豊かな食材に感謝して、今日もおいしくいただきましょう!
11月17日の給食
牛乳 マーボー豆腐丼
もずくと卵のスープ フルーツ杏仁 です
杏仁豆腐は中国で生まれたデザートです。「杏仁」という、杏の種の中にある核の部分を粉にして使い、砂糖や牛乳などと合わせて固めて作ります。杏仁豆腐の独特の香りや風味は、この杏仁の香りからきています。
今日の給食は、シロップに浮かべてフルーツを加えたフルーツ杏仁にしました。ピリ辛のマーボー豆腐を食べた後にもさっぱり食べられると思います。ぷるぷるの食感と杏仁の香りをぜひ楽しんでください!
11月14日の給食
『牛乳 ツナピラフ
デミグラスハンバーグ キャベツスープ』 です
デミグラスソースの「デミ」はフランス語で「半分」を意味する「demi(デミ)」からきています。また、「グラス」は「煮詰める」という意味の「glace(グラス)」から来ています。このため、「デミグラス」は「半分に煮詰めた」という意味になります。
今日のデミグラスハンバーグのソースは、赤ワインやケチャップ、ウスターソースを煮詰めて、ふっくら焼き上げたハンバーグにとろっとかけています。フランス料理の風味に近づけて炒るかどうか?!味わって食べてみてくださいね!