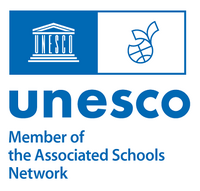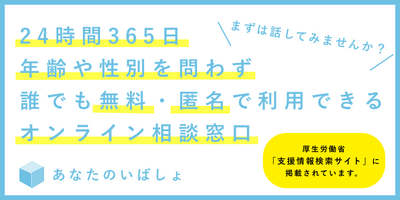文字
背景
行間
経 営 方 針
令和7年度 多摩市立東愛宕中学校 学校経営方針
校 長 竹田 和彦
本校は校内生活も落ち着き、人権尊重の精神を基盤として、生徒が集団の中でよりよい人間関係を築きながら、将来的によき社会人となることを目指す教育活動を行ってきた。
昨年度新設されたチャレンジクラスでは、それまで諸事情により、学校へ登校できなかった生徒たちが入級し、既存の学級との協力を経て、日々の学校生活を営んでいるところである。さらなる変化の激しい時代を生き抜く力を育成する為に、思いやりの心を醸成し、他者への理解を深めると共に、正解のない、答えが1つに定まらない諸課題に対して、一人一人が責任をもって自己の考えや思いを述べ、少しでもよりよい答えを協働的に見出していく姿勢を身に付けさせる教育活動を進める。また、多摩市公立学校研究奨励校で培った「教育のユニバーサルデザイン」(授業のUD化・教室環境のUD化・人的環境のUD化)を途絶える事なく継続実施させ、生徒の学力向上及び自己肯定感を高め、主体的に学習に取り組む態度を育成する。さらに、チャレンジスクール新設2年目にあたり、不登校出現率減少のための取組を工夫すると共に、そこで得た知見を活かし、すべての生徒が安心して学校生活を送れるよう、「誰一人取り残さない」教育を全校体制で実践する。
また、特別支援教室を活用した特別支援教育の充実をさらに進め、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を図っていく。
1 学校教育目標
義務教育の後半にあたる中学校教育の役割は、将来的に「よき社会人を育てる」ことの基礎段階と捉え、次の目標を設定する。
- 深く考えみずから学ぶ人
- 心ゆたかですこやかな人
- 自他を敬愛し協力する人
2 目指す学校像・生徒像・教師像
目指す学校像
「よき社会人を育てる学校」
東愛宕中学校は、社会人としての基盤を身に付けさせるために、教職員が地域・保護者及び関係諸機関と連携して教育活動に取り組み、将来社会を担う、「よき社会人」を育成する学校を目指す。
目指す生徒像
「誠実で、協調性があり、粘り強く困難に立ち向かう生徒」
誠 実 :自分に与えられたことを、全力で誠実にやり遂げる。
協調性 :他人と上手にコミュニケーションを取りながら、協力して物事を進めることができる。
粘り強さ:困難な課題に直面しても、諦めずに自分の力で切り開こうとする。
※「よき社会人」とは、誠実さ、協調性、粘り強さをバランス良く兼ね備えた人間と考える。
目指す教師像
生徒一人ひとりとしっかり向き合い、寄り添い愛情を注ぎ、生徒の輝くところに気付き、自己肯定感を高めさせることができる教師
3 学校教育目標達成のための具体的な方策
(1) 学習指導の充実のために(知育)
これからの時代に求められる資質・能力(育成すべき三つの資質・能力)
・何を知っているか、何ができるか(個別の知識・技能)
・知っていること・できることをどう使うか(思考力・判断力・表現力)
・どのように社会・世界と関わり、よりよい人生を送るか(学びに向かう力、人間性等)
授業改善の3つの視点
〈主体的な学び〉見通しと振り返り
・見通しをもって粘り強く取り組み、自らの学習活動を振り返って次につなげる主体的な学び。
※「教えてもらってわかった」ではなく「自分で考えてわかった」へ
教え込まれるのではなく、自分が主体的に動いて、頭を回転させ、自分の力で解決し、自分に必要なものを獲得させる(自分で考える癖をつけさせる)。
〈対話的な学び〉協働
・他者との協働や先哲の考え方を手掛かりに考えることを通じ、自己の考えを広げ深める学び。
※人と学ぶことの良さ(影響し合う・認め合う)に気付かせる。
〈深い学び〉習得・活用・探求
・今まで学習したことと比べたり分類したり関連付けて(見方・考え方)、より深く理解したり、考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりする学び。
上記を念頭に入れ、以下の取り組みを行う。
ア 基礎的・基本的な学習内容の確実な定着を図るとともに、各教科において一人1台タブレット端末等、ICTを活用した知識・技能の定着を図る活動を充実させる。さらに、各種学力調査及び各種体力・運動能力調査及び生徒の日々の学習状況の実態に基づいて授業改善推進プランを作成し、指導方法の工夫・改善を行い、授業のねらいに即して「何を学んだか、何ができるようになったのか、どのように学ぶのか」を振り返る活動を通して生徒が主体的に学ぶ態度を全校体制で育成する。
イ 思考力・判断力・表現力を高めるため、各教科等において、主体的・対話的で深い学び(アクティブラーニング)を効果的に実現する授業改善を充実させるとともに、校内外の研修を通して、ファシリテーター(生徒を主体的な学びに導く教師)としての技量を磨く。
ウ 授業内での評価方法の工夫に努め、十分な評価材料による指導と評価の一体化を図る。また、評価・評定方法や評価材等については各学期始めに生徒に説明し見通しをもたせる。
エ 生徒による授業評価を年間2回(1学期末・2学期末)行い、授業改善に活用する。
オ 国語科を中心に、全ての教科等において、生徒が各文章(教科書等)の内容をきちんと読み取れているかという視点をもって指導にあたり、生徒の読解力の向上を図る。
カ 習熟度別指導(数学科)では、個別の習熟の実態に沿った指導を行い、基礎学力の定着およびそれを活用した応用力の向上を図る。
キ 少人数指導(英語科)では、グローバル化の進展に伴い、国際共通語である英語によるコミュニケーション能力の向上を図るため、GTECおよびオンライン英会話を活用しながら、オールイングリッシュによる指導に取り組み、スピーキング力を高める。
ク 基礎学力定着のための取組として、次のことを実施する。
・地域未来塾(愛宕アカデミーによる毎週水曜日及び長期休業中の学習教室)
・放課後質問教室(定期考査前)
・学力補充教室(夏季休業中)
・各学期始業式復習テスト(漢字・英単語・計算等、主に5教科)
ケ 「2050年の大人づくり」を念頭に、SDGsの達成を目指したESD(持続可能な開発のための教育)を、地域や社会、人とのつながりに視点をもって推進し、ESDで重視する下記の能力・態度の育成を図ると共に、ESDカレンダーの充実を目指し、課題解決的・目標達成的学習実践を積み重ねる。
*批判的に考える力
*未来像を予測して計画を立てる力
*多面的・総合的に考える力
*コミュニケーションを行う力
*他者と協力する力
*つながりを尊重する態度
*進んで参加する態度
コ 学校図書館司書を中心に、学校図書館を整備・有効活用し、読書教育に力を入れるとともに、毎朝の朝読書を全校体制で実施し、読書に親しむ態度を育てる。
サ 家庭学習習慣の定着を図るため、各教科等で、質・量共に生徒の実態に合わせた課題及び取り組みやすく達成感が得られる課題を提示する。
シ 各種検定(英語科・PTAによる英検、国語科・PTAによる漢検)を設定し、学習意欲を高める。
ス ICTを有効活用した学習指導の充実を図るために、一人1台タブレット端末を活用した指導力の向上を図り、「個別最適な学び」と「協働的な学び」の一体的な充実を通して、情報活用能力を育成する。
(2)豊かな心を育てるために(徳育)
ア 「特別の教科道徳」において、道徳教育推進教師を中心に、「考え、議論する道徳」教育の推進へ向けた指導の工夫を図るとともに、5月・12月にオンラインを活用した全校道徳を実施し、自分の生き方について考えを深めさせ、思いやりの心、規範意識等の道徳的価値観を全校規模で高める。
イ 特別活動(学級活動・生徒会活動・学校事)及び部活動において、有意義な教育活動を積極的に行い、自主自律を目指し、役割と責任の自覚、相互理解、協力について学び、よりよい人間関係づくりができる力を育成するとともに、自尊感情、自己肯定感を高める。
ウ 「学校2020レガシー」として地域行事参加や校内外学習を通してボランティアマインドなどの資質を高め、協力しながら物事を進めることができる「協調性」を育む。
エ 道徳授業地区公開講座の公開授業及び意見交換会を通して、学校・家庭・地域が連携した道徳教育を推進する。
オ ふれあい月間等を使って、いじめに関する指導・啓発を折に触れて実施し、全校体制でいじめを許さない風土を教職員及び全校生徒でつくりあげる。
カ SNS東京ルール及びSNS東愛宕中ルールの見直し及び更新を行うとともに、生徒への指導及び保護者に対する啓発活動を行い、学校と家庭が連携して、生徒の適切な情報機器の使用を指導する。
キ 特別支援教育コーディネーターを要とし、特別支援教育校内委員会の機能を向上させ、スクールカウンセラー及び外部機関と連携を図りながら、不登校等の学校不適応及び自殺防止等について早期の対応を心掛ける。
(3)健やかな体を育てるために(体育)
ア オリンピック・パラリンピック精神を継続させる授業や体験活動を、家庭・地域社会・外部人材の協力を得ながら実践し、体力向上・健康増進を進めると共に、スポーツへの関心を高めさせ何事にも挑戦する意欲と協調性を育む。
イ 保健体育の授業において、毎回補強運動を取り入れることにより、基礎体力の向上を図る。
ウ 体育的行事において、運動に対する興味・関心を高め、生涯にわたり体を動かすことが好きな生徒を育成すると共に、思いやりや協力して責任を果たす態度を身に付けさせる。
エ 部活動(運動部)への参加を奨励し、体力の向上を図ると共に、粘り強く1つのことに打ち込むことの大切さ、協調性、礼儀作法等を養う。
オ 養護教諭及び外部講師を招聘した健康教育・食育教育を行い、健康な体づくりへの意識を高める。
カ 防火・防災・不審者等を想定した避難訓練、交通安全等の安全指導、防災デイキャンプ、セーフティ教室を通して、自己の生命・安全を自ら守ろうとする態度や危機回避能力を身に付けさせる。
(4)秩序ある学校生活を送らせるために(生活指導)
ア 特別支援教育校内委員会及び生活指導部会を中心とした校内の組織的な教育相談体制を整えると共に、スクールカウンセラー等の外部機関との連携を深め、不登校生徒8%未満(前年度12.4%)を目標とする。また、別室登校・学習生徒の学習環境の整備を進める。
イ 不登校対応校内分教室「あたごSpace」に入級する不登校生徒が安心して学校生活が送ることができるよう、全職員で支援すると共に、全校生徒に対して思いやりの心を醸成し、他者への理解を深める指導を継続する。
ウ 生徒の実態を把握し、生徒理解に基づく生活指導を実践し、生徒一人ひとりと最後までかかわり続け、見通しをもって組織で育てる。
エ 常に全教職員で一人の生徒を育てるという意識をもち、報告・連絡・相談を密にして、早期発見、早期対応、誠実な対応に努め、有事の際は学級・学年の枠を超えて全教職員で組織的に対応する。指導の場面は、必ず複数で対応する。
オ いじめ防止対策委員会を中心に、未然防止、早期発見に努め、いじめが確認されたときは早期に対応し、その解決に努める。また、また、「いじめは許さない」という認識を維持し、SOSを発信しやすい教育相談体制を整えると共に、いじめや差別に対しては人権に配慮した指導を心がける。
カ 生活環境の整備に努めると共に、成果物などの掲示は綺麗に、かつ人権に配慮して掲示する。
キ 「挨拶」「5分前行動」「整理・整頓」の3つに具体的に焦点化し、生徒に達成感をもたせる。
ク 暴力行為、器物破損行為、違法行為等には厳しい姿勢で指導する。
ケ 防災・安全教育は『防災ノート 』『東京マイ・タイムライン』などを利用して充実に努めるとともに、様々な場面を想定した実践的訓練を行う。
(5)キャリア教育を充実させるために(進路指導)
ア 3年間を見据えた進路指導計画に基づき、卒業後の進路、将来の生き方について主体的に目標がもてるように指導する。
イ SDGsの達成を目指したESDの視点を踏まえた職業調べ・職場体験・上級学校調べなどの体験学習や課題解決学習を積極的に取り入れ、自身を振り返させるとともに将来への展望をもたせ、生きる力を育む。
ウ 生徒・保護者の進路希望を受け止め、実現のための道筋を丁寧に指導する。日ごろから生徒の考えを理解するための関わりをする。
エ 愛宕アカデミーを中心に取り組む養蜂活動は起業体験と捉え、キャリア教育の一環として生徒の参加を積極的に募る。
オ キャリアパスポートを活用した自己評価の取組を年間3回以上実施し、振り返りと改善を通して将来の見通しをもたせ、あわせて生徒の汎用的活用能力の育成を図る。
(6)個の理解及び具体的支援(特別支援教育)
ア 特別支援教育コーディネーターを中心として、学級担任、スクールカウンセラー、巡回心理士、こども家庭支援員等との連携を密に行い、個に応じた特別支援を組織的に実践し、全ての生徒が、所属する学級の中で充実した学習活動及び学校生活に適応できるよう、指導の充実を図る。
イ ユニバーサルデザインを意識した授業、学習環境を工夫する。特に教室掲示は、前面への掲示をなくし、できるだけ簡素にする。
ウ 「学校生活支援シート」「個別指導計画」をもとに、具体的に見える支援を継続して進めていく。
エ 外部機関・外部人材の積極的かつ有効活用を図る。
オ 特別支援教育コーディネーターを要として、学級担任、巡回指導教員、特別支援教室専門員、心理士等の連携を密に行い、全ての児童が、所属する学級の中で充実した学習活動及び学校生活に適応できるよう、指導の充実を図る。
(7)学年・学級経営について
行事にとどまらず、日常の活動を通して学年・学級のリーダー・サブリーダーを育成する。また、小規模校であることを生かし、各学年の実態を踏まえつつ、学校経営方針を柱とした、3年間を見通した教育計画を全教職員が一体となって推進する。
ア 学年経営
・学年経営方針のもと、年間を見通した計画的かつ組織的な経営を行う。
・各学級の実態を大切にしつつ、学級差のないように、学年で決定した方針に基づき経営を行う。
・担任を学年全体で支え合う体制を心がける。
・学年会の運営では各担当が責任をもって計画的に提案し、効率よく行いながら、OJTの場とするとともに、他学年との連携・情報共有を行う。
イ 学級経営
・学級経営方針を生徒に簡潔に示し、生徒とともにその達成を目指す。
・生徒の実態を把握し、目標と方針・方策を立て、計画的な学級経営に努める。
・教師と生徒の信頼関係のもと、一人ひとりが生きる学級経営を工夫する。
・一人ひとりの生徒を公平に認め、寄り添い、見届ける。
・軽微な課題を見逃さず、初期対応を重視するとともに、学年及び生活指導部での情報共有を徹底し、指導の方向性を確認しながら対応する。
4 保護者・地域等との連携および教育公務員の責務
(1) 学校運営協議会(コミュニティスクール)・地域学校協働本部
学校運営協議会(コミュニティスクール)、地域学校協働本部と協働し、地域・保護者及び関係諸機関と連携して、教育のねらい・目標を保護者・地域と共有し、一体となって子どもを育てる地域の学校を目指す。
(2)教育公務員として、次のことを念頭において、自身の教育活動に取り組む。
- その取組は、生徒の成長につながるものか。
- その取組は、生徒、保護者の願いなのか。
- その取組は、地域や社会全体の期待に合致しているか。
- その取組は、全体の奉仕者である公立学校の教職員として、また教育公務員として適正であるか。
- その取組は、教職員にとって資質の向上に寄与するものか。
(3)組織人としての責任感、協調性、規範意識など相互啓発に努め、東愛宕中学校の組織を構成する職員としての誇りと責任をもつ。
- 法令を遵守し、公平・公正で服務に厳正な職員
- 教育に対する熱意と使命感をもつ職員
- 豊かな人間性と思いやりのある職員
- 組織人としての責任感、協調性を有し、互いに高め合う職員
- 教育者として学び続ける職員
- 明るく、元気で、笑顔を絶やさない職員
(4) 教育公務員には研修と修養の義務がある。研修の機会には積極的に参加し、ライフステージに応じ各々の資質・能力の向上を図る。また、日々の学級・学年・分掌等の教育実践の中で意識的にOJTを行うと共に、教職員が相互に授業を見せ合い、意見交換できる場や雰囲気をつくり、ベテランと若手双方が互いに高め合う。
(5)保護者・地域の教育力を生かした教育実践を展開し、様々な地域行事への参画を促すことで、生徒の社会性や郷土愛を育ませ、地域に貢献できる生徒を育てる。
地域学校協働活動推進員・地域学校協働本部・多摩市青少年問題協議会・近隣大学(国士舘大学 明星大学 帝京大学 中央大学)・小・中連携(第三小 愛和小)・PTA 等
(6)放課後学習教室(愛宕アカデミー)を水曜日に、夏休み学習倶楽部を7月最終週から8月初週にかけた月~金曜日の5日間に渡り実施し、生徒に学習の場を提供し、基礎学力の定着を図る。ここでは、教職志望の大学生等を支援員として活用し、支援員の研修の場としての配慮をする。また、養蜂活動を通して関心のある生徒に社会参画の機会を工夫していく。
(7)学期1回以上の学校公開及び学校だより、学年だより、学級だより、学校ホームページ等で情報発信を行うことにより、保護者・地域に対する説明責任を果たし、信頼される学校を築き上げる。