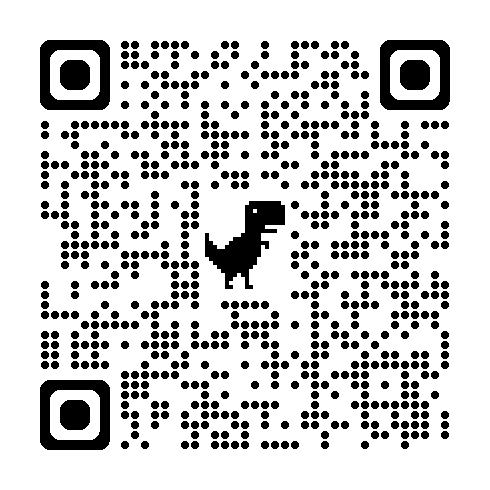文字
背景
行間
◆学校林での活動や学校林・学校の自然
2018年2月の記事一覧
学校林活用・再生プロジェクト委員会
2月17日、学校林活用・再生プロジェクト委員会を開催しました。
現場を見ながら、多摩市グリーンライブセンターの職員や樹木医の専門家のご意見を聞き
今後の学校林の中・長期的な管理の方向性を検討しました。

アスレチックゾーン
大木が枯れたり倒れたりしたために、中央斜面に樹木がなくなっている。
2年前、多摩市産ヤマザクラを6本移植した。
残りの樹木はすべて大きくなりすぎている。
下草刈りは継続する。
実験ゾーンから実生のコナラを移植して育成する。

以前、恐怖の階段があった下のくぼ地は落ち葉を貯めて表土を再生する。
アスレチックゾーンの南下の部分(ブランコとフェンスの間)に土を入れ
その上に落ち葉を貯めておくことで多摩市産カブトムシを養殖したい。
カブトムシは典型的な里山の昆虫。人間の手が入る里山で多く繁殖できる。
アスレチックゾーンと雑木林ゾーン(実験ゾーン)の間の坂は階段を設置して
古いくもの巣のロープは撤去する。
雑木林ゾーン
実験ゾーン(雑木林ゾーンの東端)
大きな木を伐採して明るくしてきた。
今年度もクロマツをすべて伐採し、より明るくなった。
状況はとてもいい。
あと、下方に常緑樹のシラカシが1本残っているので伐採したい。
実生からのコナラが育ってきている。
コナラ以外の常緑の苗や萌芽した常緑樹の枝は切る。
下草刈りをし、コナラを間伐しながら育てていく。

実験ゾーン西続きの雑木林ゾーン
将来的には、
実験ゾーンから順に西へ伐採していき、実験ゾーンを西に拡張しながら
実生の雑木を育てていきたい。
下草刈りを継続する。
雑木林ゾーン西端のタマノカンアオイ自生地周辺は
このまま日陰になるようにする。
タマノカンアオイ自生地から校庭方向の斜面への立ち入りは今後も禁止する。
多様腫ゾーン・シイタケ小屋付近
常緑樹をだいぶ伐採してきたが、まだ暗い。
シイタケ栽培をしているので、明るくする必要はないが
シラカシの大木を間引く。
学校林西端の旧松林の急斜面
松が枯れて、木の根の張りがなくなった。今後崩落の危険性が増大する。
市に対策を依頼するが、植林すれば20年30年すると伐採・剪定の管理が必要となり
膨大な予算がかかる。
引き続き立ち入りは禁止。
子どもが進入しないように、粗朶(そだ)で区域を区切ることも検討する。
現場を見ながら、多摩市グリーンライブセンターの職員や樹木医の専門家のご意見を聞き
今後の学校林の中・長期的な管理の方向性を検討しました。

アスレチックゾーン
大木が枯れたり倒れたりしたために、中央斜面に樹木がなくなっている。
2年前、多摩市産ヤマザクラを6本移植した。
残りの樹木はすべて大きくなりすぎている。
下草刈りは継続する。
実験ゾーンから実生のコナラを移植して育成する。

以前、恐怖の階段があった下のくぼ地は落ち葉を貯めて表土を再生する。
アスレチックゾーンの南下の部分(ブランコとフェンスの間)に土を入れ
その上に落ち葉を貯めておくことで多摩市産カブトムシを養殖したい。
カブトムシは典型的な里山の昆虫。人間の手が入る里山で多く繁殖できる。
アスレチックゾーンと雑木林ゾーン(実験ゾーン)の間の坂は階段を設置して
古いくもの巣のロープは撤去する。
雑木林ゾーン
実験ゾーン(雑木林ゾーンの東端)
大きな木を伐採して明るくしてきた。
今年度もクロマツをすべて伐採し、より明るくなった。
状況はとてもいい。
あと、下方に常緑樹のシラカシが1本残っているので伐採したい。
実生からのコナラが育ってきている。
コナラ以外の常緑の苗や萌芽した常緑樹の枝は切る。
下草刈りをし、コナラを間伐しながら育てていく。

実験ゾーン西続きの雑木林ゾーン
将来的には、
実験ゾーンから順に西へ伐採していき、実験ゾーンを西に拡張しながら
実生の雑木を育てていきたい。
下草刈りを継続する。
雑木林ゾーン西端のタマノカンアオイ自生地周辺は
このまま日陰になるようにする。
タマノカンアオイ自生地から校庭方向の斜面への立ち入りは今後も禁止する。
多様腫ゾーン・シイタケ小屋付近
常緑樹をだいぶ伐採してきたが、まだ暗い。
シイタケ栽培をしているので、明るくする必要はないが
シラカシの大木を間引く。
学校林西端の旧松林の急斜面
松が枯れて、木の根の張りがなくなった。今後崩落の危険性が増大する。
市に対策を依頼するが、植林すれば20年30年すると伐採・剪定の管理が必要となり
膨大な予算がかかる。
引き続き立ち入りは禁止。
子どもが進入しないように、粗朶(そだ)で区域を区切ることも検討する。
皆既月食
1月31日。今月2回目の満月「ブルームーン」が皆既月食で赤銅色の月になりました。
下は本校職員が撮った写真です。
皆既月食は地球の影に月が入るので、日食のように黒く見えそうですが、
実際は、太陽の光が地球の大気で屈折して、赤い光が影の中に入ってしまうために
赤銅色の月になります。
大気の状況によって見える色はオレンジぼかったり黄色っぽかったりして、色が違って見え、
その時になってみないとどのような色に見えるか分からないようです。

下は本校職員が撮った写真です。
皆既月食は地球の影に月が入るので、日食のように黒く見えそうですが、
実際は、太陽の光が地球の大気で屈折して、赤い光が影の中に入ってしまうために
赤銅色の月になります。
大気の状況によって見える色はオレンジぼかったり黄色っぽかったりして、色が違って見え、
その時になってみないとどのような色に見えるか分からないようです。

☆ 連絡・手続き等
服務事故防止ポスター
豊ヶ丘小学校では、服務事故の根絶を目指して教職員でスローガンを定め、ここに宣言します。職員室前に掲示してあります。
☆ 学習支援コーナー
●学習支援サイトのリンク集
NHK for School
ミライシード(アプリ版東京ベーシックドリル)
東京ベーシック・ドリル(東京都教育委員会)
☆ カウンター
1
4
8
6
0
0
2