文字
背景
行間
日々の様子
4年生 多摩川下流河口体験
4年生が「総合的な学習の時間」で取り組んでいる多摩川。
学習のフィールドは、関戸橋付近です。これは多摩川でいうと、中流に当たります。
学習を深めていく上で、上流や下流の多摩川はどのような様子なのか、どんな生態系なのか、そういった比較的な学習が必要になってきます。
毎年、河川財団から学習支援のための補助金をいただいているのですが、そこからバス代を補助し、数年前から上流と下流にも見学・体験に出かけています。
昨日は、下流に出かけました。
目的地は川崎市にある大師河原干潟館です。
多摩川に架かる橋、六郷橋(箱根駅伝でも走る第一京浜<R15>の橋です)から大師橋の間にある施設です。
この六郷橋から大師橋にかけては、多摩川両岸(川崎市側・大田区側)に干潟が広範囲にあります。
私が20年以上前に羽田の小学校に勤めていた時には、よく土曜日の4時間目に学級レクレーションで多摩川の河原で遊びましたが、当時干潟はありませんでした。
大師橋が2006年に改築された際、新しい橋脚になったので、その影響でしょうか。
干潟館の方ともそんな話をしましたが、真偽のほどはわかりません。
天気が心配されましたが、干潟館につくときには雨は上がり、携帯で雨雲レーダーの動きを見ると、しばらくはレインコートなしで活動できそうです。
身支度をして、干潟館に荷物を置き、大師橋の下の干潟まで向かいます。

今日は大潮の日です。
そして今が干潮の時刻。一番干潟が見えている時間帯に観察です。
まずはかわいい水鳥たちの足跡がお出迎え。

干潟館にたも網やシャベルなどを借り、どんな生き物がいるのか調査開始です。




前回の学習で、川の中に入って生き物を探したガサガサを体験しているだけに、この日は水の中に入っていく抵抗感は全くなし(笑)。
いや、正確に言うならば、長靴の中に水が入る抵抗感なし!
気持ちの良いくらい、長靴の水深を気にせず活動しています。
時折足を上げて、長靴の中の水を出しながら活動が続きます。

見つかったのはこんな生き物たち。

タボハゼ、マハゼ、クロベンケイガニ、ヤマトオサガニ、チゴガニ、ケフサイソガニなどが採取できました。
調査の終わりは、干潟館の方からの総括です。

そして、最後は自然保護という大切な視点から、トロ船に入っていた採取した生き物たちを干潟に放ちます。
誰一人として、「持って帰りたい」と言わなかったところが、さすが連小の子供たち。

昼食をとり、次は大森海苔のふるさと館に向かいます。
大田区大森は多摩川河口の海の町です。
そして、1964東京オリンピックまでは海苔の養殖が盛んでした。
その歴史を後世に伝えるために2008年に創設されたのがこの施設です。
あわせて、大森海岸の白砂の砂浜も復活させました。
多摩川の豊かな恵みがあってこそ、大森の海苔は、質、量ともに江戸随一と言われました。
館内見学と河口の海の見学です。
「海苔」の歴史にも、子供たちは教員の予想を上回る関心を見せ、熱心に見入っていました。
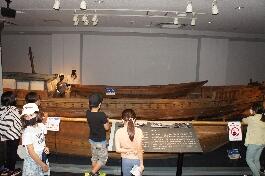


学習のフィールドは、関戸橋付近です。これは多摩川でいうと、中流に当たります。
学習を深めていく上で、上流や下流の多摩川はどのような様子なのか、どんな生態系なのか、そういった比較的な学習が必要になってきます。
毎年、河川財団から学習支援のための補助金をいただいているのですが、そこからバス代を補助し、数年前から上流と下流にも見学・体験に出かけています。
昨日は、下流に出かけました。
目的地は川崎市にある大師河原干潟館です。
多摩川に架かる橋、六郷橋(箱根駅伝でも走る第一京浜<R15>の橋です)から大師橋の間にある施設です。
この六郷橋から大師橋にかけては、多摩川両岸(川崎市側・大田区側)に干潟が広範囲にあります。
私が20年以上前に羽田の小学校に勤めていた時には、よく土曜日の4時間目に学級レクレーションで多摩川の河原で遊びましたが、当時干潟はありませんでした。
大師橋が2006年に改築された際、新しい橋脚になったので、その影響でしょうか。
干潟館の方ともそんな話をしましたが、真偽のほどはわかりません。
天気が心配されましたが、干潟館につくときには雨は上がり、携帯で雨雲レーダーの動きを見ると、しばらくはレインコートなしで活動できそうです。
身支度をして、干潟館に荷物を置き、大師橋の下の干潟まで向かいます。

今日は大潮の日です。
そして今が干潮の時刻。一番干潟が見えている時間帯に観察です。
まずはかわいい水鳥たちの足跡がお出迎え。

干潟館にたも網やシャベルなどを借り、どんな生き物がいるのか調査開始です。




前回の学習で、川の中に入って生き物を探したガサガサを体験しているだけに、この日は水の中に入っていく抵抗感は全くなし(笑)。
いや、正確に言うならば、長靴の中に水が入る抵抗感なし!
気持ちの良いくらい、長靴の水深を気にせず活動しています。
時折足を上げて、長靴の中の水を出しながら活動が続きます。

見つかったのはこんな生き物たち。

タボハゼ、マハゼ、クロベンケイガニ、ヤマトオサガニ、チゴガニ、ケフサイソガニなどが採取できました。
調査の終わりは、干潟館の方からの総括です。

そして、最後は自然保護という大切な視点から、トロ船に入っていた採取した生き物たちを干潟に放ちます。
誰一人として、「持って帰りたい」と言わなかったところが、さすが連小の子供たち。

昼食をとり、次は大森海苔のふるさと館に向かいます。
大田区大森は多摩川河口の海の町です。
そして、1964東京オリンピックまでは海苔の養殖が盛んでした。
その歴史を後世に伝えるために2008年に創設されたのがこの施設です。
あわせて、大森海岸の白砂の砂浜も復活させました。
多摩川の豊かな恵みがあってこそ、大森の海苔は、質、量ともに江戸随一と言われました。
館内見学と河口の海の見学です。
「海苔」の歴史にも、子供たちは教員の予想を上回る関心を見せ、熱心に見入っていました。
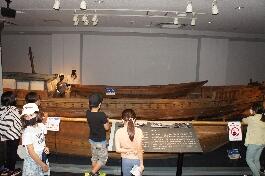


連絡・手続き等
★インフルエンザ、コロナ、手足口病、リンゴ病、ヘルパンギーナに感染し、治癒した際には「学校感染症治癒届」をご提出ください。
ダウンロードして印刷してご記入くださるか、用紙を学校からもらってください。
★土日祝日、平日夜間に学校への連絡が必要になった場合は、
多摩市庁舎管理室 042-338-6855にご連絡ください。
庁舎管理員が状況を聞き、学校に連絡を取ります。
★保護者向け相談窓口一覧
★悩みを抱え込まないで!★
24時間365日、誰でも無料・匿名
あなたのいばしょチャット相談
★18さいまでのチャイルドライン
子ども専用のダイヤルです。困っていること、悩んでいること、誰かと話したいとき、あなたの気持ちを大切にどんなことでもいっしょに考えます。
0120-99-7777 (NPO法人チャイルドライン支援センター)
★こどもSOS~こんなことでなやんでいたられんらくしてください
・いやなことをされる
・ひどいことを言われる
・ごはんを食べさせてもらえない
・かぞくのせわをしていて、じぶんのやりたいことができない
多摩市子ども家庭支援センター 042-355-3777 (月~土 9:00~18:00)
東京都多摩児童相談所 042-372-5600 (月~金 9:00~17:00)
児童相談所全国共通ダイヤル 189 (365日24時間)
★こどもの人権110番
なやみを一人でかかえないで相談できます
0120-007-1100 (月~金 8:15~17:15)
PTA作成 地域安全マップ
川の学習のボランティアをしてみませんか?
オンライン関係
スマートフォンからですと全画面を表示することができません
タブレットかPCでご利用ください
ロイロノート・ログイン
学校IDは「renkouji」と入力
★保護者用Googlemeetのつなぎ方.pdf
保護者会で使用するGoogle Meetの接続方法
★Wi-Fi接続方法.pdf
簡易なWi‐Fiへの接続方法
カウンタ
5
6
5
2
0
3
3



