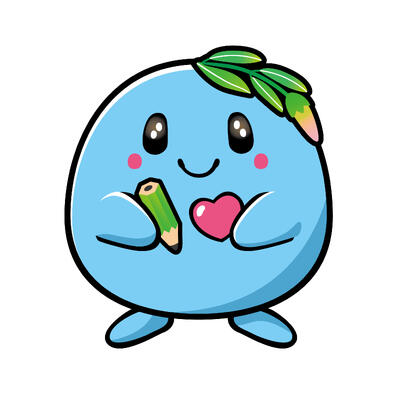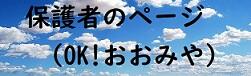文字
背景
行間
日誌
研究授業
1月21日(火)、3時間めに1年生、4時間めに2年生、5時間めに6年生、6時間めに5年生が、算数の研究授業をしました。東京家政大学の石田教授をお招きして、T2として授業に参加していただきました。指導者は授業者を指導するので参観しているのが多いのですが、石田教授の場合は実際の授業に参加します。授業が終わってから指導を受けるのでなく、授業中に指導を受けます。そのことによって、子どもたちの影響を最小限にします。石田教授は、たくさんのビデオカメラを用意し、それぞれの班で話し合っていることを撮影します。特徴的な解決方法を話し合った班は、映像から児童の話した言葉を文字に変換し、授業記録にします。大変な作業です。
石田教授の学びあいは、わからないことをわからないままにせず、助け合って答えを導いたり、創り上げたりする活動です。一般的なグループでの話し合いだと、ずっと発言しない子がいたりするものです。また、グループでの話し合いといっても、一人一人の意見の発表になって終わってしまい、その発言に質問をしたり、反対意見を言ったり、意見を統合させたりしないことが多いものです。しかし、石田教授の学びあいは、従来ありがちな話し合いのスタイルを変えるものでした。「みんなそれぞれが素晴らしい考えをもっているので発表しよう。」とか、「せっかくの45分(授業)なのに、なぜわからないままにするのか。わかる人がわからない人に教えればいいのではないか。」などと、人権尊重の考え方も学びあいに含まれているようです。
どのクラスも、石田教授の学びあいを展開していました。石田教授は、「大宮いいね。」とほめてくださいました。ありがたいことです。教職員ががんばったおかげです。もちろん、子どもたちもたくさんのカメラに囲まれながらも、がんばっていました。
石田教授をはじめ、学力向上推進リーダーなど、大宮小を支えていただけるのはありがたいことです。


↑ 1年算数「おなじかずずつ」


↑ 2年生も「おなじかずずつ」ですが、かけ算の考え方を使うのが1年生と違うところです。


↑ 5年生「比べ方を考えよう」


↑ 6年「資料の特ちょうを調べよう」

↑ 授業研究会

石田教授の学びあいは、わからないことをわからないままにせず、助け合って答えを導いたり、創り上げたりする活動です。一般的なグループでの話し合いだと、ずっと発言しない子がいたりするものです。また、グループでの話し合いといっても、一人一人の意見の発表になって終わってしまい、その発言に質問をしたり、反対意見を言ったり、意見を統合させたりしないことが多いものです。しかし、石田教授の学びあいは、従来ありがちな話し合いのスタイルを変えるものでした。「みんなそれぞれが素晴らしい考えをもっているので発表しよう。」とか、「せっかくの45分(授業)なのに、なぜわからないままにするのか。わかる人がわからない人に教えればいいのではないか。」などと、人権尊重の考え方も学びあいに含まれているようです。
どのクラスも、石田教授の学びあいを展開していました。石田教授は、「大宮いいね。」とほめてくださいました。ありがたいことです。教職員ががんばったおかげです。もちろん、子どもたちもたくさんのカメラに囲まれながらも、がんばっていました。
石田教授をはじめ、学力向上推進リーダーなど、大宮小を支えていただけるのはありがたいことです。


↑ 1年算数「おなじかずずつ」


↑ 2年生も「おなじかずずつ」ですが、かけ算の考え方を使うのが1年生と違うところです。


↑ 5年生「比べ方を考えよう」


↑ 6年「資料の特ちょうを調べよう」

↑ 授業研究会

お知らせ
創立150周年記念
マスコットキャラクター
「おーみー」
ダウンロード書類
欠席・遅刻・早退届.pdf
↑トラブル防止のため、できるだけ書類による連絡をお願いします。
学校感染症に関する登校申出書.pdf
出席停止(新型コロナ、インフルエンザ等)後、再登校する際に提出してもらうものです。医師の証明等は必要ありません。
リンク
カウンタ
2
1
7
6
3
5
3