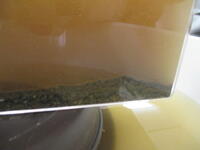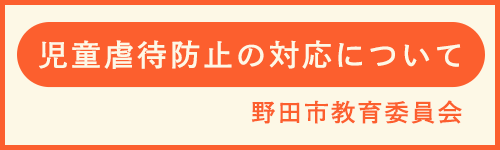6年わくわく理科授業
令和5年11月16日(木)、6年生が東京理科大学の関先生を講師にお招きして「わくわく理科授業」を実施しました。
理科の授業で行っている地層のでき方について、実験を通して学びを深めることができました。
まず始めは、大きさの違うガラス球を同時に水の中に落とすと、どうなるかの実験です。
大きなガラス球の方が速く沈んでいきました。
同じ大きさの鉛球とガラス球で比べると、より重い鉛球の方が速く沈んでいきます。
このことから、粒の大きなものから速く沈み、大きさが同じ場合はより重いものから速く沈むことがわかりました。
次に、粒の大きさの違う砂を混ぜて水の中に入れると、どうなるかを実験しました。
最後に、川砂を流して地層を作る実験を行いました。
目の粗い砂が下の方に、細かい砂が上の方にたまっています。
同じことを3回繰り返すと、きれいな層が見えてきました。
今回の学習を通して、流れる水の働きで学習した浸食、運搬、堆積の運搬から堆積する様子がよくわかりました。
普通に実験しても、はっきりと地層が出てこないことが多い実験なのですが、実験用具に様々な工夫がされており、どの班も地層がくっきり現れていました。
大学で地学を専門に教えている先生の授業を受けることができ、理科に興味をもった児童も多いのではないでしょうか。