特別棟の耐震工事 矢板の歴史小話
特別棟の耐震工事が始まります。
特別棟は、理科室や音楽室、図書室などの特別教室がある矢板小学校の東側にある校舎です。
特別棟は、昭和46年に竣工されたので、できてからもう40年以上の年数が経ちます。
老朽化もしているので、今回耐震工事をすることになりました。
工事のために、先週特別棟の周囲に植えられてある植木を新校舎後ろとプールの西側に移植しました。
↓植え木が移植されてきれいになった特別棟周辺


↓中庭に移植しました。

以下、耐震工事の日程です。
6月23日(土) 植え木移植(新校舎後ろとプール西側に)
7月13日(金)~7月15日(日) 仮囲い工事及び鉄板敷き
7月21(土)~8月26日(日) 特別棟工事及び外階段解体・取り付け
9月1日(土)~9月7日(金) 内装及び外壁仕上げ
・現時点では教育研究所の駐車場は使用できます。
・7月21日(土)~8月2日(木)までは、解体工事により騒音が予想されますので、1~3年学年の個人懇談は自教室ではなく管理棟で行います。(個人懇談の日程や場所については、来週配付します)
【矢板小学校の特別棟がある場所は、むかーしむかし・・・】
昨日、今日と特別棟北側のアジサイや特別棟の耐震工事についてなど、「特別棟」に関連した記事を掲載しました。
なので、今回は矢板小学校の特別棟にちなんだ歴史小話を・・・。
矢板小学校の特別棟がある場所付近は、今から400年以上も昔、「矢板城」というお城が建っていました。
つまり、特別棟を含めた三区公民館、ひばり公園、武道館、駐車場、NTTなどが建っている高台一帯は、この矢板城の跡地になります。

矢板城は、塩谷氏の重臣矢板重郎盛兼によって築かれ、その後代々矢板氏の居館になったと考えられていますが、その歴史はほとんど伝承がなく定かではありません。
塩谷氏の居城である川崎城の北の守りの支城として機能しており、平城ではありましたが、やや高台に城が築かれていました。
この高台にあたる場所が、現在の特別棟の北側にある三区公民館です。
戦国時代に矢板城の物見台として使っていた三区公民館の小高い所は、現在、権現様の古墳となっており、「矢板城跡碑」が建っています。

矢板城は、南側の一段低い土地に広がる湿地帯と、城の東を流れる人工の用水路である富田堀(現在の塚原川)を天然の要害とし、北に土塁を築いて防御を固めていました。
現在の矢板小学校の敷地の東側半分(新校舎、児童館、校庭東側一帯)は、当時は沼地のような湿地帯が広がっていたことになります。
矢板城の廃城後、この場所は「たたり山」と呼ばれ、城の土塁などがそのまま残されていました。
でも、明治時代に入り、学校の建設などの開発によって遺構が徐々に破壊され、土塁の土も矢板駅の建設や近くの窪地の埋め立てに使われて、現在はその遺構のほとんどを失っています。
ただ、三区公民館あたりは、現在も周囲よりやや小高くなっており、なんとなくお城があった面影が残っています。
↓矢板小学校北側の三区公民館入口。画像真ん中に、「矢板城跡碑」が確認できます。

矢板の歴史に興味をもった方は、ぜひ矢板市郷土文化研究会から発行されている「矢板の伝説」を御覧になってみてください。
矢板城にまつわるさらに詳しい歴史話やちょっとこわ~い話?まで掲載されています。
また、矢板に古くから伝わる様々な歴史や昔話がたくさん紹介されています。
ちなみに、「矢板の伝説」は、前編と後編があるのですが、現在この前編と後編を一冊に編集して、「合冊版」を発行する準備を進めています。
(筆者もこの矢板の伝説合冊版発行準備委員会の一員なので、この場をお借りして宣伝させていただきます)
「矢板の伝説」前篇・後篇は矢板図書館にも置いてありますが、筆者も数冊持っていますので、まだ読んでいない方・読んでみたい方は声をかけてくださればお貸しします。
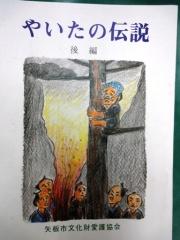
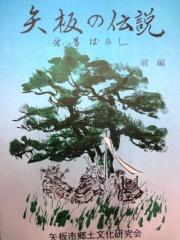
私たちの故郷「矢板」の歴史に、じっくりと思いを馳せてみるのもおもしろいですね。



